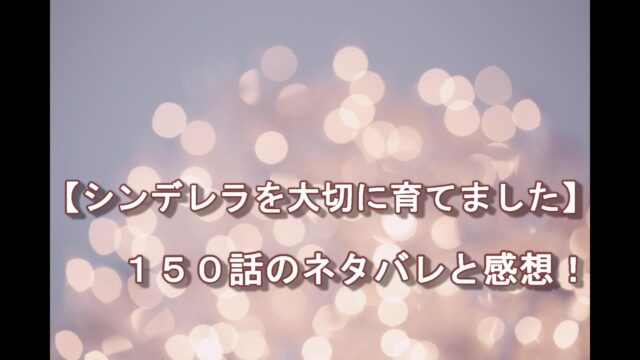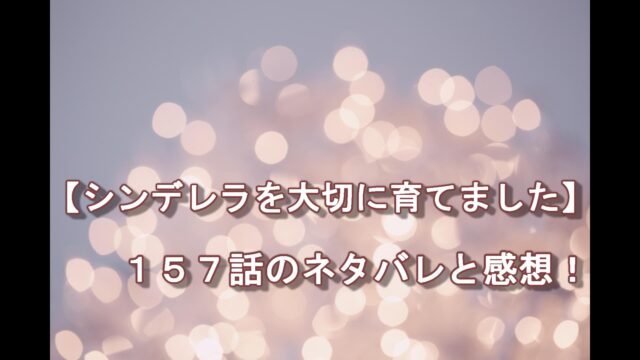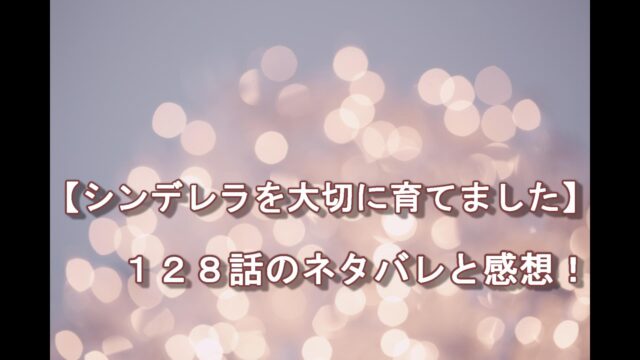こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

219話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 試験中断④
その時、扉の外から侍従が静かに入ってきて、国王に告げた。
「ウィルフォード男爵がお目通りを願っております。」
国王の顔に、興味を引かれたような表情が浮かんだ。
一体何事だろうか。
国王は、ダニエルがミルドレッドのために、クレイグ侯爵がいるこの場に現れたと確信しているに違いない、と考えた。
そうであれば、ミルドレッドを助けようということだ。
国王はそこまで考え、肘掛けを軽く叩いて言った。
「入れよ。」
しばらくして、侍従たちがダニエルのための椅子を用意すると、彼が入ってきた。
余裕のある態度で部屋に入ったダニエルは、まず国王に挨拶をする。
「お会いする機会をいただき、ありがとうございます。」
「座れ。」
事が面白い方向に進んでいる――国王は、むすっとした表情を浮かべるクレイグ侯爵と、同じくむすっとした表情のミルドレッドを見比べて微笑んだ。
クレイグ侯爵が不機嫌なのは理解できるが、バンス夫人まで同じ表情をしている理由は分からない。
ダニエルはミルドレッドがむすっとしているのを見て、くすっと笑う。
彼は、彼女がなぜ不機嫌なのかを知っていた。
自分で調べれば分かることなので、助けてやる必要はないということだ。
国王も、ミルドレッドならうまくやれると分かっている。
だが、それを黙って見ているだけというのも性に合わなかった。
「クレイグ侯爵が、バンス家のビーヌがあまりにも高く売られていると申しておりました。」
すると、国王は表情を変えずにダニエルを見やった。
その話はすでにバンス夫人が反論した件だ。
国王は、ウィルフォード男爵がどんな反論をするのか興味を持つ。
「しかし先日、ビーヌ商組合で面白い話を耳にしました。ここにおられるクレイグ侯爵が、ビーヌ工房の出資者だと伺いましたが?」
もちろん知っている話だ。
だが、国王は一部知らなかったふりをして、クレイグ侯爵を見る。
案の定、侯爵の顔色は一変した。
「投資家だと?」
短い一言だったが、国王の口調はまるで「国のためを思っての心配など嘘で、自分の事業を妨害されるのを恐れてクレイグ侯爵が口実を作っているだけだ」と言っているように聞こえた。
侯爵は慌てて弁明するように言った。
「はい、陛下。しかし私はただの投資家にすぎません。それに比べ、こちらのバンス夫人のビヌ工房の社長は、なんと彼女の娘だそうで。」
国王もそれを知ってはいたが、あえて知らぬふりをして驚いた表情を浮かべた。
その表情を見た侯爵は、再び得意げになって言葉を続けた。
「私が懸念しているのはまさにそこなのです、陛下!この女は……」
その瞬間、クレイグ侯爵はぴたりと動きを止めた。
彼は無意識のうちにダニエルを振り返り、顔を青ざめさせながら国王を見る。
そしてどもりながら、言葉を継いだ。
「ここにいるバンス夫人は、次女を工房の社長に据え、長女を王妃候補の座につけた。明らかに何らかの策略があるのは明白です。」
「三女です。」
「何?いや、え?」
「次女ではなく三女です。工房の社長に就いたのは三女のアシュリーです。」
ミルドレッドの指摘に、クレイグ侯爵は呆れた表情を浮かべたが、すぐにダニエルの視線を意識し、小声で自分の発言を訂正した。
「ああ、はい。次女ではなく三女ですね。」
「それと侯爵、先ほどは『何も知らない女が商売などできるはずがない』とおっしゃいましたよね?でも先ほどご自身で、『ウィルフォード男爵が背後で支えている』とも言われましたが、その二つの発言は矛盾していると思いませんか?」
再びクレイグ侯爵の顔に血が上った。
ダニエルは、侯爵の言葉の一部は正しいと言うべきかどうか、心の中で迷い始めていた。
確かに、彼はミルドレッドの背後を支えてはいる。
しかし、その支え方は侯爵が考えているようなやり方ではない。
そのとき、国王が再び口を開いた。
「まあ、誰が後ろ盾になっているかは重要ではない。バンス夫人とウィルフォード男爵は非常に親しい間柄なのだからな。」
「その通りでございます、陛下!」
思いがけず国王が自分の味方をしてくれたと思った侯爵は、嬉しそうに同意し、うなずいた。
つまり、この陰謀の背後にバンス夫人がいようと、ウィルフォード男爵がいようと、大した違いはないということだ。
彼は、ウィルフォード男爵とバンス夫人の両方に後ろ盾がある以上、バンス嬢を王太子妃候補から外すべきなのはもちろん、国王にも二人とあまり親しくなりすぎないよう釘を刺したかったのだ。
しかし国王もまた、侯爵のそうした考えを見抜いていた。
彼はダニエルを見ながら言った。
「そしてここ、クレイグ侯爵のビールは誰に対しても安く売ったり、無料で分け与えたことはなかったのだから、ここで議論すべきなのは、むしろ夫人がビールを無料で分け与えたことにどんな意味があるのかということだろう。」
「おっしゃる通りです、陛下!非常に見事なご指摘です!」
執事は侯爵の味方としてうなずくようだった。
ダニエルは腹を立て、再び得意げな侯爵をじっと見て冷笑する。
そして国王に言った。
「私がビールを分け与える際に、どの階級であっても差別がなかったことを証明する証人を連れてまいりました。」
証人を連れてきただと?
侯爵はもちろん、ミルドレッドも驚いた。
ダニエルの顔も引き締まった。
彼は二人を無視し、国王に願い出た。
「この場に、その証人の同席をお許しください。」
「証人だと?」
国王は興味深そうな表情で尋ねる。
つい先ほどまで、クレイグ侯爵とバンス夫人は互いに「証人を連れてこい」と言い合っていたのだ。
クレイグ侯爵は「ビヌを無償で受け取った貴族を連れてこい」と言い、バンス夫人は「欲しいと言ったのに受け取れなかった貴族を連れてこい」と主張していた。
国王は、証人がいないから話が流れたのだと思っていたが、どうやらそうではなかったらしい。
彼はダニエルにもう一度尋ねた。
「その者を呼ぶ前に、どうして証人になれるのか教えてくれ。」
「簡単なことです。バンス家から送られたビヌを受け取ったのです。」
「貴族ですって?」
クレイグ侯爵が口を挟んで尋ねた。
ダニエルは片方の眉を上げ、冷ややかに言った。
「そうでなければ証人にはなりませんでしょう?」
クレイグ侯爵が眉をひそめたのと同時に、国王は証人を入れるよう命じた。
その言葉に従い、侍従が外で待機していた人物を中に招き入れ、声を張り上げた。
「リンダ・カーシー夫人とレジナ・ヘンリー伯爵夫人でございます。」
二人とも記憶がかすむほど存在感の薄い人物だったため、国王の眉間にしわが寄った。
ヘンリー伯爵のことは知っている。
先代ヘンリー伯爵は数年前に亡くなり、三人の息子のうち長男が伯爵位を継いだが、兄弟仲は良くなかった。
しかしヘンリー伯爵夫人とは誰だっただろうか?
その近くにいた者が「ヘンリー伯爵夫人は以前…」と囁いた。
病で亡くなったとき、ヘンリー子爵が自分より10歳も年下の二番目の妻を迎えていたことを思い出した。
「このお二人が証人です。」
侍従たちが用意した椅子の前に、二人の貴族夫人が両手を揃えて立った。
ダニエルに紹介され、二人の顔に緊張が走る。国王とこれほど近くで向かい合うのは初めてだった。
ヘンリー子爵夫人は、思わず口を開きかけ、驚いて動きを止めた。
その様子を見て、ミルドレッドの表情が険しくなる。
二人とも、彼女からビヌを送られた人物だった。
もちろん、ミルドレッドが送ったのはビヌだけではない。
国王は、バンス夫人の表情が曇ったのを見て不審に思い、ヘンリー子爵夫人に尋ねた。
「バンス夫人から何か受け取ったと聞いたが?」
「陛下、私がヴァンス夫人からいただいたものは本当にたくさんございます。」
そうか?
国王の顔に驚きの表情が浮かんだ。
彼はミルドレッドを一度見やり、それから続けるようにと促すような視線をヘンリー伯爵夫人に向けた。
伯爵夫人は国王の許しが下りると、思わず深呼吸をしてから再び口を開いた。
「ヴァンス夫人は親切にも私にたくさんの贈り物をくださいました。茶やチョコレートのような品はもちろん、最近ではビヌも使ってみるようにと送ってくださいました。」
ビヌを送ったという言葉に、国王は再びミルドレッドを見やった。
彼女は背筋をぴんと伸ばし、国王を見返していたが、その顔には満足げや誇らしげな表情はまったく見られなかった。
奇妙なことだ。
国王はカーシー夫人に向き直った。
「カーシー夫人と言ったか。」
「はい、陛下。ジェームズ・カーシー男爵は私の夫です。」
ジェームズ・カーシー男爵という名を聞き、国王の脳裏にぼんやりと記憶が浮かんだ。
馬車の事故で亡くなったのだったか、それとも病で死んだのだったか。
はっきりとは思い出せないが、若い人物が突然亡くなったことに同情した記憶があった。
「ああ、そうだ。カーシー男爵夫人。」
今はカーシー夫人だが、リンダは国王が自分を覚えていたことに、かすかな笑みを浮かべた。
すでに再婚していると思っていたが、姓が変わっていないということは、再婚していないということだろう。
国王は思わず尋ねた。
「どう過ごしていたのだ?」
カーシー夫人の表情がわずかにこわばったが、すぐに和らいだ。
彼女はミルドレッドを一度見やってから言った。
「陛下のお心遣いのおかげで、元気に過ごしておりました。」
嘘だ。
同時に礼儀正しい模範的な答えでもあった。
王は彼女がミルドレッドを見ていたことを思い出し、くすっと笑った。
そして尋ねた。
「そうか、お前もヴァンス夫人から贈り物を受け取ったのか?」
「はい、陛下。」
国王はそのまま椅子にもたれ、机の上に置いていた手の指を組みながらクレイグ侯爵に尋ねた。
「お前が求めていた証人が出てきたようだが、どう思う、侯爵?」
「彼らは皆、ヴァンス夫人と親しい間柄ではありませんか?」
国王にそう言ったクレイグ侯爵は、くるりと視線をミルドレッドに向けた。
「親しい者に贈り物をしたことを証拠として持ち出すのは、恥ずかしくはありませんか?」
しかし証人として連れてきたのはミルドレッドではなくダニエルだった。
ダニエルは自分が連れてきたのだと説明しようとしたが、それより先にヘンリー子爵夫人が険しい表情で口を開いた。
「恐れながら陛下、私の名誉にかけて申し上げます。私はバンス夫人とは親しくございません。」
国王の眉がぴくりと上がった。
場の空気が凍る中、国王は一度ダニエルを見やってから、今度はカーシー夫人に尋ねた。
「そなたもバンス夫人とは親しくないと言えるのか?」
「おお、陛下、私は…ええと…よく分かりません。バンス夫人には多くの助けをいただき、彼女を知ってはおりますが…好きだと言っても、私がヴァンス夫人を友人だと呼んでいいものかどうか…。」
一体これは何の状況なのか。
国王は眉を上げたまま、カーシー夫人とヘンリー伯爵夫人を見やった。
そしてクレイグ侯爵に言った。
「これで十分ではないか?そうだろう?」
もちろん、クレイグ侯爵は何も言えなかった。
その顔が赤く染まっていくのを見たダニエルが、淡々と口を開いた。
「必要であれば、もっとお連れすることもできます。」
つまり、ヴァンス夫人から贈り物を受け取った貴族がまだいる、ということだ。
国王は目の前にいる五、六人を一人ずつ見渡し、再びクレイグ侯爵に言った。
「これ以上知らせることがないのなら、もう下がってもらってもいいぞ、クレイグ侯爵。」
これ以上言うことはない。
腕を胸に組んだままのクレイグ侯爵は険しい表情を崩さなかった。
国王は今度は机に身を乗り出し、ミルドレッドを見やった。
彼女もまたクレイグ侯爵に劣らぬ厳しい表情で、背筋を伸ばして座っていた。
「敵を退けたというのに、あまり嬉しそうではないな、バンス夫人。」
国王の言葉に、ミルドレッドの目が見開かれた。
彼女は一度ダニエルを振り返り、それから国王に向き直って深く一礼し、ため息をついて言った。
「恐れながら陛下、私はクレイグ侯爵を敵だとは思っておりません。ここにいる者は皆、この国の臣民であり、陛下に忠誠を誓う者たちでございます。」
完璧な答えに、国王はにやりと笑い、ダニエルは口元を手で覆った。
そして国王は再びミルドレッドに向かって問いかけた。
「しかし、王太子妃の座をかけて争う者としては、勝利を収めたのだから気分がいいでしょうね。」
そんなことはない。
ミルドレッドは全く違うと言いかけて口をつぐんだ。
彼女はアイリスをかけて他の家と競い合っているわけではない。
アイリスが叶えたい夢のために手助けをしているだけなのだ。
ミルドレッドはひとつ息を吐いた。
張り詰めていた彼女の姿勢が崩れた。
「陛下、ここに来たお二人の夫人は、私を助けるために勇気を出して陛下の前に出てきてくださったのです。」
ミルドレッドの言葉に、王の視線がカーシー夫人とヘンリー伯爵夫人に向けられた。
二人ともミルドレッドの言葉に顔を赤らめていた。
カーシー夫人は否定しようとしたが、結局何も言えなかった。
ダニエルが連れてこなければ、ヴァンス夫人を助けなければならない立場にあったのだ。
そう考える余地もなかった。
そして、それはレジナも同じだった。
レジナは、もしダニエルが自分を訪ねてきたのなら不思議に思っただろう。
彼女はマーフィ伯爵夫人を通じて、ミルドレッドの仕事を手伝ってほしいという依頼を受けたが、断った。
代わりに贈り物を渡すという提案も拒否した。
それは彼女が、そんなことは高潔でも名誉あることでもないと考えたからだ。
しかしその後も、バンス夫人はしばしばレジナに贈り物を送ってきた。
何も助けないと言っていたにもかかわらず。
価値のない贈り物なら問題ないと思ったのか。
あるいは、いつか今日のような日が来ると考えていたのか。
どちらなのか気になったが、レジナはダニエルの話を聞き、すっかりバンス夫人を庇う決心を固めた。
「そうか。」
国王はミルドレッドの言葉を受け、再びカーシー夫人に向き直った。
そしてヘンリー伯爵夫人を見やった。
ヴァンス夫人は、もしビヌを買うのが負担になるほど生活が苦しい人であれば、身分に関係なく分け与えていたと言ったのだ。
つまり、それは目の前の二人がビヌを買うのが負担になるほど困窮しているという意味になる。
果たして――国王はミルドレッドの言葉を思い返しながら、カーシー夫人とヘンリー伯爵夫人の様子を観察した。
二人はきちんとして毅然とした態度を保っていたが、宮中に入る際に人々が着ている服と比べれば、とても質素で目立たないものだった。
「伯爵夫人。」
国王は、ヘンリー伯爵が今、自分の義母がここに来ていることを知っているか気になり、尋ねた。
「先ほど、ヴァンス夫人と全く親しい関係ではないとおっしゃったのに、なぜ証人として出てきたのですか?」
「彼女が私にくれた物を返さなければならないと思ったからです。」
「バンス夫人は何を贈ったのだ?」
レジナはしばしミルドレッドを見た。
その表情には、カーシー夫人のような親しみや感謝の色はなかった。
無表情のままミルドレッドを一瞥し、再び国王に顔を向けて答えた。
「先ほど申し上げた通り、バンス夫人は私に多くの物を送ってくださいました。お茶やケーキのような物を贈ってくださったこともあり、ビヌの価格が上がると、週に一度ビヌも送ってくださったのです。」
そこまで話すと、ヘンリー子爵夫人は思い出したように付け加えた。
「最近では、王太后陛下から下賜されたという名目で、もう一つビヌを送ってくださったこともあります。」
「おお、それは本当に王太后陛下がお下しになったものですよ。」
驚いたミルドレッドが慌てて言った。
レジナはミルドレッドを一瞥し、再び国王に向かって言った。
「陛下、ヴァンス夫人の助けは、私が求めたり要求したものではございません。ですが、確かに必要ではありました。そしてウォルフォード伯爵は、私にあるがままの事実だけを述べればよいとおっしゃいました。」
今度は人々の視線がダニエルに向けられた。
彼は背筋を伸ばして座ったまま、何も知らないという表情を浮かべていた。
レジナはきっぱりと姿勢を正し、続けた。
「であれば、あるがままの事実を述べるくらいはすべきだと考えただけです。」
――こういう人なのだ。
ミルドレッドはレジナがどんな人物なのかをはっきり理解した。
これまで茶やケーキのような物を何度か送ったが、彼女からは一度たりとも感謝や「いただきます」という返事すらなかったのだ。
ミルドレッドも、それはきっと自尊心のためだろうと考えていた。
衣服や砂糖、食材のようなものは丁重に断ってきたからだ。
ヘンリー子爵夫人も、知人同士のやり取りとして差し障りのない程度の贈り物しか受け取らず、
一度もミルドレッドに直接連絡をしたことはなかった。
だから、今この場にレジナが来ていることに彼女は驚いた。
誰に対してもミルドレッドの助力を受けたことを認めないだろうと思っていたからだ。
しかし、今こうして国王に向かって話す様子を見て理解した。
レジナにとってケーキやお茶程度なら、自尊心を傷つけずに返せる恩だと考えていたのだ。
そしてその恩を返す機会を逃さなかったのだ。
「そうか。」
王はそう言いながら、顎を撫でた。
助けるために出てきたわけではないという話に、彼はますますヴァンス夫人を気に入った。
しかし同時に、ヴァンス夫人がビヌを買うのが難しい人々にだけビヌを送ったという話が思い浮かんだ。
彼はレジナに尋ねた。
「母上を世話してくれたので、ヘンリー伯爵はヴァンス夫人に感謝しているだろうな。」
レジナの表情がこわばった。
彼女の三人の息子は、父親が亡くなった後、若い継母を受け入れようとしなかった。
彼らは小さな別邸にレジナを送り込み、その存在自体を無視していたのだ。
せいぜい三男がたまに小遣い程度のお金を送ってくるだけであった。
「ヘンリー伯爵は、おそらくご存じないでしょう、陛下。彼は忙しくて、私の交友関係まで把握するのは難しいでしょうから。」
レジナの言葉に、国王の目が細められた。
だが彼は何も知らぬふりをし、顎をさすりながら言った。
「そうか。話は終わったようだな。帰ってもいい。ウルフォード子爵は、もう少し私と話をしていこう。」
帰ってよいという王の言葉に、三人の女性が席を立った。
ダニエルもミルドレッドをエスコートするため立ち上がり、こう言った。
「私の馬車をお使いください。奥様がお乗りになった馬車にそのままお乗りいただけます。」
ダニエルの馬車は私用のもので、貴婦人方を送り届けるという意味だ。
その申し出に、ミルドレッドは微笑んだ。
「ああ、それと王子を連れてきて。」
侍従が三人を案内するために扉を開けて出て行こうとしたとき、国王が再び命じた。
リアンを?――ミルドレッドの視線がダニエルへと向かう。
彼女の頭の中に、ある一つの仮説が浮かんだ。