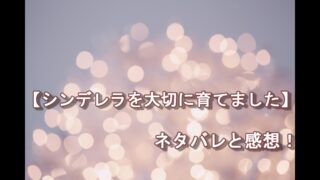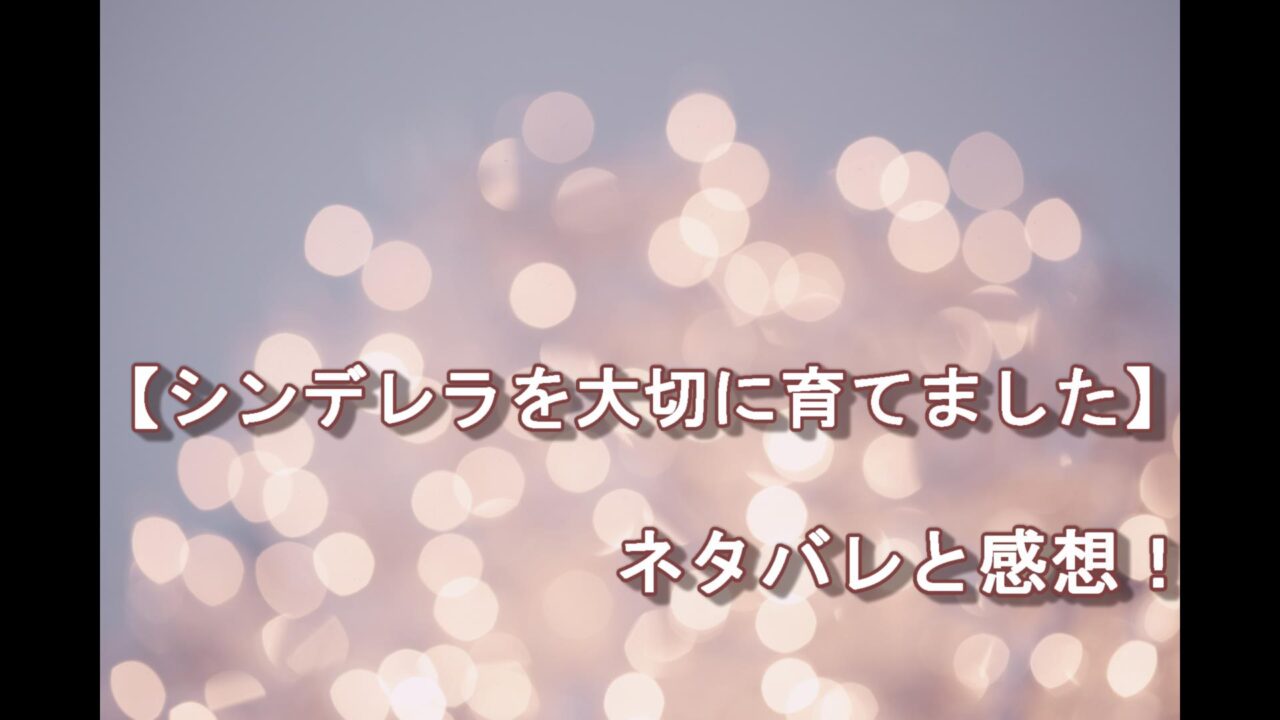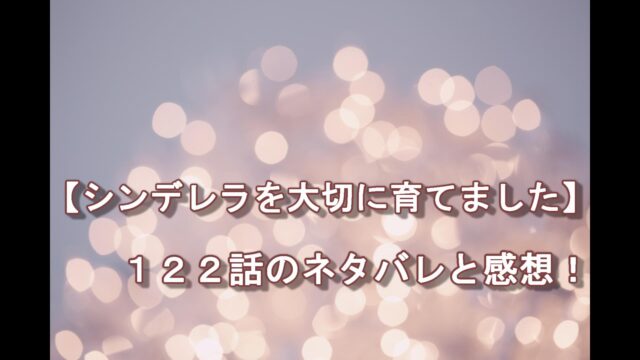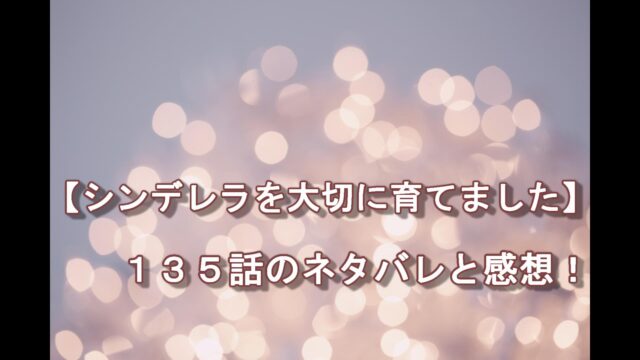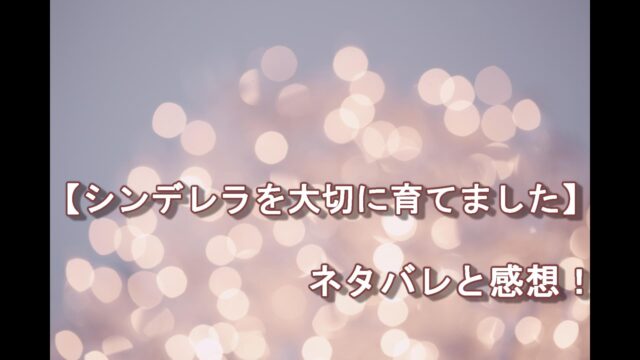こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

167話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 結婚観④
私はため息をつきながら言った。
「もしダニエルが後継者を望むなら、この年齢で息子を産むまで妊娠しろってことになるけど、私には無理よ。」
子供たちを育て上げ、快適な家で自分一人で悠々と暮らそうと思っていたのに、若い男に出会ってまた妊娠しろだなんて?
もういいわ。
ダニエルは本当に素敵な人で、素晴らしい男性だけど、命をかけて後継者を産むべきかどうか考えると、ちょっと悩むわ。
私は三十一歳だし、もう若くない。
この国でこの年齢で妊娠・出産をするというのは、簡単に言えば命を捧げるということだ。
私が生きてきた場所は少し違うかもしれないけど、この国では十九歳のアイリスが子供を産むことさえ反対したいくらいだ。
「でも、結婚するということは子供を産むという意味でしょう?」
アイリスが困惑した表情で言った。
それも無理はない。
特に貴族なら、女性の義務には後継者の出産が含まれているからだ。
私はため息をつきながら言った。
「男が恋人なのに、なぜ男が産まなくて、女が産まなきゃいけないの?」
「お母様ったら。」
私が冗談を言ったと思ったのか、アイリスが笑い出した。
しかし、私は真剣だった。
私はアイリスの肩を引き寄せながら言った。
「そうでしょう?私が産んだのに、なぜ私の姓ではなく、男の姓を継がなければならないの?」
「それは・・・。」
まだ笑みを浮かべているアイリスが言い訳しようとしたが、彼女の顔から笑みはすぐに消えた。
それが当然のことなの?ねえ、本当に、それが当然なの?
私はじっと立ったままアイリスの顔を見つめた。
不公平じゃない?
私が産んで、私がまだ生きているのに、なぜアイリスとリリーは二度も姓を変えなければならなかったの?
この子たちは「バーンス」という姓を使っているが、バーンスの人間じゃない。
だからと言ってリベラ男爵家の人間かといえば、それも違う。
ジム・リベラ男爵は遠い親戚で、子供たちを登録しただけだから。
少しでもアイリスとリリーの面倒を見たのは、私の親戚であるマーフィ伯爵だった。
でも、この子たちは「バーンス」という姓を使っている。
「アイリス、どう思う? もしあなたがリアンと結婚したら、アイリス・シャクレルになれるわね。」
その瞬間、アイリスの顔が赤く染まる。
えっ? なんで照れてるの?
私は困惑して彼女を見つめ、それからようやく理由に気づいた。
アイリス・シャクレル。
アイリスはそれを恥ずかしがっているようだ。
私はそんな彼女が可愛らしくて笑い声を上げた。
こんなことを考える自分が可笑しい。
私がかつていた場所でも、恋愛が話題になると誰々夫人と呼ばれることがよくあったから。
いつも落ち着いて見えたアイリスが、十九歳の女の子らしく感じられた。
まったく、私の十九歳の娘が王太子妃試験を受けているなんて。
これはちょっと早すぎない?
結婚は三十歳を過ぎてからでもいいじゃない。
「お母さん?」
私の肩を抱きしめながらアイリスが私を呼んだ。
私は彼女の顔が見えるほど体を起こし、静かに言った。
「あなたが王妃になるなら、アイリス。あなたは後継ぎを産まなければならないわ。それは男の子が生まれるまで妊娠し続けなければならない、ということよ。」
アイリスの表情が硬くなった。
まだ十九歳の娘にこんな重荷を背負わせたいわけではない。
しかし、同時に彼女が理解すべき問題でもある。
いつ男の子が生まれるか分からない。
50%の確率だと言われているけれど、私は二度とも女の子を産み、三番目の子供は私の実子ではなかったものの、それも女の子だった。
私は深いため息をつき、言った。
「アイリス、あなたたちを産んだことを後悔しているとか、そういう意味じゃないのよ。分かってる? あなたとリリーが私の娘で本当に幸運だと思っている。あなたは私にはもったいないほどの娘よ。」
聡明で責任感の強いアイリス。
しかし彼女は女性であるがゆえに、どれほど聡明であろうともその才能を発揮する場が限られてしまう。
「分かってます。」
アイリスは軽くうなずきながら、口を結んで答えた。
「私はあなたがリベラの男爵になれたらと思っている。」
私はそう言いながら、もう一度ため息をついた。
アイリスがリベラ男爵になれば良いのにと思う。
この子は聡明で責任感が強いのだから。
「良い男爵になるでしょう。」
アイリスの体が一瞬緊張したかと思うと、力が抜けたようだった。
そして彼女は、ありえないと言いたげに言った。
「ええ、私がどうやって男爵になるんですか?」
「どうしてなれないの?」
「女性は爵位をもらえないじゃないですか。」
「それが問題だ。」
私はアイリスの瞳をまっすぐ見つめながら言った。
「そうだね。」
ゆっくりとアイリスの瞳にいくつかの感情が浮かび上がった。
私は彼女の瞳に疑問と驚きが現れるのを確かに見届け、こう続けた。
「お前がウィルフォード男爵の娘になれば、王太子妃の試験で有利になるかどうか、ウィルフォード卿に尋ねてみるよ。もう寝よう。」
アイリスは呆然と私を見つめたまま、何かを考えるような表情で階段を上り始めた。
私は階段下に立ち、彼女が無言で上っていくのを見守った。
・
・
・
「どうしてそこにいるんですか?」
アイリスが上の階に到着して間もなく、ダニエルが現れた。
彼は外に出ていたのだろうか、彼の靴には泥がついていた。
私は腕を組んで彼を見つめた。
「まさか私を待っていたんじゃないでしょうね?」
ダニエルがからかうように尋ねた。
その「まさか」が的中した。
彼の顔に浮かんだ笑みは、私の表情を見て信じられないという顔に変わった。
「え、本気なんですか?」
「ちょっと聞きたいことがあって。」
「何ですか?」
彼がさらに近づくと風の匂いが漂ってきた。
そして草の匂いも。
散歩でもしていたのだろうか?
私はダニエルの腕に手を置いて洗濯室に向かおうと体を回しながら口を開いた。
「もしアイリスがウィルフォード男爵の娘になったら、王太子妃試験で有利になると思う?」
ダニエルの顔には奇妙な表情が浮かんだ。
あちゃ。私はすぐに言葉を付け足した。
「だからといって、あなたに結婚を申し込むつもりはないわよ。」
「ええ。ただ気になったから聞いてみただけですよね。」
正確に言うと、私ではなくアイリスが気になっているのだが。
私の弁解にダニエルの顔は再び穏やかにほころんだ。
彼は肩をすくめるようにして言った。
「大差はないでしょう。どうせ推薦したのは君ですから。」
そうか。
考えてみれば、結局アイリスが候補者になれたということは、背景に問題がなかったということだ。
その後の試験は候補者の実力を試すものだから、父親や推薦者は関係ないかもしれない。
「でも、それが理由で私に求婚しないというのは、結婚する気があるという意味ですか?」
アイリスについて一人考えていたら、私の歩調に合わせていたダニエルが尋ねた。
え?私は戸惑いながら彼を見つめた。
「ああ、まあね。状況次第だろう。」