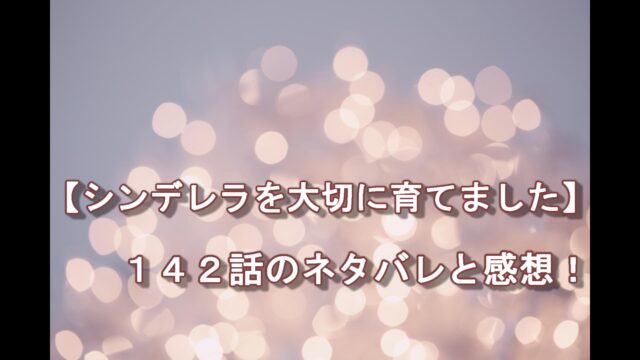こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

199話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 後継者②
「バンス夫人がウォルフォード男爵夫人になれると思うか?」
その翌日、まったく同じ質問を王太妃から受けたダニエルは、自分でも気づかないうちに険しい表情を浮かべていた。
この二日間、異なる人たちから同じ質問を何度も聞かされ、気分が妙にならざるを得なかった。
しかしその表情を違った意味で受け取った王大妃は目を細めながら再び尋ねた。
「私が年を取って判断力が鈍ったとでも?」
「いえ、殿下のご判断は正しいです。」
ダニエルはすぐにそう答えたが、王大妃の表情は和らがなかった。
彼女はダニエルをじっと見つめながらさらに尋ねた。
「何か気になることでもあるのかい?」
「いいえ。最近、似たような質問を受けただけです。」
王大妃の顔にかすかな笑みが浮かんだ。
それはつまり、みんながダニエルの本音を見極めようとしているということ。
誰が見てもミルドレッドとダニエルはお互いに大切に思っていたからだ。
誰かにとっては社交界で人気を集める貴族の令嬢には見向きもしなかったくせに、結局付き合う相手は夫を二度も亡くした、少し派手な未亡人だと陰口を叩く者までいた。
そして王太妃も、ミルドレッドよりはダニエルに近しいだけに、そういう考えを抱かなかったとは言い切れなかった。
「誤解しないで聞いてね。」
王太妃は食器を置き、茶杯を持ち上げながら言った。
「誤解しないで聞いてね」とは、誤解の余地がたっぷりあるという意味だ。
ダニエルは目を細めてカップを悲しげに見つめた。
呆れたようなその態度に、王太妃はくすっと笑いながら言った。
「私はバンス夫人が好きよ。気が利くし、センスもいいほうでしょう?自分が産んだわけでもない子どもたち三人を立派に社交界デビューさせたのだから、その手腕は称賛に値するわ。」
現在、社交界ではアイリスとリリー、アシュリー、彼女たちは有名だった。
名前は知らなくても、「バンス家のあの令嬢たち」と言えば誰でも分かるほど。
これは決して簡単なことではない。
ほとんどの貴族の結婚は「どこの家に結婚適齢期の令嬢がいるか」という情報から始まる。
存在感のない未婚女性が結婚市場に足を踏み入れるのは難しい。
もちろん、その存在感が非常に強くなくても、少なくとも「不快感を与えない」程度ではなければならない。
それは、行動はもちろん、服装や家庭内のあらゆる部分で不快感を与えないという意味であり、バンス家はその点では少し気になる面があった。
しかし、ミルドレッドはそのような不利な条件の中でも、子どもたちの社交界デビューを成功させ、アイリスとアシュリーの印象を肯定的に導いた。
リリーについては評価が少し分かれるが、それでも悪くはないレベルだ。
あの貧しい未亡人がやってのけたことだった。
王太妃はミルドレッドのそうした点が気に入った。
最初に会った時に感じたやや荒っぽい印象は、女一人で娘三人を育てるにはそのくらいの性格は必要だという好意的な印象に変わっていた。
「でも、バンス夫人は年を取りすぎてるわ。三十五歳だったかしら?」
「三十七歳です。」
すぐに答えたダニエルの返答に、王太妃の目が細められた。
この状況でミルドレッドの年齢がさらに増えるのは決して歓迎すべきことではなかったが、それでもダニエルは落ち着いて紅茶を口にしていた。
「そう、三十七歳。もう結婚の準備をして結婚したとしても、三十八歳か三十九歳でようやく結婚式ができるでしょうね。その家の長女は王太子妃候補の試験を受けているところだから、もしかするとあと数年待たなければならないかもしれないわ。」
アイリスが王太子妃になるなら、彼女もまた結婚の準備をしなければならない。
同じ家で母娘が同じ年に結婚するのは見栄えがよくないため、ダニエルがミルドレッドと結婚できるのは早くても彼女が39歳になる頃だろう。
王大妃が何度も進言しても、ダニエルは依然として冷静さを崩さなかった。
その姿に王大妃はため息をついた。
三十を過ぎても結婚の意志も婚約の話もなく、紹介される女性たちにも全く興味を示さない態度を取り続けた結果、彼の目にとまったのが、子どもを三人も持つ寡婦とは——。
まぁ、それはまだ理解できる。
王大妃は運命の愛を信じていたし、もしミルドレッドがダニエルの運命の相手であるならば、支えてやる覚悟もしていた。
「でも後継者ができるのが遅すぎるんじゃない?もうすぐ四十になるというのに、子どもを持つつもりはないのかしら?」
子どもを持つ気がないと答えたなら、王大妃はどんな顔をすればいいのだろうか。
ダニエルは苦笑いしながら茶杯を置いて尋ねた。
「それで、殿下はどうお考えですか?」
しばらく食堂の中に沈黙が流れた。
王太妃はカップを置き、背後に立っていたジャクス伯爵夫人に目配せした。
その目配せに気づいた伯爵夫人は体を翻し、食堂の外へと出て行く。
彼女に従っていた侍女と使用人たちも伯爵夫人の後に続いた。
王太妃の食堂には彼女とダニエルだけが残った。
何か言いたいことがあるのだろうか。
ダニエルは目を細め、人々が退出する様子をじっと見つめていた。
夏仕様に飾られた王太妃の食堂には、窓ごとにレースのカーテンが風にそよいでいた。
どこからか鳥のさえずりが聞こえてきたが、二人ともそれには耳を傾けなかった。
王大妃は杯を持ち上げ、口をつけたあとゆっくりと置いた。
そしてダニエルを見つめながら穏やかに言った。
「子どもをもうけるつもりはないの?」
無茶な質問に一瞬、ダニエルの目が見開かれたが、すぐに元の表情に戻った。
彼は目の前の老婦人が王大妃であり、年配であることを思い出した。
ときどきこのような人たちは、本当に欲しいもののために自分の基準すらも変えてしまうことがある。
頑固で融通が利かないことで知られる王大妃でさえ、後継者のこととなると、未婚女性の突然の妊娠というありえない事態まで受け入れるつもりでいるらしい。
ダニエルは姿勢を正した。そして静かに口を開いた。
「バンス夫人にはすでに子どもがいます。」
「全員女の子でしょう。女の子が悪いというわけではないけれど。ただ、爵位を譲ることはできないでしょう?」
爵位。
王太妃の言葉に、ダニエルは苦笑した。
彼にとって爵位はそれほど重要なものではなかった。
望めば王に頼んで男爵より高い爵位を与えてもらうこともできる。
それをしなかったのは、男爵くらいで十分だと考えていたからだ。
「もし私がバンス夫人と結婚して、彼女が私の子どもを産んだとして、その子が女の子だったらどうするんですか?」
気分の悪くなるような状況に、王太妃の表情が一瞬こわばった。
しかし彼女はすぐに表情を整え、眉間と目尻を指で軽くなぞってから言った。
「男の子を産まなきゃ。」
「いつまでそんなことを言うおつもりですか?」
「いつまでって、何を言ってるの?」
再び王太妃の眉間にしわが寄った。
彼女の表情にダニエルが再び尋ねた。
「もしまた子どもが生まれて、それも女の子だったら?5人も6人も産んで全部女の子だったら、どうしますか?」
「その場合は仕方ないわね。爵位は息子にしか譲れないし、もし息子がいないまま夫が亡くなったら、妻と娘たちの将来は暗くなるから、多くの貴族の夫婦は息子を得るまで妊娠と出産を繰り返すのよ。」
「それでも妻が亡くなれば、多くの夫は新しい妻を迎えるわ。爵位を譲る息子を得るためにね。」
「もし妻が出産できなかったり、どうしても息子が生まれない場合は、遠縁の男子を養子にすることもあるの。いっそ、血縁の男の子を養子にするのがましだけど。」
「夫が別の女性に産ませた息子を連れてくることだって時にはあるわ。どちらにしても地獄ね。遠い親戚の男子を養子に迎えるなんて。」
後継者として育てることと、夫が他の女性に産ませた男の子を養子に迎えることとの違いの間で――。
ダニエルにはすべてが滑稽に思えた。
どうせ子どもを産むのは女性の役目だ。
自分が産んだ子の父親が誰かを知っているのは女性だけ。
夫人でもない女性に騙されて「自分の息子だ」と言われて育てていたのに、後で実子ではなかったとわかったという話は珍しくない。