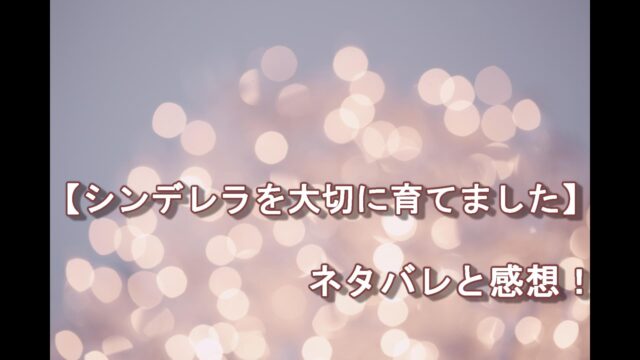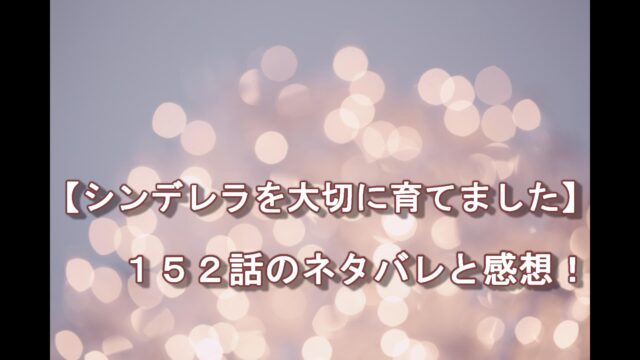こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

205話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 世の中の偏見
「友達が増えるのはいいことですね。」
ダグラスの言葉に、リリーはぱっと笑ってうなずいた。
「そうですね。話が通じる人と会話できるって、本当に楽しいことですよね。」
ダグラスの頭の中に、彼が水彩画と油絵の区別もつかなかった瞬間が浮かんだ。
その瞬間、自分の表情を見たリリーが慌てて視線を逸らした。
「競馬について語れる同僚と話すと楽しくないですか?」
「私は……」
リリーと一緒にいる方がいい。
ダグラスはリリーの顔を何時間見ていても飽きない気がした。
しかし彼がそう言う前に馬車が止まった。
「どうなさいましたか?」
ある男性と会話していたアトリエの主人は、ペアで入ってきた男女を見てすぐに尋ねた。
彼はダグラスとリリーの服装を見て一目で貴族だと察しただけでなく、二人がカップルだと思った。
男性の方は趣味で絵を描いているという、少々大胆なタイプに見えた。
もしかすると女性に肖像画を描いてあげようとして大きな声を出していたのかもしれない。
それならば、こうしたお客様には主人として最もありがたく、貴重なお客だ。
最大限の値を引き出せるはずだから。
しかし彼の予想に反して先に口を開いたのは女性側だった。
「最近エミリーという職人の帽子がいいって聞きました。」
主人の右側に立っていた男性が、リリーの言葉に彼女を見つめるのが見えた。
ダグラスも知らず知らずのうちにリリーの後ろにぴたりとくっついた。
「エミリーの帽子ですか?」
主人はそう尋ねながら右側に立っていた男性をじっと見つめた。
どういうこと?
リリーとダグラスが戸惑っている間に、主人はすばやくカウンター後ろの書棚から紙に包まれた帽子を取り出して尋ねた。
「何号になさいますか?」
何号?帽子に号数なんてあるの?
ダグラスが戸惑っている間に、リリーは自分に必要な靴の話をしていた。
そんな様子を黙って見ていた男がふいに聞いた。
「お嬢さんが履くのか?」
男の質問に戸惑ったのはリリーではなくダグラスだった。
しかし彼が口を開く前に、リリーが素早く言った。
「知ってどうするの?」
リリーの返しに、男と主人の顔に当惑の表情が浮かんだ。男は慌てて言った。
「いや、その……彼女は靴を見る目が高いと思って。」
ダグラスの目が細くなった。
こいつ、今何を言ってるんだ?
だが今回もリリーが先に口を開いた。
「なんで?あなたの周りの女たちは目がないわけ?」
「いや、そうじゃなくて……このレベルの靴を見分けられるって、すごいって褒めたつもりなんだけど。」
それが褒め言葉になるの?
ダグラスの表情が曇った。
すぐさまバンス嬢に謝ろうと声を上げようとしたとき、リリーがふっと笑って言った。
「市場に出てからまだそれほど経っていない帽子がこの程度の完成度なら、ダグがこの帽子を作った人ってことでいいでしょ?」
正解だった。
リリーの冗談に、男性はもちろん店主まで大いに戸惑い、ダグラスは動揺する二人を見て目を見開いた。
エミルは動揺して、しどろもどろに言った。
「え、ええ、そうよ。私がエミルよ。」
リリーの表情がぱっと変わった。
彼女は信じられないという顔でエミルを見てから、店主に帽子を返して言った。
「自分の作品が市場に出たばかりなのにあんなに得意げな人を見ると、その帽子、買う気になりません。包装はしなくていいです。」
「えっ?」
リリーの言葉に、主人は戸惑って包装していた手を止めた。
包装しないというのは買わないということだ。
エミルも口をぽかんと開けた。
主人はぼんやりとエミルとリリーを交互に見てからリリーに尋ねた。
「お嬢さん、買わないんですか?」
「はい。それじゃなくて、ただ使っていたものでいいです。」
「使っていたもので」という言葉に、主人はようやくリリーが以前来たことを思い出した。
ウィルフォード男爵と一緒に来た女性。
そのときに買った道具が、ウィルフォード男爵が使うためのものではなかったようだ。
主人は口をぽかんと開けてリリーの顔を見つめた。
まさかと思っていた噂が頭に浮かんだ。
ウィルフォード男爵がある女性に絵を教えているという噂。
くだらないと鼻で笑って忘れていたその噂だ。
「いや、お嬢さん、ちょっと待ってください……」
動揺したエミルがリリーに近づき、彼女の腕を掴もうとした。
リリーは帽子を返しながら、彼が無断で自分の体に触れようとするのを冷たい表情でじっと見つめた。
そのとき、ついに我慢できなかったダグラスが口を開いた。
「無礼だな。」
雰囲気が一変した。
エミルと店主はダグラスの威圧的な姿に思わず身をすくめた。
そして、それはリリーも同じだった。
いつもはすぐに怒ると思っていたダグラスの赤い髪が本当に燃えているかのように見えた。
彼は怒りを抑えながら言った。
「買おうとしてお金を出そうとしている客に、こんな無礼を働く店は初めてだ。」
正確に言えば、店というよりも、エミルが無礼だったわけだが、とにかく店主の顔色も真っ青になった。
ダグラスのはっきりとした言葉に、店主の顔には明らかに慌てた表情が浮かんだ。
エミルはリリーが言った「ケイシー卿」が、あの有名なフィリップ・ケイシーのことを指しているのかと驚いて目を大きく見開いた。
二人は、リリーがダグラスと一緒に店を出ようとするのを呆然と見つめながら、視線をそらせなかった。
「うちの店も今後、あなたの商品は扱わないから。」
店主はそう言いながら、エミルが作った帽子をすぐにすべて取り出し、カウンターの上に並べた。
値段のわりに品質の良い帽子を作るからと、みんなが褒めちぎっていたのが間違いだった。
店主は、ウィルフォードの模造品やケイシー卿の美学に従って帽子を選ばないようにしていたわけではなく、単純にバンス嬢の言葉が正しいと考えたのだ。
エミルが帽子を売り始めて、まだかろうじて一ヶ月ほど。
こんな程度でこれほど狼狽えるとは…。
もしそうなら、明らかにすぐに事件が起こるところだった。
その前に、主人は自分の店との関係を断ち切りたかったのだ。
主人の意図がはっきりと表れた行動に、エミルはぼんやりとした表情を浮かべていたが、主人が置いた筆をつかんで、ぱっと外に飛び出していった。
幸い、リリーとダグラスはちょうど馬車に乗り込もうとしていた。
ケイシー侯爵家の馬車。彼はようやく自分の目の前にいる相手が誰かに気づいた。
「お嬢さん、お嬢さん、少しだけお待ちください。」
リリーを先に馬車に乗せようとしていたダグラスの背後から、エミルが駆け寄り、叫んだ。
「お嬢さん!」
ダグラスは思わずエミルの肩をつかんで止めた。
怒って強くつかんだせいで、エミルは声も出せずに止まった。
肩が砕けそうだった。
彼は青ざめた顔でダグラスの腕をつかみ、懇願した。
「す、すみません。ですからお願いです……。」
少し情けない様子に、ダグラスはリリーの許可を求めるように彼女を振り返った。
まるで忠実な騎士のような態度に、リリーの目が大きく見開かれた。
彼女はダグラスとエミルを交互に見てから、帽子をつまんでみた。
「す、すみません、お嬢様。身分の高い方とは知らずに、つい……。」
「私が身分の高い人間でなければ、謝らなかったということですか?」
リリーの冷ややかな指摘に、エミルは言葉を失った。
謝ったらそれで済むのに、なぜまたこんなに鋭く指摘するのかと彼は思ったが、帽子を差し出しながら言った。
「そういう意味ではなく、とにかく謝りたくて……。お詫びのしるしに、私が作った帽子を差し上げたいのです。」
リリーの視線が、エミルと彼が差し出した帽子に向けられた。
彼女は黙って見つめていたが、やがてダグラスに入るようにというような視線を送り、そしてエミルに言った。
「謝罪だけ受け取ります。筆は結構です。」
「では、贈り物として差し上げます。」
エミルの言葉にも、リリーの態度は変わらなかった。
彼女は手を軽く振って言った。
「必要ありません。あなたの作ったその筆がそんなに価値のあるものかどうかも分かりません。でも、店主には私が謝罪を受け取ったと伝えてくださって結構です。」
それで十分だった。
エミルはすぐに礼をし、ダグラスの目が細められた。
彼が望んでいたものが何だったのか分かったからだ。
もう少し怒っても良さそうだったが、ダグラスは馬車のドアを閉め、リリーの向かい側に座った。
そして馬車が動き始めると、静かに口を開いた。
「それくらいで許してあげてもいいのでは?」
「そうですか?」
「もう少し怒ってもよかったのに。」
「もっと怒ったら、それは怒りっぽい人ですよ。」
それもそうだけど。
ダグラスはちらりとリリーを見てから、ため息をついた。
なぜか侯爵夫人が彼にリリーと一緒に出かけるよう言ったのが分かった気がした。
ただ娘への愛情から気を配っただけではなかったようだ。
「こういうことがよくあるのですか?」
ダグラスの問いにリリーは帽子を軽くつかんだ。
ダグラスはリリーがぱちくりと目を瞬きしながら帽子を撫でている姿に、つい自分の服をぎゅっと掴んでしまった。
可愛すぎて死にそうだった。
「どんなことですか?」
「ああ、さっきのあの男のようなことです。あんなふうに無礼なことがよく起こるんですか?」
ダグラスの質問にリリーはくすっと笑った。
彼女は驚いたような表情で尋ねた。
「女性画家、見たことありますか?」
ダグラスの目がくるくると回った。
彼の脳裏には、フィリップの家に行ったときにすれ違った何人かの画家たちの顔が浮かんだが、その中に女性はいなかった。
今まで気づかなかった事実に、彼の目が見開かれた。
なるほど。彼は“女性画家”という存在そのものをリリーで初めて知ったのだ。
「いいえ。」
「女性の剣士は?」
たまに見たことがあった。
傭兵の中にごくまれにいた。
彼らは貴族であるダグラスの目から見ても驚くほど粗野な口調を平然と使っていた。
「見ました。」
「彼女たちに“女性のくせに剣が上手だ”って言ったこと、ありますか?」
リリーの質問にダグラスの表情がはっきりとこわばった。
あった。
言ったことはないが、そう思ったことはある。
そして、それを褒め言葉だと思っていた。
なぜなら、女性は弱くて剣のような危険なものを扱うことができないと考えていたからだ。
その顔を見たリリーは穏やかに尋ねた。
「じゃあ、もう一度聞いてみます。そんな無礼なこと、よくありますか?」
ダグラスはとっさにリリーの顔を見ることができず、帽子のつばを触った。
ふと頭の中に「これは無礼なのでは」という思いがよぎった。
女性は力が弱く、剣を扱うのは難しい。
だからこそ、そんな女性の中で剣士になった人々を「女性のくせに立派だ」と思うのは当然ではないか。
——だが、彼はリリーにその弁明を一切伝えられなかった。
ダグラスは通じないだろうと考えていた。
女性画家に「女なのに上手だね」という言葉が褒め言葉でないのと同じように、女性剣士に対してもまったく同じだ。
一瞬、気が抜けたようになったダグラスを見たリリーは、思わずため息をついた。
ダグラスが自分に好意以上の感情を抱いていることを、彼女は知っている。
だからこそ彼にこれ以上思わせぶりな態度を取りたくなかった。
「さっき私の代わりに支払ってくれてありがとう。お金は……」
「家に帰ってお渡しします。」
彼女がそう言おうとした瞬間、ダグラスが素早く返した。
「受け取らないでください。」
リリーの目が一瞬見開かれたが、すぐに元の表情に戻った。
彼が受け取らないつもりなのは分かっていた。
それは彼が貴族だからだ。
他人のために一度出したお金を返してもらうというのは、貴族にとって好意を拒絶したか、あるいは侮辱に等しいからだ。
それでもリリーは返したかった。
ダグラスが送ってくる花や本も、彼女にとっては負担だった。
受け取ったのが金貨ではなかったとしても、今すぐ返せるものなら返したかった。