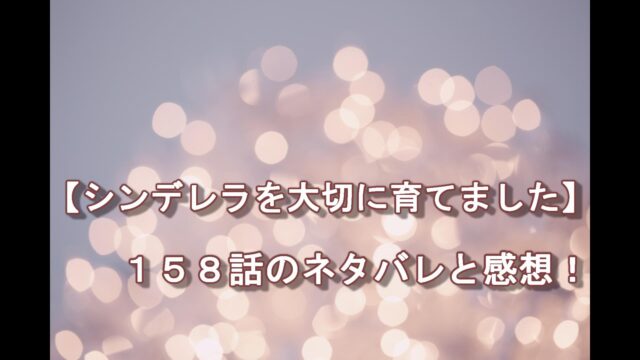こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

206話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 世の中の偏見②
「怒ってごめんなさい。」
リリーはため息をつきながら謝った。
彼女の謝罪に驚いたダグラスが片方の眉を上げた。
「さっきちょっと怒って、ひどい言い方をしてしまいました。ごめんなさい。」
女剣士に「女性なのに剣がうまい」と言ったり、そう思ったことがあるかと尋ねたことを謝っているのだ。
リリーの謝罪にダグラスはどうしていいかわからなかった。
自分の発言が間違っていたのだ。
それをリリーが謝るとは思わなかった。
だがリリーもまた、ダグラスに怒りをぶつけたことに罪悪感を感じていた。
彼女が怒りを向けるべき相手は、ダグラスではなかったからだ。
エミルだった。
リリーがエミルに怒らなかったのは、その相手が相手にする価値もない小者だったからであり、ダグラスが怒らなかったのは怒れば彼が傷つくと分かっていたからだった。
それが、リリーには罪悪感を覚えさせた。
理解できる人には、もっと優しく接しなければならない。
怒るべきではない。
「大丈夫です。」
おずおずとダグラスを見つめていたリリーは、小さくため息をついた。
彼が自分にしてくれるすべてのことが負担に感じられ、申し訳なかった。
客観的に見れば、ダグラスはリリーの相手になるような人ではなかった。
ダグラスは将来の婿候補であり、王子の後継者でもある。
このような男には伴侶が必要だ。
結婚するつもりのないリリーは、結婚する気がないという理由だけで、ダグラスと親しくするのはふさわしくないという考えが浮かんだ。
「それと、これからは花や本のようなものは送らないでいただけたら嬉しいです。」
リリーの静かなお願いに、ダグラスはスプーンを止めた。
彼は何か言おうとして口を開けたが、何を言うべきかわからないことに気づいて口を閉じた。
そして再び慎重に口を開いた。
「お気に召しませんでしたか?」
「そうじゃないんです。」
花は綺麗だったし、本も面白かった。
以前送ってくれたチョコレートも美味しかった。
でも、リリーは自分が応えることができない求愛をするダグラスに対して申し訳なかった。
自分が応えられないことを知りながらも知らないふりをして彼の好意を受け取っていたことに罪悪感を感じていた。
「前に……だから私……。」
そこまで話したリリーの顔がぱっと赤くなった。
彼女の姿を初めて見たダグラスの目がまんまるになったのを見て、リリーはおどおどしながら再び口を開いた。
「私が軽率でした。キスしたのは、雰囲気に流されただけなんです。もしそれで誤解されたのなら……」
その時ようやくダグラスの顔も赤くなった。
彼は左手で顔を隠したまま、右手を差し出してリリーの口をふさぎ、急いで言った。
「誤解なんてしていません。ご心配なく。」
「で、でもそれならどうして私にプレゼントを送ってきたんですか?」
「前にも言ったじゃないですか。私はリリー、あなたが好きなんです。」
「でも、私は結婚するつもりはないって言いましたよ。」
ダグラスはようやく顔を隠していたリリーを見つめた。
彼の緑色の瞳がかすかに熱を帯びて輝いていた。
まるで視線が捕まったような気がして、リリーはぼんやりとダグラスの顔を見つめた。
「好きな人に贈り物をすることのどこが悪いんですか?」
「応えられなくてもですか?」
「あなたは誰かに応えてもらえる確信があってこそ好意を示すんですか?」
今度はリリーの方が一撃を食らったようだった。
彼女はきまり悪そうに顔を赤らめ、小さな声で言った。
「でも、これはただの好意とは違います。あなたは私に、ぷ、プロポーズをしてるんですよ。」
ダグラスのまなざしが何かを語るように一瞬上がったかと思うと、すぐに彼の顔に笑みが浮かんだ。
彼はリリーを見ながら身を乗り出し、にっこり笑ってこう言った。
「リリー、私は男女関係においては非常に頑固で柔軟性のない人間です。もし私があなたにプロポーズするなら、贈り物として渡すのは小さな花や本ではないでしょう。」
リリーの顔がぱっと赤くなった。
彼女がスプーンを勢いよく回すと、ダグラスも恥ずかしそうな表情を浮かべてスプーンを口に運んだ。
実際のところ、彼は花や本よりもっと良いものを贈りたかった。
彼はすでにリリーの瞳の色とそっくりな宝石を購入していた。
それでネックレスとイヤリング、ブレスレットのセットを作って贈りたかったのだ。
しかしリリーが気が引けるだろうと思って、花と本でとどめておいたのだ。
そして今、彼女の反応を見て、自分の判断が正しかったと感じた。
その間に馬車はいつの間にかリリーの住む東郊の邸宅に近づいていた。
馬車が止まると、ダグラスはすぐに馬車から降りて、リリーに手を差し伸べた。
「今日は送ってくださって本当にありがとうございました。画廊でも私の味方をしてくださって感謝しています。」
「当然のことをしただけです。」
リリーの感謝にダグラスは無表情で答えた。
家まで送ることや画廊で味方をすることは、たとえリリーでなくても彼はしただろう。
だから彼は、そんなことで感謝の言葉を受け取る理由はないと思っていた。
しかしリリーはそうは思っていなかった。
ミルドレッドは娘たちが助けを受けたなら、必ず感謝の気持ちを示すように教えていた。
彼女はダグラスに「中に入ってお茶を一杯飲んでからお帰りになってください」と勧めるべきだと心の中で何度も練習したが、結局こう口にした。
「帽子代も出してくださって、贈り物も送ってくださったのに、何かお返ししたいのに、お返しできるものが何もないんです。」
ダグラスの表情が曇った。
彼はリリーと出会う前から言いたかった言葉を思い出した。
もしかすると今がその機会かもしれなかった。
「一つ、あります。」
リリーの顔に警戒の色が浮かんだ。
もし“結婚してくれ”ということなら、それは無理だ。
しかし幸いにもダグラスの望みはそういうことではなかった。
彼は息を整えて、あまり切実に見えないようにゆっくりと言った。
「両親が、少し前に私に肖像画を描かせるべきではないかとおっしゃっていたんです。」
裕福な人々は肖像画を描かせるのが一般的だ。
歴代の家主や家族の肖像画をギャラリーに展示することもある。
ダグラスは、リリーとの距離を縮める良いきっかけになると考えた。
「絵の代金はもちろんお支払いしますから……」
「いいえ。」
ダグラスがさらに何か言おうとする前に、リリーが慌てて口を開いた。
断るの?と戸惑う彼に、彼女が続けて言った。
「はい。肖像画を描いて差し上げます。」
嬉しそうなダグラスの顔がぱっと明るくなった。
もしそのとき執事が現れなかったら、彼はリリーの手を思わず握っていたかもしれない。
「お帰りですか、リリーお嬢様。奥様がケイシー嬢とお食事してから帰るのはどうかと仰せでした。」
リリーが到着したのに中に入らない理由を知ろうとしたミルドレッドが、ダグラスが一緒に来たという話を聞いて夕食に招待したのだ。
彼は嬉しい気持ちを隠そうとして無表情な顔で帽子を脱いだ。
「ありがたく頂戴いたします。」
「分かりました。」と小さく帽子を脱ぎ、二人は扉を開けて、中に人が入れるようにした。
ダグラスは馬夫に「夕食後にまた来てくれ」と言い、独りでにやけないよう唇を引き締めながら中へと入っていった。
「リリー、あなたの角にあるトイレ2つは私のものよ!」
そのとき、向こうから現れたアシュリーがリリーを見つけてそう叫んだが、ピタリと声を止めた。
彼女の隣に立つダグラスの姿を今やっと見つけたのだった。
「2つとも私の角にあるなら、そのうち1つくらい私のトイレってことにすべきなんじゃない?」
くすくすと笑いながらそう言うリリーの言葉に、アシュリーも思わず笑い返した。
「なによそれ!トイレは私のもんよ!」
…これはなんの話?
ダグラスは戸惑いの表情でリリーの横に立っていた。
アシュリーに挨拶すべきか、リリーとアシュリーの会話に入るべきか、迷っていた。
だが幸いにもアシュリーが先に目を合わせて挨拶をした。
「こんにちは、ケイシー卿。」
「お久しぶりです、バンス嬢。」
アシュリーの顔は赤く染まっていた。
恥ずかしいのだ。
どうしてよいかわからず視線を上に向けた彼女に、リリーがくすくすと笑った。
「何の話ですか?」
ついに我慢できなかったダグラスが尋ねた。
リリーは彼を応接室へ案内しながら軽く答えた。
「最近、弓の練習をしているんですよ。」
「弓?」
彼の知っている弓以外に他の弓があるのか?
困惑する彼に、リリーが丁寧に説明した。
「男爵様が剣や弓の扱い方を教えてくださったんですよ。アシュリーは弓の方がもっと面白いみたいです。」
「剣、ですか?」
「はい。アイリスは剣の方が面白いって。どっちも大したことないですけど。」
ダグラスの脳裏に、優雅な姿勢のアイリスの姿が浮かんだ。
聡明で気品ある、まるで貴族令嬢の見本のようなアイリスが剣を振るっているなんて、彼には想像もつかなかった。
もちろんリリーが剣を振るう姿も想像しづらいのは同じだった。
彼は小さくて繊細なリリーが大きな剣を持ち上げるところを思い浮かべ、不安げな表情で尋ねた。
「では、あなたはやっていないんですか?」
「うーん、たまにはしますよ。アイリスが相手をしてって言ってきたら。もともとはウィリアムがアイリスの相手だったんですけど、あいつ、他に行っちゃって。」
ウィリアム?
知らない男の名前がリリーの口から出ると、ダグラスの眉がぴくりと動いた。
しかしリリーはウィリアムが誰かを言わず、話題をさっと変えた。
「弓を射るのも時々アシュリーと勝負するんです。さっきの痣も、それでできたんですよ。」
何のことかわかった。
ダグラスは好奇心が少し収まったが、新たな好奇心に火がついた。
ウィリアムとは誰だ?
なぜリリーが親しげにその名を口にしたのだ?
軽く問いただす前に、二人はすでに応接室に到着していた。
すでに書類に目を通していたミルドレッドがダグラスを迎えた。
「いらっしゃいませ、ケイシー卿。ご一緒に夕食をされるのがよろしいかと思いお誘いしましたが、ご都合はいかがでしょうか?」
「いいえ。お招きいただきありがとうございます。」
その間に、リリーは「着替えないと」と言いながら上の階に上がってしまった。
彼女の後ろ姿を名残惜しそうに見つめるダグラスの表情に、ミルドレッドはほろ苦く笑った。
「リリーは今日、フィリップ卿やケイシー卿と一緒にアトリエに行くって言ってましたけど。」
召使いがお茶を運んできたとき、ミルドレッドが尋ねた。
ダグラスはティーカップを持ち上げてから、すぐに礼儀正しく答えた。
「ええ。でも、奥様が今朝階段を下りてくる途中で腰を痛められてしまって。」
「まあ、それは……」
「おかげで今日はリリー嬢とバンス嬢にお会いできました。」
ダグラスの微笑みに、ミルドレッドの顔にも笑みが浮かんだ。
彼女はティーカップを持ち上げながら、再び尋ねた。
「卿がリリーに求婚するっていうの、ケイシー卿も侯爵様と侯爵夫人様はどう受け止めておられますか?」
どう受け止めているとも言えない。ダグラスは礼儀正しい姿勢で答えた。
「何もおっしゃいませんでしたが、戸惑っておられたかと思います。」
「本当ですか?」
湯飲み越しにミルドレッドの緑色の瞳が輝いた。
ダグラスは困惑した表情で尋ねた。
「本当とは、どういう意味ですか?」
「常識的に考えてみましょうか?本当にご両親がリリーを気に入ると思いますか?」
当然気に入るはずだ。
ダグラスの表情がこわばった。
彼の両親は、彼がどんな女性を連れてきても喜んで迎えてくれるだろう。
もちろん、貴族ではないか、資産家でないか、あるいは結婚歴があれば話は別だが――それは彼も知っていた。
だがリリーは未婚であり、しかも貴族だ。
それだけでも十分すぎるほど素晴らしくて申し分ない。
しかしミルドレッドの考えは違っていた。
彼女はすでにケイシー侯爵夫人がリリーを側室に迎えようとしていたこと、そして二人が話を交わしたことを知っていた。
ケイシー侯爵家は立派な家柄だ。
名門であり裕福な貴族の家だ。
もし相手がアシュリーやアイリスであれば、ミルドレッドは心配しなかっただろう。
しかしダグラスが恋に落ちたのはリリーであり、ケイシー侯爵夫人と会った今となっては、ミルドレッドはケイシー侯爵がリリーにとってそれほど良い相手ではないのではと思うようになった。
「ケイシー卿、リリーは結婚するつもりはありません。もし卿が何とかしてリリーの気持ちを変えて結婚することになったとしても、ご両親が彼女が画家として活動するのを黙って見ているでしょうか。」
「それは私がうまく説得します。」
「説得したのではなく、説得するつもりなのですね。」
ミルドレッドはそう言って茶碗を置いた。
その音にダグラスは我に返った。
彼は今、自分が試されていることに気づいた。
「ご心配なさらないでください、バンス夫人。私の両親はすでに私が二度目の結婚をするとしても、その相手が誰であれ感謝することでしょう。」
「本当ですか?」
ミルドレッドの目が冷たく輝いた。
その瞬間、ダグラスはなぜかダニエルを思い出した。
今のミルドレッドの瞳はダニエルと似ていた。
彼女は冷たくなりすぎないように気を配りながら言葉を続けた。
「卿、卿の母君は侯爵夫人としてほとんどの生涯を過ごされました。それに、こんなに素晴らしい息子を育てられたのですから。」
「はい、ありがとうございます。」
ダグラスの感謝に、ミルドレッドは穏やかに笑った。
嘘ではない。
ダグラスはこの国で完璧な結婚相手とされる男性だ。
整った容姿と見事に鍛えられた体つき。
この国で名高い剣の腕前に王子の側近。
そして侯爵家の後継者でもある。
性格が少し堅物で不器用なところはあるが、それくらいは悪いところではなかった。
当然、ケイシー侯爵夫人の息子に対する期待も高かったに違いない。
たとえビロク令嬢との婚約が二度も破談になったとしても、人というものは基本的に期待を持つものだ。
「息子を持つ母親というのは誰しも、自分の息子にふさわしい立派な妻が来てくれることを願うものです。侯爵夫人であればなおのこと、素晴らしい妻であることが条件なのです。いや、後継者のためにも努力してくれることを願っています。その期待に及ばないリリーがあの方の目にかなうでしょうか?」
「目にかなわないからといって、バンス嬢を嫌ったりいじめたりなさる方ではありません。」
「おお、もちろん後継者夫人ともあろうお方が、妊娠した嫁を呼びつけて“クチョプバンサン(九菜飯床)”を作らせたりはしませんよ。」
ダグラスの表情がこわばった。彼はじっとミルドレッドを見つめながら尋ねた。
「クチョプバンサンって何ですか?」
ミルドレッドの目がぐるりと回った。
簡単に言えば、ご飯とスープ、キムチを除いたおかずが九つある個別の膳立てを意味するが、この世界にそんな言葉があるはずがない。
彼女は一瞬言葉に詰まった。
「つまり、リリーは固く反対しないというだけではなく、積極的な支持が必要だということです。」
ダグラスの目が細められた。彼はリリーを支持している。
自分が剣を愛するのと同じように、リリーが絵を愛していることを知っていたからだ。
しかし、彼の両親はリリーが画家として活動することを支持するだろうか?
ダグラスはその問いには懐疑的な返答しかできなかった。
最も好意的な反応であっても、反対も支持もせず黙っているにすぎないだろう。
ミルドレッドは沈黙したダグラスに再び語りかけた。
「卿のご両親が悪いというわけではありません。あの方たちはあの方たちの立場から望むものがあり、私とリリーは私たちの立場から望むものがある、それだけのことです。」
それはどうしようもないことだ。
誰が悪いわけでもないし、利己的だからでもない。
ミルドレッドの言葉に、ダグラスの表情が曇った。
彼は慎重に尋ねた。
「では、反対されるということですか?」
ミルドレッドは冷たく答えた。
「それをなぜ私に聞くんですか? まずは公のご両親を説得するのが先でしょう。」