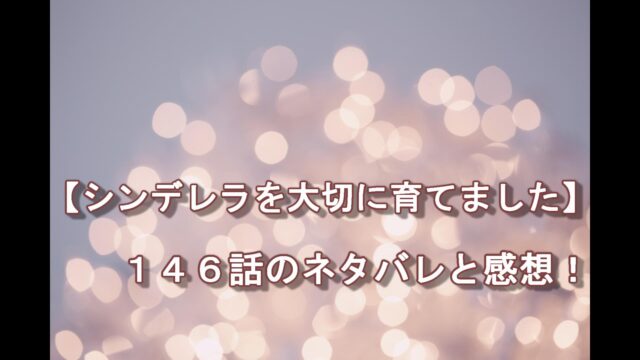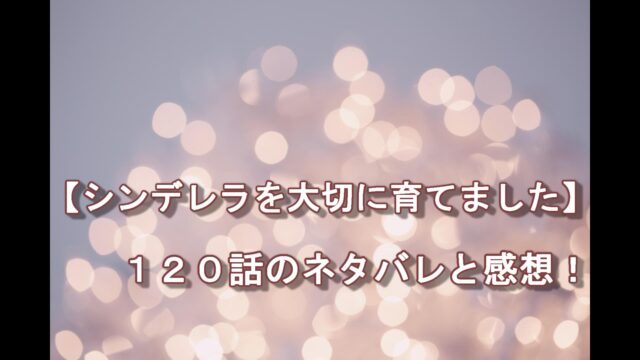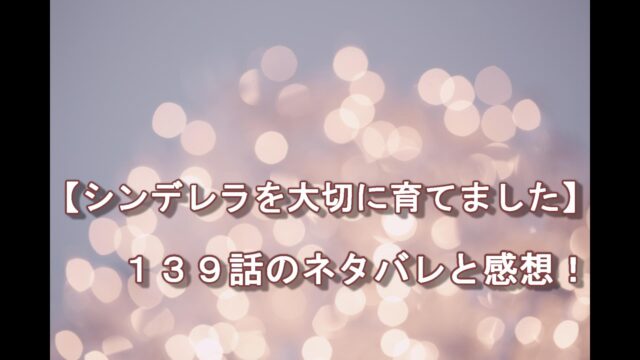こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

212話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 恐ろしい人②
「アシュリー。」
ミルドレッドがアシュリーの名を呼ぶと同時に、矢が放たれた。
その瞬間、にやけていた男たちの顔に驚きの表情が浮かんだ。
「うちの娘、弓を少し使えるんです。右目と左目…目のどこが不要か教えてくれれば、矢を射るようにしなさい。」
ミルドレッドの言葉に顔色が青ざめたのは、むしろ男たちよりもアシュリーだった。
彼女は目を瞬かせ、自分が放った矢を見た。
矢は一番近くにいた男の両足の間の地面に正確に突き刺さっていた。
「ちょっと……」
男たちの一人がミルドレッドに声をかけながら近づいてきた。
しかし、その瞬間ミルドレッドが再びアシュリーの名を呼んだ。
「アシュリー。」
反射的にアシュリーは矢を引き抜き、弓に番えた。
彼女が強く弦を引き絞る様子に、男が身をすくめて動きを止めると、ミルドレッドは再び言った。
「言うべき時に言え。」
「ちょっと……」
男が再び口を開くと、アシュリーはミルドレッドを見た。
「撃つんですか?」
「どちらの目が不要か聞いてからね。」
ミルドレッドの答えに、男の顔色がさっと青ざめた。
どう返すべきか一瞬迷った男は再び口を開こうとしたが、そのとき背後から荒々しい声を上げながら馬に乗った男が駆け寄ってきた。
「バンス嬢!」
聞き慣れた声に、アシュリーの背後にいたリリーの目が見開かれた。
それはミルドレッドやアイリス、そしてアシュリーも同じだった。
四人が同時に顔を向けると、稲妻のような速さで馬を駆るダグラスの赤い髪が目に入った。
瞬く間に男たちとバンス家の人々の間に到着したダグラスは、そのまま馬から飛び降り、大声で叫んだ。
「リリーさんの髪の毛一本でも傷つけようものなら、ただじゃおかない!」
人々の目が大きく見開かれた。
この男、今なんて言った?
リリーの顔が真っ赤になり、同時にミルドレッドとアイリスの口がぽかんと開いた。
そしてその瞬間、
ヒュッと音を立ててアシュリーの弓から矢が放たれた。
「きゃっ!」
アシュリーの悲鳴と共に、矢は前に出てきた男の右足のすぐ前に突き刺さった。
男はその場で固まり、アシュリーは男に駆け寄って叫んだ。
「まあ! ごめんなさい! 大丈夫ですか?」
ほんの少し角度が上がっていたら、大変なことになっていただろう。
驚いて男に謝るアシュリーの姿があった。
リリーがアイリスに小声で言った。
「ねえ、今私たち、あの人たちを脅してるってこと忘れてない?」
脅してるって?
ダグラスはぎょっとしてリリーを振り返った。
しかし彼が心配していたのとは違い、リリーは落ち着いていた。
怯えている様子も、パニック状態でもない。
「大丈夫ですか?」
彼は男たちから身体を向け直し、リリーに尋ねた。
幸い、彼女は平然としていた。
むしろ、なぜダグラスがここに来たのか不思議そうな顔をしていた。
「大丈夫です。」
どこか気まずそうな表情でリリーが答えると、ダグラスの顔にも安堵の色が浮かんだ。
それならよし、と彼は再び男たちへと視線を戻した。
母と共にティーパーティーに行っていただけなので、彼は特に持参できるような物はなかった。
武器になりそうなものを探して周囲を見回しているうちに、転がっていた木の枝を拾い上げた。
これでは切ったり突いたりはできないが、少なくとも相手の目の前に星が飛ぶくらいの一撃は食らわせられるだろう。
「バンス夫人、バンス嬢。馬車の中にお入りいただくのがよろしいかと。」
ダグラスの言葉に、ミルドレッドの顔に驚きの表情が浮かんだが、すぐに微笑みに変わった。
「まあ、ありがとう、ケイシー卿。でも私たちは大丈夫よ。」
そう言ったミルドレッドは、再び棒を振り回していた男たちに向かって視線を戻し、こう言った。
「こんなにたくさんの人の前で、私たちに手を出すことなんてできないはずよ。」
そうして彼女は、従業員たちの間に紛れ込んで棒を振るバンス家の人々を見つめていた。
彼らは貴族だ。
貴族に無礼を働き、首都で何事もなく過ごせるはずがない。
「最後のチャンスよ。」
ミルドレッドは腰に手を当て、こう告げた。
「今すぐ立ち去らなければ、明日からは右目だけで世の中を見ることになるわよ。」
男たちの視線は、エシュリーが手にしている弓に向けられた。
彼らは、エシュリーが正確に的へ向けて矢を放ち命中させるのを見た。
それがたとえ射撃の実演だったとしても、次の矢が別の場所に当たらない保証はない。
男たちは互いに顔を見合わせ、じりじりと後退し始めた。
近くにいた使用人たちは、男たちが動くと同時にわっと集まってきた。
「失せろ!」
ようやく勇気が湧いたのか、奥にいた男が立ち去る仲間に向かって叫んだ。
それをきっかけに、他の者たちも男たちへ向けて罵声を浴びせた。
叩き始めた。
「二度と来るな!」
「この悪党ども!」
ダグラスは一変した雰囲気に口をつぐんだ。
しかしすぐにリリーの方へ歩み寄った。
「大丈夫ですか?」
「ええ、大丈夫。ケガはしていませんから。」
「そうよ。髪の毛一本だって触らせやしないわ。」
アイリスの冗談に、リリーは彼女を見つめ、つられてダグラスの顔が真っ赤になった。
全く…とミルドレッドはため息をつく。
こういうとき、彼は年甲斐もなく十代の少年のようだ。
「ケイシー卿、来てくれてありがとう。」
どうやら今日は開所式を行うのは無理そうだ。
開所式といっても、人々に建物を案内したり、ビーニュの作り方を教えたりするだけなのだが。
今日は皆驚いただろうから、一旦落ち着かせる必要があると考え、ミルドレッドはエシュリーを呼んだ。
人々と挨拶を交わさなければならない。
そして工房の仕事を手伝うことになったアイリスも紹介するつもりだった。
新しい工房長が来るまでの間、エシュリーも工房を手伝うことになるので、彼女の紹介も必要だ。
「時間があれば、少し待ってもらえる?私たちを助けてくれたお礼もしたいし、お茶でもご一緒したいの。ここで少しリリーと待っていて。」
リリーと二人きりでいることを、ダグラスは望んでいなかった。
彼が真剣な表情で首を横に振ると、ミルドレッドはエシュリーとアイリスだけを連れて人々の方へ向かった。
「本当に大丈夫ですか?」
ミルドレッドが人々に挨拶しながら、エシュリーを臨時の工房長として、アイリスを財団代表として工房を手伝うことを説明した。
説明している間に、ダグラスが再び尋ねた。
リリーは目を細めて睨むようにしてから、ため息をつき言った。
「本当に大丈夫です。あの人たちは私たちに近づきもしなかったんですから。」
ダグラスの表情が和らいだ。
同じ質問だが、先ほどと今とでは少し意味が違う。
先ほどは体にケガがないかを確認するための問いだったが、今は驚かなかったかを確かめるためのものだった。
しかし、ダグラスは今回もリリーが「驚かなかった」と答えることを分かっていた。
驚かなかったはずがない。
だが、リリーと少し打ち解けてきた彼は、彼女が驚いたとしてもそれを認めないことを知っていた。
そして、彼女が驚いたことを心配していると知られるのは、彼女のプライドを傷つけることになるとも分かっていた。
「行こう。」
工房の職員たちと挨拶を交わし、明後日同じ時間にまた来てほしいと頼んだミルドレッドが、黙って立っているダグラスとリリーのもとへ歩み寄り声をかけた。
羊に貸した物なら明後日持ってきてもいいだろう。
正確に言えば、羊の名を借りて来た作家の物だが。
ダグラスはそう考えながら、借りた物を持ってバンス家の馬車の後について、丘のふもとの邸宅へ向かった。
「ところで、どうやってあそこへ行ったんです?」
ミルドレッドは家に着くと、ダグラスを応接室に案内しながら尋ねた。どうやって行ったのか?
答えにくい質問に言葉が詰まり、ダグラスはどう説明すべきか迷い始めた。
その時、驚くべきことに予想もしなかった救援者が現れた。
「ミルドレッド、大丈夫ですか?」
応接室に突然現れたダニエルが、ミルドレッドに歩み寄って尋ねた。
明らかに5人ほどが先ほど屋敷に到着したばかりなのに、ダニエルはミルドレッドが何を経験したのか知っているような様子だった。
「何もなかったですよ。ちょうどケイシー卿が必要なときに現れたんです。」
ミルドレッドが自分をかばうようにそう言うと、ダグラスは驚いて背筋を伸ばした。
ダニエルもまた、先ほど外出から帰ってきたばかりの服装だった。
「そうですか?」
ダニエルの視線がダグラスに向けられた。も
しリリアンの指導ではなかったら、ミルドレッドが台所へ行くときに彼も一緒に行っただろう。
しかし、ダグラスがそこにいたおかげで助かったのだ。
ダニエルはダグラスに手を差し出しながら言った。
「保護魔法をかけておきました。」
ダグラスがリリーとずっと一緒にいたいなら、それを知ってもらうのも悪くないだろう。
その指輪は、ミルドレッドが使うと瞬時に彼女の周囲にシールドが展開される。
しかしダニエルの説明に、ダグラスは首をかしげて再び尋ねた。
「いや、その指輪のことです。」
「ただの指輪です。」
ダニエルがあまりにも当然のように言うので、ダグラスもそれ以上追及せず受け流した。
彼はカップを口にしながら尋ねた。
「でもそれは……」
「ああ、それより殿下はどうやってそこへ行かれたのですか?」
あまりに強引な話題転換だったが、応接室にいる人々にはうまく通じた。
ミルドレッドはカップを置きながら尋ねた。
「ありがとう。」
まるで夫のような態度に、ダグラスは目を大きく見開きながらも反射的にダニエルの手を握った。
ダニエルはその手をしっかり握って微笑み、そして手を放すと再びミルドレッドに向かって言った。
「必要なら使えと言ったはずですよ。」
「必要なかったんですから。」
ミルドレッドは懐から男性用の指輪を取り出しながらそう答えた。
それはダニエルの指輪だった。
彼が初めて彼女に会ったときに渡したもので、その後もずっとミルドレッドが持っていたが、ダニエルは返却を求めたことはなかった。
代わりに、彼は常にその指輪を持ち歩くよう求めていたのだ。
「それは何です?」
ついに好奇心を抑えきれなくなったダグラスが尋ねた。
ダニエルはその指輪を再びミルドレッドの手に押し込みながら答えた。
「そうですね。どうやって探して来られたんですか?」
「あ、それは……」
ダグラスの顔に困惑の色が浮かんだ。
彼は思わずアイリスを振り返った。
プリシラに国王を廃位に追い込むつもりだと協力を求めたが、バンス家の応接室でその話をすると、まるで自分がそうなるかのような感覚に襲われた。
彼はつぶやくようにしてミルドレッドに言った。
「バンス夫人、少しお話ししてもよろしいでしょうか?」
「もちろんです。」
「二人きりで。」
ダニエルの眉が上がり、リリーの額に皺が寄った。
ミルドレッドは何事かと思い、互いに視線を交わすアイリスとアシュリーを見てから、再びダニエルを振り返った。
「ダニエルも一緒に聞いてくれたら良かったのに。」
バンス夫人と二人きりで話すより、もう一人誰かいた方がいいかもしれない。
それがウォルフォード男爵だというのは気に入らないが。
ダグラスはミルドレッドの案内を受け、ダニエルと共に書斎へ向かった。
そこで、自分が今回どうやって工房にいることを知ったのか、そしてどうやって工房まで来たのかを打ち明けた。
「話したってことですか?」
ダニエルの問いに、ダグラスは頷きながら答えた。
「海の魚を数えるような真似はしません。ですが、何があったのか話してくれればご迷惑はおかけしないと申し上げましたので、ご迷惑をかけるかどうかはお二人次第というわけです。」
ミルドレッドは黙ってダグラスの話を聞いていた。
彼女は、ダニエルが思わず身を乗り出しているのに気づいていた。
彼の指輪をそっと触れながら、自分の考えが揺らいでいること、そしてダニエルの考えも揺らいでいることを感じ取った。
工房に乱入してきた男たちは、ミルドレッドの考えではバンス家の人間に危害を加えるつもりはなかった。
ただ工房を開けさせないことだけが目的だったのだ。
しかし、ダニエルの主張どおり、魔法がかけられた彼の指輪を持ち去ろうとしたことも事実だった。
ダグラスの話によれば、乱入してきた男たちは傭兵だったということになる。
傭兵の数が狂えばどうなるか分からない。
もちろん法を守る傭兵もいるが、法を守らない傭兵の方が多い。
首都で起こる犯罪のかなりの部分を彼らが占めていることを考えれば、指輪を奪おうとしたダニエルの判断も理解できた。
「私が説明しましょう。」
ダニエルは腕を胸の前で組みながら言った。
そうでなくても、彼はすでにギルド長が警告にもかかわらず妙なことをしていると察していた。
むしろ都合が良かった。
もしビーヌ工房の者たちがミルドレッドの工房に危害を加えようとして、そこにムーア伯爵家が関わっているのなら、それはタッサンピ一味と変わらない。
プリシラ・ムーアが王妃候補から外れれば、現行のビーヌ・ギルドは解体されるだろう。
その後釜に座るのは、新たなビーヌ製法で工房を築いたミルドレッドだ。
「直接訴えることはできなくても、証人になってくれる可能性はありますよね、ケイシー卿?」
ダニエルの問いに、ダグラスは厳しい表情で答えた。
ムーア卿が今日、庭園で彼女に何を言ったのかを証言することは難しくない。
「はい。私以外にも、それを聞いた者がいます。」
ワッソン嬢と一緒に庭園を散策しているところに偶然出くわした。
そこまで考えたダグラスの顔はみるみる青ざめた。
目が飛び出しそうになるほど見開いた彼に、驚いたミルドレッドが尋ねた。
「大丈夫ですか?何があったんです?」
大きな非礼を犯した。
助けもせず、パートナーを置き去りにするとは――なんと無礼な行動だろう。
ダグラスは片手で頭髪をかき上げながら言った。
「ええと、私は、その……無礼を働きました。ある女性と散策中であったことを忘れてしまっていたのです。」
「どんな女性ですの?」
「メアリー・ワッソン嬢と……」
そこまで言って、ダグラスははっと我に返った。慌てて弁明を始める。
「ワッソン嬢とは何の関係もありません。ただ庭園を案内していただけです。」
ミルドレッドはくすっと笑い、ダニエルの方を向いた。
彼女には弁明する必要はなかった。
ダニエルもまた、呆れたように笑っていた。
彼女は再びダグラスに視線を戻し、こう言った。
「私に説明する必要はありませんわ。卿は独身で、何の約束もしていませんもの。」
ダグラスの表情が一瞬、困惑したように揺らいだ。
困惑するような内容ではない。
何と答えるべきか分からずミルドレッドを見ていると、その隣でダニエルも同じような表情を浮かべているのに気づいた。
「お母様、馬車の用意ができました。」
その時、アイリスが書斎の外から三人を呼んだ。
何を話しているのか気になっていた様子だ。
「お茶を飲んでいってください。ワッソン嬢に謝罪するためでなければ、夕食もご一緒に。」
ワッソン嬢には謝罪の手紙を送れば済むことだった。
ダグラスは「ありがたく頂きます」と答え書斎の外へ出た。
ドアの前に立っていたアイリスとアシュリーと目が合うと、二人はくすくす笑いながら走り去ってしまった。
おかげでリリーだけが残された。
「お食事をしてから行かれるのですか?」
どうすればいいか分からずにいたリリーは、思わずそう尋ねた。
今日は昼食も一緒に食べた。
一日に二度も共に食事をすることになるとは――ダグラスは喜びを抑えながら答えた。
「出してくださるなら。」
「私たちを助けに来てくださったのですから、もちろん召し上がっていってください。」
ややそっけない口調の中でも、「もちろん」という言葉だけでダグラスの気分は一気に高まった。
ついに彼は笑いをこらえきれず、にこにことしながらリリーに腕を差し出した。
「ミル。」
ダグラスが出て行くや否や、ダニエルは後を追おうとするミルドレッドを呼び止めた。
彼女が振り返ると、素早く腕を取って書斎の扉を閉める。
――これはどういうことだ?
ミルドレッドの表情に浮かんだ色が、その問いの意味を物語っていた。
しかしダニエルは心配そうに尋ねる。
「大丈夫ですか?」
「もしあなたが、ケイシー卿がリリーと二人きりで歩いていたことを気にしているなら、
それは大丈夫だと思いますわ。」
「そうではなく、工房でのことです。怪我をしていないと聞いてはいますが……。」
何を言いたいのか察したのか、ミルドレッドの唇にふっと微笑が浮かんだ。
彼女は腕を伸ばし、ダニエルの首元を引き寄せながら囁く。
「あなた、私に魔法がかかった指輪をくれたでしょう?」
「それは……私の責任ではありませんよ。」
「でも、あなたが私を守ってくれている証拠でしょう?」
ダニエルの顔にも微笑みが浮かんだ。
それだけでは物足りず、彼はミルドレッドの腰を引き寄せて言った。
「その証拠を、私の指輪ではなく、あなたの指輪にするつもりはありませんか?」
「指輪を返しましょうか?」
「いいえ、返してほしいという意味ではありません。私の指輪はあなたには少し大きいでしょう。指にはめて持ち歩くのは不便ではないかと思っただけです。」
「指輪はもう一ついただいていますし。」
ぐっとダニエルは言葉を飲み込んだ。
ミルドレッドにもう一つ指輪を渡すという壮大な計画は、水泡に帰してしまったのだ。
彼はため息をつき、こう続けた。
「それならせめて、私の指輪をいつでも、どこでも身に着けてくれると約束してください。」
「護符の魔法のことですか? わかりました。外出するときは着けていきます。」
それで十分だった。
ダニエルはミルドレッドの肩に顔を寄せた。
あの指輪には護符の魔法だけでなく、もう一つ別の魔法がかかっている。
ミルドレッドの近くに、ヴァンス家の人間以外が接近した瞬間に察知できる魔法だ。
そのことは、彼女には知らせないつもりだった。
「イヤリングはどうです?」
依然として肩越しに顔を寄せたまま、ダニエルは半ば囁くように尋ねた。
身長差のため、彼はかなり身を屈めなければならなかったが、それは気にならなかった。
「イヤリングですか?」
「指輪が一つあるならそれで十分でしょう?それならイヤリングは関係ありませんよね?」
抱き寄せられたミルドレッドの体が、かすかに震えた。
彼女が困惑したように笑う声が、間もなく聞こえてきた。