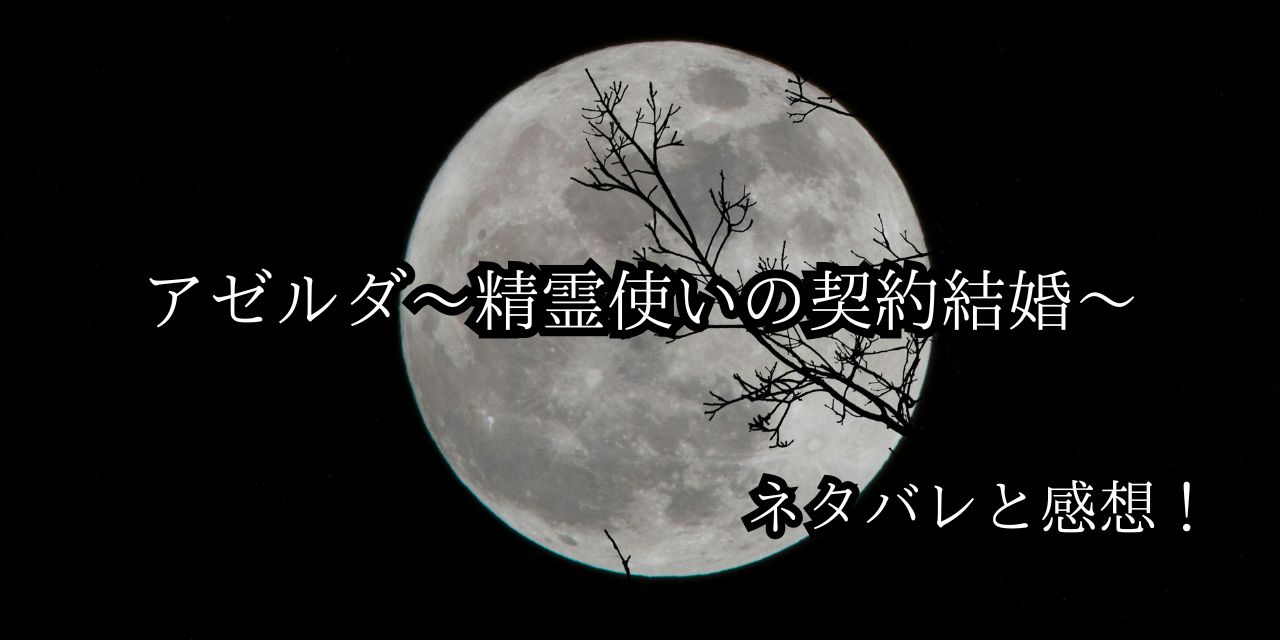こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

39話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 邪悪な噂
ティルトは宴会場の騒ぎから離れ、庭園が見える部屋へ戻ってきた王子の後ろに従った。
王子はしばらく庭園を見つめていたが、ふと扉のそばに積まれていた報告書を手に取り、束をひっくり返した。
「つまり北部への支援金は継続するってことだろ?そこに加えて武器まで贈ることになってんのか?笑わせるな、何だよそれ?違うか?」
「はい、仰る通りです。」
「燃やせ。」
「はい。」
ティルトは王子が手渡した報告書を、新たに積まれていた壁際の炉に押し込み、端に火をつけた。
紙は白く燃え上がった。
「ただの時間の無駄だ、こんなもん。」
「はい。」
「俺は北部で何が起ころうが、微塵も関心なんてないってことを、あのバカは一生理解できねぇだろうよ。」
「はい。」
「一生ずっとまっすぐ正しく生きて、老いて死ぬときにようやく気づくんだろうな。」
「はい。」
「温和で退屈な人生がどれだけ意味がないかってことを。」
「おっしゃる通りです。」
「もちろん、それも老いるまで誰にも頭を下げずに生きられたときの話だろうがな。」
「はい。」
王子は別の報告書を手に取った。
「それと、また首都のスラム街の失踪者を調査したって?こんなもの、飽きもしないのか?」
「仰る通りです。」
「これも燃やせ。」
壁際には新しい焼却装置が設置されていた。
火はすぐに新しい紙に燃え移った。
「はい。」
王子は燃え上がる火花を見つめながら顎を動かした。
「気に入らないことが一つある。」
「ご命令ください。」
「ラブロのやつ、最近やたらと失踪事件に関わってるだろう。黙ってろって言っても、察することもできずに、どこで政治を学んだんだか。」
「ごもっともです。」
「だけど、そうは言ってもあいつが死んだとなれば、誰かがしゃべり出して面倒なことになるよな?」
「はい。」
「なら、どうにか綺麗に始末する方法はないのか?」
ティルトは再び身をかがめた。
「失踪に見せかけて処理する方法もございます。」
王子は何か良い考えが浮かんだのか、窓の外を見ながら、しばし考え込んだような薄笑いを浮かべた。
「失踪か。そうか、そんな手もあるな。」
王子は姿勢を正して身を低くし、忠誠心あふれる自分の騎士に親しげに声をかけた。
「行ってジョディアを連れてこい。」
「はい。」
ティルトはすぐに侍従長の宿舎へと駆けていった。
公爵夫妻がピオルドを離れている間に、北部の雰囲気はにわかにざわめき始めた。
足の速い噂ほど早いものはないとは言うが、「暗闇で何をしていたのか」といった突飛な噂話がたちまち北部中に広がった。
噂の出どころが南部だという話もあったが、噂に最も敏感だったのはやはり北部の民だった。
その噂が最初に広まったのは、テレポートゲート周辺の広場にいる商人たちで、次に公爵邸内部、そして後から北部に戻ってきた人々の間にまで騒ぎが広がった。
もともと情報を統制するよりも、住民間の情報共有を促進しようという政策をとっていた北部だったため、チアンドから流れてきたその噂文は、なんと翌朝には原文のまま広場に張り出されるまでになっていた。
春になり、やっと物資の流通が再開された北部の住民たちは、時が来るたびに一斉に集まって広場の掲示板の前でざわついていた。
「闇?」
「闇だって?」
「それってどういう意味だ?」
「何か知らんが、大ごとになるってことじゃないか?」
「おお、神よ……」
人々の間では、首都から密かに北部を監視しに来た王子の直属の密偵、ジョディアの噂があった。
彼が王子の命令で北部に来ている間にこんなとんでもない命令を下したという話が広まったのだ。
王子が北部に行って本当に「キャンディ」だか何だか知らないが、闇の技術を使う密偵に命令を下して、それを実行させた時は唖然とした。
だから彼は北部に来てからも何をすればいいのかわからず、しばらく周囲をうろつきながら時間をつぶしていたのだが、まさかこんな事態になるとは思ってもみなかった――
彼は人々がざわついている中にひっそりと紛れ込んだ。
「信託にいるあの黒い影のことだけど、まさかあの侍従長じゃないよね?」
「……いや、まさか。」
「そうだよね。あの侍従長はちょっと気難しいところはあっても、公爵様が信頼して重用してる人だから、北部の人が疑うわけないよ。」
「でも一度考えてみてくださいよ。あのタイミングでぴったり信託が現れるなんてあります?信託って、何をしても罪に問われない存在なんだから、裏切る可能性だってありますよ。」
人々は逆にジョディアクの発言のほうを怪しんで、彼を取り囲んだ。
「でもあなた、見たことない顔だけど。」
「……僕ですか?そんなはずないですけど。」
「どこの家の者だ?旅人か?」
ジョディアクは初めての酒で粗相をしたくなくて、腰を低くしてその場をそっと離れた。
彼の読みはあまり外れておらず、慎重だった。
人々は最初こそ理性的に反発していたが——
密偵がこれまでに起きた出来事を振り返りながら、神託と彼女の間には何の関係もないだろうと思っていたが、時が経つにつれ状況は変わっていった。
噂が公爵家の塀を越えて広まると、騎士や傭兵たちもその話に耳を傾け始め、そこから噂は爆発的に広まり、悪質な言葉が飛び交うようになった。
騎士たちは軽はずみな判断で噂に口を出すべきではないと考えて黙っていたが、傭兵たちは違った。
傭兵団の中の酒場では、かつてないほど大規模な宴が繰り広げられていた。
ジョディアクが惜しみなく金を使ったためだ。
度数の高い安酒とビールがテーブルごとにドラム缶で運ばれ、夏が近づいて特に仕事もない北部から手を引こうとしていた傭兵たちは、ようやく羽を伸ばして団の中で口を開き始めた。
「なあ、おい、最近なんか面白い噂ないか?」
「面白い噂がないわけないだろ?あれがあるじゃん。」
「ああ、それ。」
「おう、その信託の話か?」
「そう、それさ。北部の物価もかなりいいし、引っ越そうかって考えてたけど、その信託の噂を聞いたら一気に冷めてやめたよ。」
「そんな変な噂がある信託があるなんてな。俺も傭兵を長くやってるけど、あんな気味の悪い話は初めて聞いたぞ。」
酒にすっかり酔った傭兵たちの間に、ひっそりと紛れて座っていたジョディアクが、彼らに酒を注ぎながら口を開いた。
「まさにそれなんだよ。けどさ、もしかしてあの侍従長、その信託と関係あるんじゃないか?」
傭兵たちはお互いの顔を見合わせた。
確かにあの不気味な術を使うあの女、キャンディラってのは本物だった。
彼女の技で命拾いした者も何人かいた。
彼女が通り過ぎるときに、あいさつ程度の声をかけることはあっても、べつにみんな信託のことを大きく取り上げたりはしてなかったが——
「「闇」って、何かを呼び寄せるとかそういうことだろ?」
それもまた気分のいい話じゃなかった。
「そんなこと言うなよ。最近あいつ見かけもしないだろ?」
「そうだな、確かにちょっとおかしいよな?」
だが酔いが頭の先まで回っていたトゥンバは、そんな会話にも入り込んでいた。
彼は息子エロルドの脚が完全に治るという話を聞いても、それが全く信用できないデタラメのようにしか感じられず、すべてはあの密偵の戯言にしか思えなかった。
あの女があれほどすべてを防いでくれていなかったとしても、マモルが襲ってきた時に城壁の上にいた彼の息子エロルドの脚が、あんなふうに台無しになることもなかったはずだ。
「ふざけるなよ……みんな頭おかしいんじゃないか?なんであの密偵をありがたがるんだ?じゃあその技術を見て、あの女以外に別の『闇』があるって思えるのか?正直、住民たちは笑って面白がってるだろうけど、俺たちの子供たちは、あの恐ろしい女に背を向けられるかよ。」
トゥンバを知っている傭兵たちは、彼が酔って愚痴をこぼしているだけだとわかっていたが、そうでない者たちはその言葉に密かに耳を傾け、魚のように食いついた。
トゥンバはその反応が気分良かったのか、ビールをさらに一口で飲み干した。
顔は赤くなり、目は半開きのまま真剣にささやいた。
「……ところでお前ら、疑問に思ったことないのか?」
「何を?」
「俺はさ、あの女がどうやってあの傷を負って生きて帰ってきたのか、ずっと気になってたんだ。」
そこにいた傭兵たちは互いに目を合わせた。
みんな暗黙の了解でその件について話すのを避けていたが、どう考えても不可解な出来事だった。
『いや、どう頑張って前向きに考えようとしても、人間ならあの傷で生き残れるわけがないだろ?』
酒に酔った頭に、その考えが一斉に浮かび上がった。
アゼルダは神託から広まったという噂があることは知っていたが、その噂が自分と関係しているとは夢にも思っていなかった。
彼女はそんなことを考える余裕もなく、毎日、母が遺した短冊を解くことに没頭していた。
戻ってきてから3日が過ぎても、彼女の一日は数字が六つ並ぶ式と格闘することに埋め尽くされていた。
あらゆる本をひっくり返しては、紙を広げ、隣でぶつぶつ言っている彼女の部屋に、慌てた様子のジェフが飛び込んできた。
「急ぎの知らせです!」
「え?」
「首都から来ました。マディソン家の主(あるじ)?」
「うん、ちょっと渡して。」
ジェフが持ってきた急報には、小さな飾り紐も一緒に付けられていた。
アゼルダは飾り紐を解くより先に、手紙を取り出して開いた。
<こんにちは、アジェルダお嬢様。
お嬢様がご出発なさってから、もう一週間になりますね。
お嬢様のいないケリアエは、特に変わりもなく、ただ毎日曇り空ばかりです。
私の心も毎日どんよりしています。
伯爵の近くに大きな競技場が建つということで、工事の音で頭が割れそうに痛いです。
でも、こうしてお嬢様にお手紙を書くことができて嬉しいです。
お元気ですか?
数日前に出発されたお嬢様のお顔を思い出すと、また無性にお会いしたくなります。
こんなに急いでお手紙を書いているのは、ただならぬ噂を耳にしたからです。
北部にいらっしゃるお嬢様がご無事かどうか、ぜひご連絡ください。
そうすれば、私は安心できます。
嬉しい気持ちでいくつかのニュースもお伝えいたします。
まずお伝えする良い知らせは、今回北部への支援に赴く騎士団の予備軍に、私の夫が選ばれたということです。
先行審査に通らなかったらどうしようと落ち込んでいたのですが、北部に行けば赤ちゃんが生まれる前に十分な収入が得られるだろうと喜んでいました。
北部も秋頃までは安全だと言われていますし、それに北部公爵様が惜しみなく補償してくださいますよね?
無事に帰ってくることが分かっているので、不安で心配するよりも、ただ嬉しい気持ちで送り出そうと思っています。
次にお伝えする良い知らせは、以前お嬢様から頼まれていたお母上様の品々をいくつか見つけることができましたので、すべて同封してお送りします。
すべての品物に、お母上様の商標である蝶の印が刻まれていました。
ですが、無理に取り出されたのか、保管状態が良くなくて少し心が痛みました。
すべてお嬢様のお手元にございます。
いつもお嬢様の明るい笑顔が恋しいです。
北部でもきっと皆さんがお嬢様を愛してくださっていると信じています。
いつでも私が会いたくなったら連絡してくださいね。
まだ体が重たいですが、赤ちゃんを産んだら休暇を取って会いに行きたいです。
― 愛と懐かしさを込めて、ジュディより。>
手紙を読み終えると、ジュディの思いがひしひしと伝わってきた。
彼女もまたジュディを恋しく思っていた。
アゼルダは手紙を胸にしっかりと抱いてから、ひと息ついてそっと置いた。
次に会いに行くときには、ジュディの赤ちゃんへのプレゼントも用意して行こう。
アゼルダは手紙についていた飾り紐をほどいて手に取ったが、ふと手紙の一文が心に引っかかって再び手紙を手に取った。
「今回、北部に支援に行く騎士団の予備軍に、私の夫が選ばれたんです。」という文を見つけた瞬間、胸がドキリとした。
そうだ、手紙で時々やりとりしていたジュディの傭兵の夫が大怪我をして生活が困難になった、とあのとき話をしてきたのが、ちょうどこの頃だった。
別のことで頭がいっぱいだったので、ジュディのことをすっかり忘れていたのだ。
報告書の件で北部への支援金が減らなかったことから、当然、これまでいなかった兵士たちが増えるだろうとしか考えていなかった。
しかし考えてみれば、それとは関係なく夏か秋には支援軍がこのくらいの数でやってくることになっていたようで、ジュディの夫もその中の一人だったのだ。
ひたすら数字ばかりを追いかけていたせいで、手紙が来るわけでもなく、母と連絡が取れるわけでもないのに、これだけに心を奪われていたようだった。
ジュディの夫を守ってあげたかった。
ジュディは前世ではただのありがたい人だったけれど、今生では私の母のように大切な存在になった。
彼女が幸せでいてくれればよかったし、彼女の人生に大きな不幸が訪れなければいいと思った。
自分にできる助けがあるならば、してあげたかった。
どうせシェイドと自分は名目上の夫婦だ。
お互いに必要に応じてうまくやっているだけの関係。
北部貴族の婦人として王宮まで行ってきたのだから、しばらくは自分の存在も必要とされないはずだ。
ジュディの夫が所属する遠征隊の予定を知るためにも、すぐにでも情報士として働きに行こうと考えながら、彼女は手紙に添えられていた飾り紐を広げた。
「ラウル。」
ベッドの下の木の床に丸くなっていたラウルが、彼女の呼びかけに前足を突き出し、体を起こしてから、ぴょんとベッドの上に飛び乗った。
広げた飾り紐の中には、羽ペンから小さな人形、蝶の形をした指輪、手帳、手のひらサイズの絵本のような雑貨たちが入っていた。
ラウルは彼女の視線を追ってそれらを一通り見回し、匂いをかいだあと、大して関心もなさそうにアジェルダの太ももの上にあごを乗せて丸くなった。
「ねえ、ここから何か感じるとか、そういうのはない? よく見てみてください。」
[人間、あれは何なんだ?]
「母が使っていた物なんです。」
[ふん。人間の匂いがするならともかく、それだけじゃ。精霊術で何かした痕跡はない。]
「本当ですか?」
[ああ。]
ラウルがそう言うなら、そうなのだろう。
アジェルダは、今では顔もぼんやりとしか思い出せない母の遺品を手に取って、一つ一つ手でなぞってみた。
せめて造花でも一つ残っていれば良かったのに、几帳面な叔母はそれさえも残してはくれなかった。
彼女はその品々を隅々まで調べたが、そこから何かの文字や短いメッセージのようなものを見つけることはできなかった。
指輪の内側やペンの軸、書籍の余白までくまなく調べたが、特に目立ったものは見当たらなかった。
「ラウル。」
【また、なんで?】
ラウルは面倒くさそうに目だけ上げて彼女を見上げた。
そのときようやくアジェルダは、ラウルが自分が首都にいる間ずっと屋敷の近くにも来られなかったことを思い出した。
「早く終わらせて、また情報士として戻ってくるつもりよ。狩りに行くの。ね?」
【ほんとう?】
「ええ。明日すぐに出発するわ。」
ラウルは嬉しそうにぴょんと跳ねて床に降りると、しっぽをぱたぱた振りながら部屋中を駆け回った。
【どうして今日じゃなくて明日なの?】
「出発前に片付けておくべき問題があるの。」
アジェルダは、今日、自分の護衛兵を任命する予定があることを前もって聞いて知っていた。
どうせ任命されるのは自分で決めた護衛兵だ。
任命式をわざわざ遅らせるのもおかしな話だったし、そんなことをしたあとで他の護衛をあてがわれても面倒なだけだが、儀式には従順に出席しなければならない。
アジェルダは任命式の服を選ぼうと立ち上がったところで、ラウルが前足で顎をカタカタと鳴らしながら何かをつぶやいているのを聞いた。
[おいしいものは本当に我慢できない~]
本当に怖いのか可愛いのか分からない精霊である。
アジェルダは思わず小さく笑った。