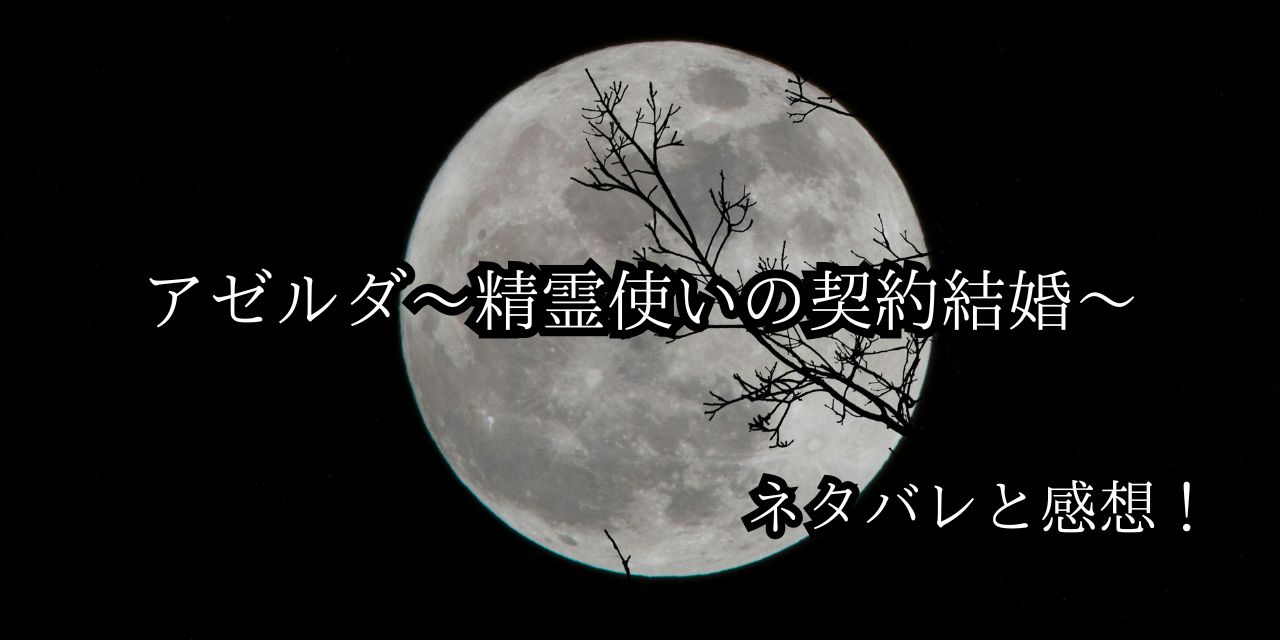こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

40話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 面白い関係
北部に戻ってから初めてシェイドに会った。
それは妙に意識する出来事だった。
アジェルダは公爵夫人としての化粧がうまくできているか確かめようと鏡を見た。
鏡の中の金髪に白い顔の女は、かつての精霊士だった自分とはずいぶん違って見えた。
剣舞を舞うときに普段使っていたのとは違う武器の剣を使ったり、何のためらいもなく舞を踊ったりしたことで、村の子供たちからは世の中は大きく変わったとはいえ、やはり気を張らざるを得なかった。
アジェルダも、タイ人が動くシルエットを見ただけで顔を見る前から誰なのかほぼ見当がつくほどだったから。
「尻尾が長ければバレやすい」という言葉があるが、まさにその通りだ。
彼女は、いつまでこの役目を続けるのだろうと思いながら、左右でかかとの高さが違う靴を履いた。
「ジェフ、準備できました。」
アジェルダはジェフの案内を受けて、大きな窓のある印象的な建物の中央ホールへ向かった。
そこは儀式やイベントが行われる時に使われる場所で、広く荘厳な雰囲気があった。
いくつか長椅子が置かれ、その前には床より少し高い壇があった。
「お越しですね、マダム。」
ブユが微笑んで彼女を迎えた。
「こんにちは、ブユ。」
証人として同席していたのはブユと、もう一人は灰色の髪の騎士だった。
どこかで見たことのある顔だったが、誰かは思い出せなかった。
そして、公爵もまもなく姿を現した。いつものように堂々とした様子だった。
引き締まった体にぴったり合った薄青の礼服を着た彼は、真面目な顔をしていた。
やはり彼はどこにいてもハンサムだった。
スタイルもよく、顔も整っていて見た目の良いイケメンなので、変な噂さえなければ本当に人気が出たことだろう。
どういうわけか、北部に戻ってからわずか3日ぶりに見るというのに、ずいぶん久しぶりに会うように感じられた。
首都ではずっと同じ部屋を使っていたからだろうか?
彼女は彼が自分をじっと見つめている気がして、彼を見上げた。
「こんにちは、公子。」
シェイドは顎を引きながら答えた。
「しばらくご挨拶をしようと思いましたが、食事も部屋で取られるとのことで、お一人の時間を望まれているのかと思い、別に訪ねてみました。」
アジェルダは首都で得た数字を思い出しながら、それらをあらゆるものと結び付けてみようとして、部屋にこもっていた。
部屋にはさまざまな書類が広げられていた。
追い詰められた状況だったので、彼を招く余裕すらなかったのだ。
「ちょっと忙しかったんですよ。」
「首都でのご活躍、いろいろと感謝していました。」
「もう何度もご挨拶したじゃないですか。」
「承知しています。」
無愛想な態度が、かえって相手に油断を与えるようだ。
アジェルダはそっと口元を緩めた。
彼は控えめに微笑む彼女の前に歩み寄り、手に持っていたものを差し出した。
アジェルダは反射的にそれを受け取ったが、それは剣だった。
しかもただの装飾用の剣ではなく、ずっしりとした重みと気品を感じさせるものだった。
アジェルダは驚いて彼を見つめ、腰に差していた剣を鞘から引き抜いた。
北部の象徴である雪の花の装飾が、ガード部分の両側に刻まれており、剣の重量を軽くするための「フラー」と呼ばれる溝が一筋、長く彫られていた。
大きな窓から差し込む光の中、その剣はきらめいていた。
見てみると、鈍く光を反射しているのは装飾用ではないとすぐにわかった。
形が整っているだけでなく、軽く作られており、それでいて硬度も兼ね備えた優れた剣だった。
しばらく眺めていると、頭上から笑みを含んだ声が聞こえてきた。
「剣身からご覧になりますか?」
「はい?」
「普通は剣身から見るものですから。」
アジェルダはようやく鞘に収められた剣を見つめた。
柄から鞘まで、薄青い地に白い雪の花が彫られた装飾は、それが北部公爵家の剣であることを示していた。
彼女はそれが北部雪の騎士団の剣とは異なるとすぐに気づいた。
あちらは金の装飾を使わないからだ。
金の装飾は公爵家の直臣であることを意味していた。
彼女はぼんやりと、それをしばらく見下ろしていた。
まさかそれを受け取ることになるとは思ってもいなかったのだ。
シェイドはアスコアとの長い試合の末に、その決断を後悔していなかった。
何度か鞘をなでる彼女の顔には、純粋な喜びが浮かんでいた。
花でも宝石でもなく、剣を手にしてこんなにも喜ぶ女性だなんて。
剣の美しさに感嘆するだけでなく、本当に剣を熟知しているという印象を受けた。
アスコはまだ彼女を完全には信じていないと明言していたが、シェイドの考えは少し変わっていた。
首都で多くの出来事があったのだから。
「でも、これは……」
「お受け取りください。これから騎士に任命され、剣を携える立場になるなら、一本は必要かと思いまして。さきほどのはお貸ししていたものですが、こちらは差し上げるものです。」
彼女の瞳に光が宿った。
貴婦人たちは剣がないとき、自分の装飾品を騎士の肩に置いて任命することもあったので、剣がなくても構わないと思っていたのだ。
……考えもしなかったこんなものを用意してくれるなんて、まさか想像すらできなかった。
「……本当ですか?」
「はい。」
彼女はおそるおそる鞘を下ろし、丁寧に金糸であしらわれた装飾を手でなぞった。
まるで北部の正式な一員として認められた気分だった。
前世では本当に夢にも見られなかったことだった。
少しは何かが変わったのだろうか?
まともに顔を合わせたこともなかったシェイドとこうして言葉を交わし、カールロス家の紋章が刻まれた剣を贈られるなんて。
一瞬、もし自分が本当に王子に忠誠を誓うことになるなら、自分はこの国の裏切り者になるということ、そしてそんなことが起こる前に彼の傍を離れなければならないという考えが頭をよぎった。
感動でいっぱいだった心が、そんな考えをするとたちまち罪悪感に染まっていった。
結局、今の自分は彼を利用しているのでは?
「剣一本でそんなにいろいろ考えてくださっていたとは思いませんでした。」
「いえ……あの……ありがとうございます。本当に嬉しいです。」
「喜んでくださって光栄です。」
そんなことを言える人だったのか?
「でも……剣を持つ必要はないのでは?これは後継者任命のためのものですし。」
「ご心配なく。本当に必要な武器であれば、惜しまず製作できるよう体制は整えていますから。」
とはいえ、こうした儀式的な任命式で剣を授けるのは少々古風なやり方だった。
アジェルダは襟元をつまんだ。
シェイドは口元を手で隠した。
「主役が来たようですね。」
こみ上げる感情を抑えつつ、剣を両手でしっかりと抱えながら前を見つめると、待機室側の扉が開いた。
オディエンは先ほどの軽装とは打って変わって、きちんとした衣装で騎士団の礼服を着ていた。
まだ身体に馴染んでいない様子の新しい服だった。
長い茶色の髪をひとまとめにして垂らしている様子は以前見た時と同じだったが、襟元をきちんと整えた姿はかなりの美男子だった。
アジェルダは何よりも彼の腰に下げられた無骨なツーハンドソードにまず目がいった。
見れば見るほど確信が持てた。
自分を庇って、首都防衛軍の何人かを相手にして命を落としたあの人だと。
任命式といってもそれほど大げさなものではなかった。
補佐騎士として任命を受けるオディエンと公爵、公爵夫人、そして証人として2人が参加する簡素な儀式だった。
オディエンはアジェルダとシェイドの前に進み出て、片膝をつき身を低くした。
シェイドはオディエンが今は黙って口をつぐんでいるが、本来はおしゃべりで女好きなことを知っていた。
「この者はどのようにして選ばれたのか?」
「ただ少し……知り合いの推薦です。」
シェイドはふとロイナの顔を思い出して、襟元をつまんだ。
ロイナはかなり前に北部を去っていたが、彼とまだ連絡を取っている者も多く、彼が推薦した可能性もあると思ったのだ。
「実力があるなら悪くありません。良い人選だったと思います。ただ、シルはこの屋敷に来てからまだ日が浅く、昇格試験もこれから受ける予定だったのですが、風紀上やや問題があり、それで少し保留にしていたところでした。たぶんその点をご配慮いただいた方が……本当に大丈夫ですか?」
アジェルダは、それが自分への遠回しな批判にも聞こえて、少し不快だった。
シェイドが長い時間かけて育てた候補者を、自分が奪ってしまったから、惜しいと思っているのかもしれない。
だが、彼には知らされていない事実があった。
アジェルダにとって重要なのは、イジャの実力もさることながら、それは第二の基準でしかなかった。
最も重要なのは、「信頼できるかどうか」だった。
つまり、自分の裏をかくような情報を漏らす人物ではないかという点だった。
「大丈夫ですよ。」
アジェルダは力を込めて顎を上げ、オディエンに向かって一歩踏み出した。
「オディエン・クリスティアン。」
「はい。」
「これから私の護衛を任せることになりますが、構いませんか?」
オディエンはその言葉に顎を上げかけ、再び胸に手を当てて姿勢を正した。
「もちろんです。私にとっては光栄なことです。」
「私のことをあまりご存じないかもしれません。」
「これから少しずつ知っていきます。」
「よく知っている」という答えや「良い噂を聞いています」などの口先だけの言葉が出るかと思ったが、そうではなかったのがアジェルダは嬉しかった。彼女は顎を引いた。
アジェルダはこのような状況を何度か経験していた。
前世で何度も。剣を抜かず、鞘に納まったままの剣を彼の頭と両肩に軽く触れることで、簡素な任命の儀式は終わった。
オディエンはジェフについていって部屋の割り当てを受けた後、寮に入ってしばらくそわそわと歩き回り、再び自分の部屋に戻ってきた。
とても真剣な表情をしていたので、アジェルダは思わず笑みをこぼした。
しかし今は初めて顔を合わせる従者としての形式を守らなければならないので、笑うわけにもいかなかった。
彼女は引き締まった表情のまま、手を差し出した。
「よろしくお願いします。」
オディエンは貴婦人の挨拶の仕方に少し戸惑い、一瞬動きを止めたが、すぐに手を握って軽く揺らした。
「よろしくお願いいたします。」
「本当によろしくね、オディエン卿。」
「今、“卿”とおっしゃいましたか?」
「はい。」
真剣だった彼の顔が一気に崩れた。
オディエンは片目をつぶりながら、いたずらっぽく両手をこすり合わせた。
「わあ、僕もついに騎士になりましたね。」
アジェルダも彼の言葉に思わず笑みをこぼした。
「雪の騎士団に正式に所属する日を待っていたでしょうに、こうして私の親衛騎士として苦労をかけてしまって申し訳ないです。」
「何をおっしゃいますか?はは、実はあのゴリタブンな敵陣の中で無表情に敵の首をはねるよりも、こうして美しいアジェルダ様をお守りする方が少し楽しいんです。女性は人類の宝石ですからね、アジェルダ様。」
あまりにもまっすぐな返事に、アジェルダは思わず笑ってしまった。
本当に真面目な人だ。
「アジェルダ様」と呼ばれるのはなんだか照れくさい。
普段その呼び方をするのは彼女を遠ざけたい時だけで、「お嬢様」と呼ばれる方がまだ多かった。
オディエンが本当に彼女専属の護衛だという実感が湧いてきた。
「そんなふうに言ってくれてありがとう、オディエン!」
その時、ジェフがお茶を持ってきた。
アジェルダはジェフを下がらせ、オディエンとテーブルを挟んで向かい合って座った。
オディエンは意外にも、任務に取り組む時は真面目な性格のようだった。
先ほどまでののんびりした態度はどこへやら、今は誠実に彼女を見つめて話した。
「まず、アジェルダ様がご希望される警護の方針を事前に教えてください。それに従います。」
「いいですね。何から決めればいいかしら?」
「警護する際、ドアの外に立つか、中にいるかを決めてください。」
「警護はドアの外で。今は特に危険なこともないので、呼び出しがない限りは隣室にいる程度で構いません。」
オディエンは顎に手をやった後、アジェルダの手のひらをじっと見つめ、かつての握手の感触を思い返してみた。
明らかに筆だけを持っていた女性の手ではなかった。
「剣を使えると聞いたのですが、本当ですか?」
「はい。」
「次の機会に、実力をきちんと確認してもよろしいでしょうか? 実力に応じて、私の対応も変わるでしょうから。」
「いいですよ。」
アジェルダは話題を変えようとしたが、オディエンは彼女の手首をそっと掴んで見せた。
「力で勝てなければ、私は勝てないかもしれません。」
「えっ?冗談ですか?」
彼女は「何を言ってるの」というように手を振って笑ったが、彼は笑って済ませなかった。
「いや、ただの勘なんですが……どうしてそんな風に感じるのか自分でも分からないんです。」
戦士の勘を軽んじる剣士はいない。
それ以上この話を続けたくなかったアジェルダは、少し寂しげな視線を逸らした。
その後、いくつかの話題が交わされた。
万が一に備えて退避動線を確認しておく話や、その後に時間を設けて一緒にまた話すことができれば嬉しいと彼が言った。
ふたりはお互いに気になる点を次々と質問し合い、意見を出しながら護衛に関する取り決めを行ったため、話がまとまるまでにはそれほど時間はかからなかった。
「それだけおっしゃりたかったんですか?」
アジェルダは湯飲みを口に運びながら、妙な質問をする彼を見つめた。
オディエンの目はにっこりと笑っていた。
「どういう意味でしょうか?」
「女性の心にはいくつもの考えがあるものです。わざわざ私にあれこれ質問されて、こうして向かい合って座っているということは、何か理由があるのでは?」
話すことがあって座ったのは事実だった。
素早く状況を見極める能力はあるようだが、実際に接してみると本当に老練な人物だった。
アジェルダはこうしたやりとりに慣れてはいなかった。
「遠慮なくおっしゃってください。私、実はアジェルダ様のこと、結構気に入ってますよ。ちょっとした噂も耳にしましたし。」
彼女は襟元を軽く整えた。
「いいですよ。でも、余計な言葉はつけずに、そのまま話してくれますか?」
「余計な言葉って……」
「どうしてか聞かないんですか?」
オディエンは襟元を直しながら、ひび割れた石の突起を指先で軽く叩いた。
「そうですね、私は少しおしゃべりな方です。だから、もし命令されることなら大体はうまくできると思いますが、なぜか“断る”というのは難しく感じるんですよね。」
「説明が必要なことならしますよ。でも、そうでないこともあるかもしれません。もし私の補佐役として居るのが不快なら、今すぐでも……」
彼は手を差し出した。
「いえ、私の方が話題を逸らしていたようです。続けてください。」
アジェルダはまた襟元を整えた。
「まず、いくつかお伝えしておきたいことがあります。」
「はい。」
「私はこの宮殿に、それほど長くいる予定ではないんです。」
オディエンの表情が奇妙に変わった。
「どこへよく行かれるんですか? 親戚のところ?」
「どこでも。」
「言いにくい場所とか?」
彼女は聞こえないふりをして、言うべきことだけを口にした。
「とにかく、旅に出ることがあって席を外すことが多いのですが、そのときは一緒に行くのが難しいです。それは先に知っておいてください。」
「……私がアジェルダ様にとって唯一の護衛なのに、旅行に行くときはついて来るなという意味ですか?」
「そうです。」
オディエンは口を不満げにへの字にした。
「でも私は、アジェルダ様にとって唯一の護衛なんですよ?」
同じことを二度も繰り返して言うのは、ただ素直に納得する気がないからだと思われたが、彼女にとっては重要ではなかった。
いずれにせよ、彼を同行させるつもりはなかったのだから。
「私と両親の名誉にかけて、絶対にカルロス家や北部の人々に害を及ぼすつもりはありません。浮気をするわけでもないし、何かおかしなことを企んでいるわけでもないです。でも私は旅をしながらあなたたちを連れて回るわけにはいきません。オディエン、あなたを信じていないからではなく、そうではないとだけ理解してくれればいいんです。」
「信じていないわけではないのに、連れて行けないのですか?」
「ごめんなさい。でもこれはどうしようもないことだから、そう理解してください。」
オディエンはそれは無理だと言いかけたが、彼女の冷静な顔を見て、この女性を説得することはできないと気づき、口をつぐんだ。
考えてみれば、雇い主はアジェルダ・カルロスであり、自分はただの補佐騎士に過ぎない。
だから、彼女が旅に連れて行かないと決めたとしても、文句を言わずに従えば、責任も減り、労力も少なくて済むだろう。
それなら良いことではないか?
しかし、傭兵団では時折噂されていたある武勇伝によれば、彼女は良家の貴族のようで、公爵の隣に立つのにふさわしい女性のようだった。
北部のすべての人々が公爵を尊敬し従っていたが、実のところ彼は公爵をあまり好んではいなかった。
公爵が優秀で、高潔で、清廉な点は気に入っていたが、自分を顧みない様子が少し気に入らなかった。
そういう人間は、いくら優れていても大義のために命を捧げてしまうものだ。
そして、そばにいる大切な人を守ることさえできないこともあるからだ。
だから彼は、公爵夫人の後援を引き受けなければならないと初めて聞いたとき、打算に満ち、夫選びを間違えた不幸な婦人の後見を任されることになると思っていた。
けれど実際に会ってみると、なんとも不思議な感じだった。
思っていた通り、清らかな雰囲気に包まれていたが、それはただの第一印象に過ぎなかった。
近くに座って話してみると、軍事についても無知ではなかったし、自分の意見を述べるのにも遠慮がない人物だった。
「わかりました。ひとまずそれでいきましょう。これからはもっと多くの仕事を任せることになると思います。」
「気分を害したならごめんなさい。」
申し訳なくはあるが、意見を変えるつもりはないという意味だった。
オディエンがかすかに笑ったとき、アジェルダが彼の手をぎゅっと握った。
「代わりに、色々とご存知なあなたにお願いしたいことがあります。」
彼は多くのことを知っていた。
騎士学校はもちろん、旅してまわった場所も多く、知っている傭兵も多かった。
誰が彼を推薦したかはわからなかったが、彼自身が自分について何らかの紹介をしていたのだろうと思った。
「お話ください。」
「秘密のことです。」
「女性の秘密なら、何であれ守らなければなりませんね。」
「冗談じゃなく、本当に。公爵夫人にも知られたくありません。これは私の私生活ですから。旅に関することも、その他もすべて。」
普通、女性がこんなふうに言う時は、愛人が別にいる場合が多いものだ。
オディエンは肩をすくめた。
それでも主人が一人だけなのは気が楽だ。
あちこちから来ては言葉を伝えるようなことは性に合わなかった。
「口は固く、秘密はしっかり守ります。」
「ありがとう。」
「それで、お願いというのは……?」
「ああ、それはこちらのことです。」
アジェルダは、自分の前に積まれていた装飾品と紙切れを彼の前に押しやった。
「ここにある装飾品とこの数字たちを見て、これが何を意味しているのかを解き明かしてください。」
「つまり、暗号を解けということですか?」
「はい。間違いなく、これらが示している何かがあるはずなんです。それが“人”かもしれませんし、指名かもしれないし……とにかく何かがあるんです。」
オディエンはその言葉があまりに突飛だと感じたが、同時に彼女の切実な表情を目にして、興味を覚えた。
一体何がそんなに重要で、わざわざ秘密裏に調査を依頼するのだろう?
もし本当に秘密なら、なぜ今日初めて会った自分を信じて、それを託そうとするのか?
それが解ければ、彼女との距離ももう少し縮まるのではないか?
なぜか、それがアジェルダ・カルロスが絶対に自分の口からは語らないと思われる彼女の秘密に接近できる鍵になるような気がした。
好奇心がくすぐられる。
「わかりました。試してみましょう。」
「本当ですか? 本当に……どうかお願いします。」
オディエンはブローチを懐にしまった。
「いつ出発するおつもりですか?」
「今のところ、最も早い計画は明日です。」
「明日ですか?」
「はい。」
いや、この女性は何なのか、メッセンジャーなのにこんなにあっさりしているのか?
彼女は「信じてください」と言っていたが、城の外へ連れ出すことができないという点を見れば、それほど信頼されているようには見えなかった。
護衛騎士に憧れがあった昔とは異なり、最近の人々は単なる雇用主と被雇用者の関係として考えるのが一般的だったため、特に気にはならなかった。
なんとなく彼は、彼女の声や雰囲気にどこかで見聞きした記憶があるような気がしたが、似た髪型の女性たちをいくら思い浮かべてみても、思い出される人はいなかった。
彼はこれは勘のようなものだと思いながら、自室に戻って再び約束を交わした。
どうやらこの秘密の多い雇用主とは、面白い関係が築けるかもしれないと感じた。