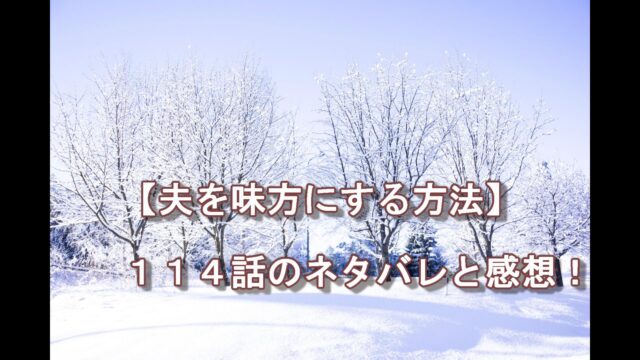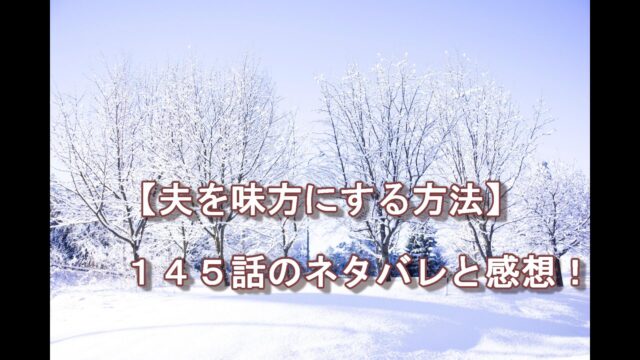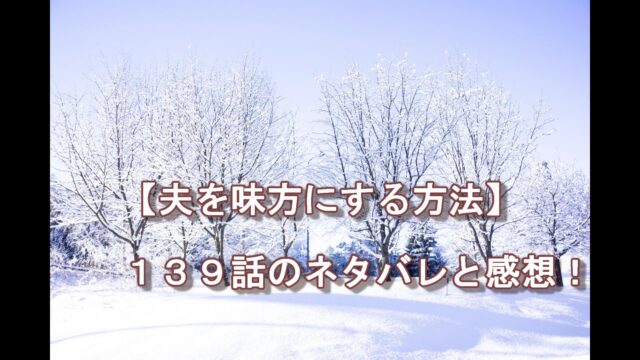こんにちは、ピッコです。
「夫を味方にする方法」を紹介させていただきます。
今回は200話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

死ぬ前に読んでいた本の中の悪女ルードべキアに憑依してしまう。
前世では養子となった家族から虐待を受けていたけど、ルードべキアも同じような境遇だった…。
しかも父によって政略結婚させられた北部最高の冷血な騎士イースケは原作で自分を殺すことになる夫だった!
小説の内容をすでに知っているルードべキアは、生き延びるために夫を愛する演技をするが…
ルードベキア:ルードベキア・デ・ボルヒア。本作の主人公。愛称はルビ。
イースケ:イースケ・バン・オメルタ。ルビの結婚相手。愛称はイース。
エレニア:エレニア・バン・オメルア。イースケの妹。愛称はエレン。
フレイヤ:フレイヤ・バン・ピュリアーナ。イースケの幼馴染。
ボルヒア:教皇。ルビの父親。
チェシアレ:チェシアレ・デ・ボルヒア。長男
エンツォ:エンツォ・デ・ボルヒア。次男。
ローニャ:ルビの専属メイド

200話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- ちび王子様の夏⑨
暑い天気の中で急にひんやりとした空気が流れ込んできたので、顔を上げるとその理由がわかった。
天井にツララがびっしりとぶら下がっているのが見えたのだ。
真夏にツララなんて!
しかも、こんなに大きくて美しいツララを見るのは初めてだった。
冬の祭りで行われる地域のツララ品評会に出したら、間違いなく優勝するだろう。
私が興味津々で眺めている間、ユリもダニルも口をぽかんと開けたままだった。
二人とも顔が驚きと新鮮な気持ちで満たされているようだ。
何かに感動して言葉を飲み込んでいるのだと感じた。
先に話したのは例のやつだった。
「ここが、例のネズミの家かな?」
「・・・。」
「向こうに何かあるか見てみよう。何か食べられるものがあるかもしれないし。」
「・・・。」
「でも、あいつら何を食べて生きてるんだろう? 果物とか、そんなものかな・・・?」
そう言った途端、それまで静かだった例のやつが急に反応した。
彼らは突然前に出て、自分たちの意見を言い始める。
ユリは、ふとっちょのウサギが普通のウサギと違って肉食かもしれないと考え、小動物や鳥を一口で丸呑みにしてしまうのだろうと主張した。
一方、ダニルは、あれは熊のように魚を捕まえて一口だけ食べて捨てる偏食家かもしれないと主張した。
ダニルが魚の話をした瞬間、ユリが吐き気を催した。
「うっ、うええっ!」
「うわぁえぇっ!」
ユリが吐いた途端、すぐにダニルもそれに続いて吐き始めた。
そのあまりに悲惨な光景を見た私は、それ以上耐えられず、洞窟の奥へ逃げ込むように走り出す。
すると例のやつらは、どこかへ一人で行こうと私を追いかけてきた。
「追いかけてくるな!」と叫びながら叫び続ける私。
その時、突然横に分かれた道が尽きたかと思うと、まるで迷路のようにいくつもの分かれ道が現れた!
行き止まりなのか抜け道なのか分からないが、とにかく一目散に飛び込んだ。
見た目も怪しくて危険そうだった。
「止まって!」
私はかろうじて恐る恐る立ち止まった。
私が急に止まると、後ろにいたユリがバランスを崩して私にぶつかってきた。
そこまではまだ問題なかった。
問題はその後だ。
ダニルが足を滑らせたのか、何かに引っかかったのか、勢いよく私たちを巻き込んで倒れたのだ。
「ぎゃあああ!」
私たちは綺麗に並んで人間ドミノのように倒れ、洞窟の中で一番広い通路を転がり落ちていく。
そのまま止まることなく、滑りやすいミコルムの上をずるずると滑っていった。
ただの滑りやすい床だけでなく、ぬるぬると油のような感触のあるミコルムで、ところどころ揺れるように動いているものだった。
さらに、どこからともなく聞こえる奇妙な音が頭の中をかき乱す。
「ぎゃあああああああ!」
目の前がピンク色にぐるぐる回り、心臓が今にも破裂しそうだった。
もしどこかでミスして頭を打ち、吹き飛ばされたら死んでしまうのではないかと心配になった。
いや、それ以前に、髪の毛がすべて引っこ抜かれるかと思うとゾッとする。
ここで何もせずに流されていったら、この先はもう何も怖くなくなる気がした。
「死ぬほど怖い」という言葉の意味が少しだけ分かった気がする。
もちろん、私は恐怖に怯えるわけではない。
王子は怯えるようなことはしないものだ。
ただ少し残念に思うだけだった。
幸運にも、その瞬間、果てしなく続くと思われた通路が突然終わり、私たちをまとめて外に投げ出した。
私たちはどこか巨大な空間の中を宙に舞い、最後にはコロコロと転がりながらようやく停止した。
互いに大声を出しながら責め合っていた私たちも、その瞬間、一斉に口を閉じた。
全員がぼんやりと茫然自失になり、身体が固まったようだった。
私たちは腕と脚を何とか広げて、かろうじてその場に倒れ込むように留まった。
息を整えて深呼吸した。
ここは一体どこなのだろう?
ただ地下の洞窟のような場所だとしか言いようがなかった。
だが、私が想像していたような暗くて不気味な地下洞窟とは違い、全く暗くはなかった。
薄暗いものの、手前が見えないほどではなかった。
なぜだろうと思っていると、ぼんやりしていた目がようやく焦点を合わせられ、理由が分かった。
洞窟の天井や壁のあちこちに張り付いている凍りついたものがぼんやりと光を放っていたのだ。
氷も光るのか?
本当にそれが氷なのかどうかは分からないが、なんだか新鮮で美しく感じた。
「みんな、あれ見える?」
向かい側でユリがふらふらと立ち上がりながら答えた。
ユリは私の質問に答える代わりに、またもや吐き気を催したように人形のような動きで周囲を見渡していた。
そして、再び大声で叫んだ。
「お前のせいでみんな死にかけたじゃないか!頭がおかしいのか!」
「うるさい!」
「俺が何をどうしたって言うんだよ!?」
隣に倒れ込んでいたダニルがぴょんと立ち上がり、大声で叫び返した。
ユリはそれにまた声を荒げることはなく、代わりに、凍りつくような冷たい怒りを込めた言葉で攻撃を始めた。
正直、聞いたこともないような罵り言葉ばかりで、それがどういう意味なのか理解するのも難しかった。
それでも雰囲気があまりにも不快だった。
もしこの場に祖母がいたら、ユリの尻に火を付けていただろう。
私はダニルが泣き出すのではないかと思ったが、代わりに彼も同じく聞いたこともないような罵詈雑言を返し始めた。
まさかこの二人がこんなにも罵倒合戦に強いとは思いもしなかった。
もしダニルの父がこの場にいたなら、きっと彼の耳を引っ張って叱り飛ばしていただろう。
だんだんと聞いているのが辛くなってきた。
「これからはお前たちと一緒に行動しない!」
両手で耳を塞いで必死に耐えながら互いに罵り合っていた二人が、その声に一瞬止まった。
呆然とこちらを見つめる姿に、私はつい苛立ちが爆発してしまった。
「何・・・?」
「何だって?お前たちと一緒に行動しないって言ったんだよ!」
「え、急にどうしたの・・・」
「お前たちとの遊びはもう楽しくなくなった!一緒に冒険に来たってのに、ずっと喧嘩ばかりで罵り合って、こんなの友情じゃない!」
言えば言うほど、自分の言葉に怒りが湧いてきて、思わず声が大きくなった。
私は苛々しながら振り返ろうとしたが、その時、呆然と私を見つめていたダニルが、突然涙をぽろぽろ流し始めた。
突然のことで何が起きているのか分からず、私は戸惑うばかりだった。
そんな私をよそに、ユリが泣きじゃくるダニルにそっと手を差し伸べて背中を優しく叩いた。
「おい・・・。なんでまた急に泣いてるの?落ち着け、バカか!アルヨシャが本気で言ったことじゃないだろ!」
ユリの不器用ながらも優しい態度にもかかわらず、ダニルは涙を流し続け、静かにすすり泣いていた。
私はため息をつきながらコートの襟を正した。
「本気で言ったの?」
「はぁ、でも僕たちは永遠のライバルじゃん!」
「お前みたいにろくに食べられないライバルがどこにいる!」
「おい・・・!ごめん、ごめんってば、もう喧嘩しない・・・」
「僕にじゃなくてお互いに謝りなよ!」
ユリは乱暴に鼻をすすりながらダニルを振り返り、少し低い声で謝罪の言葉を紡いだ。
ダニルもまた鼻をすすりながら自分の非を認め、申し訳なさそうに謝る。
そして二人は振り返って私に今までの言葉を撤回しろと要求してきた。
ああ、一体いつから同じ側だと思ってたんだろう!もちろん、それが本気だったわけじゃないのに。
しばらくして、私たちはまた仲良く集まり座った。
「光る氷を見るのは初めてだ。」
「僕も。」
「私も。」
少し前に出てきたヌグリ(タヌキ)怪物が作ったものなのだろうか、とダニルが言うと、ユリはあれはヌグリではなく、ウサギの怪物だと主張した。
また言い争いが始まりそうだったが、ダニルはいつものように反論する代わりに、冷たい床に手をつき体を震わせた。
真夏なのに氷が張る場所なのだから寒いのは当然だった。
じっと座っていると、さらに寒さが増してきたように感じ、私はついに立ち上がった。
立ってみると、この地下洞窟がさらに広大であることに気づいた。
驚くほど広大だった。
暗くて何も見えない道もあれば、壁の終わりが見えない場所もあり、天井も非常に高かった。
この森で生きる生物とは一体何なのだろうか。
ただ壮大なもののようだった。
目を大きく開いて周りを見渡すと、少し前に私たちが落ちてきたトンネルの穴が高い場所に見えた。
あの高さからここに落ちてきたとは信じられないほどで、しかも無傷だったという事実が不思議だった。
私たちは一体どこにいるのだろう?
凍りついた岩の集まりの中にいるのは分かっていたが、考えれば考えるほど、もし普通の岩だったら大怪我をしていただろうと思った。
足元を確認しようとしたが、暗くてよく見えない。
私は片方の足を軽く叩いてみた。
隣で見ていたユリも同じように足を叩いた。
ガリガリした感じがするかと思えば、意外にも足はほとんど痛くなかった。
むしろちょっと変な感じがした。
まるでベッドの上で跳ねるような感覚だと言えばいいのだろうか?
あまりにも硬いのに、その感触は不思議な柔らかさがあった。
ユリも私と似たようなことを感じたのか、黙って頷いていた。
足を揃えて、自分が一番上手にできることに挑戦した。
つまり、その場でジャンプするということだ。
「アルヨシャ、見て!」
「わあ!」
ベッドほどの高さではなかったが、それでもかなり高く飛び上がった。
私たち二人は一瞬夢中になってぴょんぴょんとその場でジャンプを繰り返した。
その間、ダニルは何を考えているのか、きちんと立ったまま私たちをじっと見守るだけだった。
ユリが「あなたもやってみてよ!」と声をかけても、彼はただ静かに立っていた。
なぜだろうと思いながら少し止まった私は、遅れて何かがおかしいことに気づいた。
「まさか足を怪我したの?」
「・・・いや。」
「じゃあ歩いてみて。ここからあそこまで。」
ダニルは首をかしげながらも、怪我をしているわけではなく、ただ足首が少し痛むだけだと答えた。
天真爛漫な性格の彼にしては、なんだか似合わない態度だ。