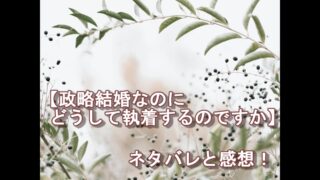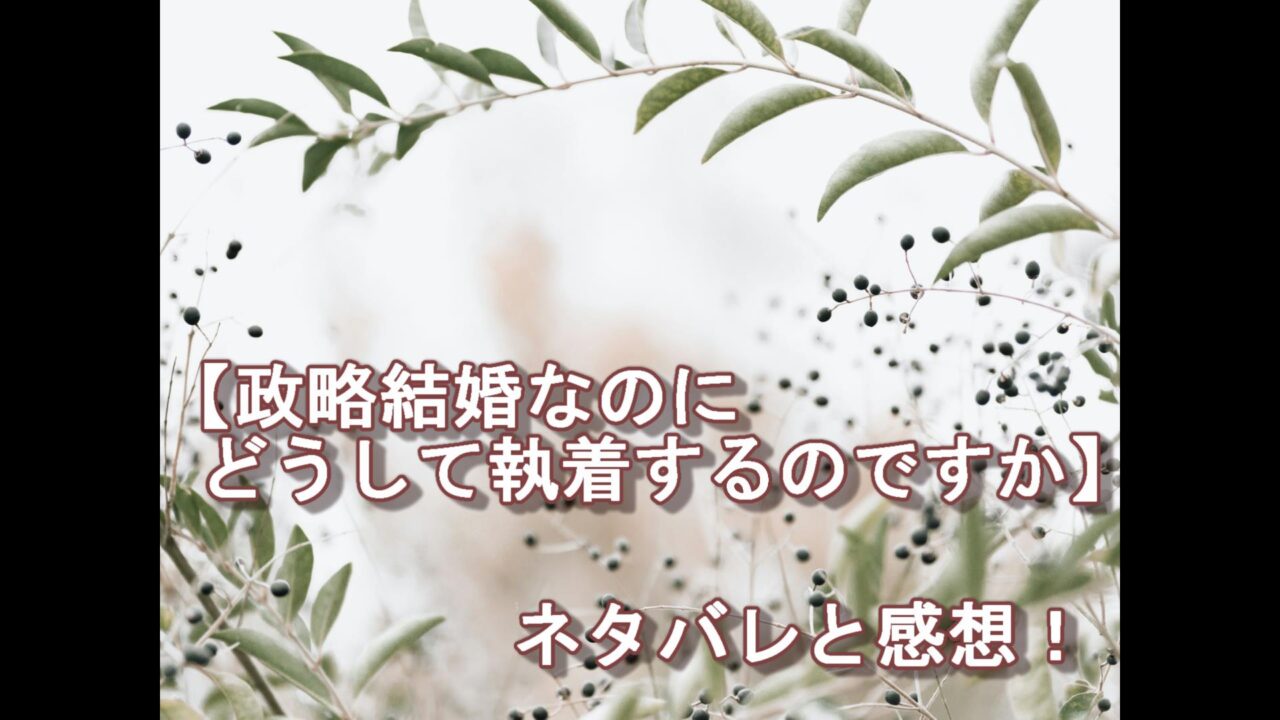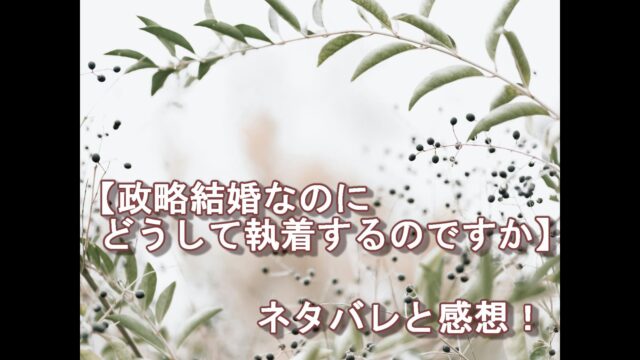こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

108話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 清算すべき縁
探しに来ないなら、こちらから行くしかない。
夫と再び会うために、ナディアはとても簡単な方法を選んだ。
つまり、グレンが必ず通るしかない場所で、じっと座って待つことにしたのだ。
『自分の部屋には戻ってくるよね。ちゃんと寝たかしら?』
予想通り、日が沈みかけたころ、遠くにグレンの姿が見え始めた。
部下と何やら会話をしながら歩いていたせいで、彼は入口に到達するまでナディアの存在に気づかなかった。
彼女は腕を組みながら口を開いた。
「グレン、私とちょっと話をしましょう。」
「ナ、ナディア?」
「ええ、私です。領主様を少しお借りしてもいいでしょうか?」
最後の言葉は彼のそばをちょこちょこついて来ていた部下に向けた質問だった。
マダムの質問が終わるや否や、部下は少しの戸惑いもなく答えた。
「はい、忙しい予定はありません。」
「そうですか。では、中に入りましょうか?」
「………」
反論する余地はなかった。
彼は仕方なくナディアの後をついて行かなければならなかった。
カーテンを開けて入ると、主人の性格らしくきちんと整理された部屋が見えた。
ナディアは整然と整えられたベッドの上に腰を下ろし、言った。
「グレン、最近私のことをちょっと避けてる気がするんですけど?」
「いや、最近ちょっと……その、忙しくて……」
「確認しに来たので、忙しいせいだって言い訳はしないでくださいね。まさか私が嫌いになったわけじゃないでしょう?」
「い、いや違う!」
軽い冗談のつもりだったが、反応は激しかった。
グレンは本当に困ったような表情を浮かべた。
その反応を見ると……。
『驚かせたいな。』
ああいう反応の鈍い男をからかうのは、なかなか楽しいことだ。
ナディアがくすくす笑いながら言った。
「私って本当にズボラじゃないですよね?」
「そんなはずないよ。私はただ……」
グレンは顔を赤らめながら視線を逸らした。
「ちょっと、面食らっただけです。」
「面食らった?それってどういう意味ですか?」
「いろんな意味で……」
「ふうん。」
ナディアの目がしょんぼりとした。
表情だけを見ると、確かに初めての恋愛でどうしていいかわからない不器用な子のようだった。
かわいい。だからもっとからかいたくなる。
彼女は彼の服の裾をそっとつかんで引っ張りながら尋ねた。
「私のこと、嫌いになったんじゃないですよね?」
「なんでそんな心配を……」
「じゃあ、キスしてください」
「えっ?」
「まだ私のことが好きだって証拠を見せてくださいよ。早くキスして。ね?」
グレンが大きく目を見開いた。
彼はしばらくためらったあと、体を動かした。
「君が望むなら……できないことはない。」
「どうぞ。」
彼がベッドの隣に腰を下ろすと、隣のマットレスが少し沈んだのが感じられた。
そして右手が彼女の肩の上に回される。
グレンはナディアの目をまっすぐに見つめながら近づいてきた。
彼女は思わずうろたえてしまう。
『なんでこの人……キスしようとする時はいつもまっすぐ目を見るの?』
本当に初心なのか、それとも初心を装っている老獪なのか分からなかった。
彼の顔が息づかいを感じるほど近づいてきた。
柔らかな感触が唇に触れる。
「…あ。」
それでもグレンは彼女の目をじっと見つめていた。
なぜか負けたくないという意地からか、ナディアも視線をそらさなかった。
互いに目を見つめ合いながら、二人はキスを交わした。
先に身を引いたのは、恥ずかしさに耐えられなかったナディアだった。
恥ずかしそうに微笑みながら唇を舐めた彼女は、気まずさを忘れるために冗談っぽく口を開いた。
「でも、私たちこんな会話してたの……外に聞こえちゃってなきゃいいけど。」
嫌われたのか、面倒くさいと思われたのか、そうでないなら証拠としてキスしてって言ってるようなもの。
みんなに聞かれたら恥ずかしすぎるセリフだった。
でも、きっと無視されると思っていたのに、グレンの返答はとても堂々としていた。
「心配ないよ。」
「総司令官が戦場で堂々と恋愛したって誰も文句言えないし。そうしていて悪口を言われるかもしれませんよ? もう少し真面目に考えてみてください。」
「そういうことじゃなくて、柵の周りの兵士たちに聞いてみたんだ。」
思いもよらない返答に、彼女の目が丸くなった。
「……人々に聞いたんですか?一体いつ?そんな話は聞いてませんけど。」
「ここに入ってくるときから。目つきで話したんだ。ちゃんと察していたみたいだ。」
「………」
ナディアはしばらく沈黙した。
柵の周辺を守っている兵士たちに聞いたなんて。
その意味は――
「じゃあ、この周囲には私たち二人きりってことですか?」
「そうだよ。聞く人もいないし、大丈夫。」
「いや……」
彼の手がナディアの肩をなで始めた。
しかし、そんな感触さえ感じられないほどに、ナディアの意識は別のところに向かっていた。
彼女はその場から勢いよく立ち上がって叫んだ。
「じゃあ、あなたを守ってくれる人が近くにいないってことですよね!」
「……え?」
「ここは戦場ですよ!いつどこから危険要素が飛び出してくるか分からないんです!でも背後を取るなんて、いくら優先順位があるとはいえ、ちょっとやりすぎじゃありませんか?」
「いや、ここは私たちの本営の韓服ブースだぞ。危険な要素なんてあるはずが……」
「もしかすると暗殺者が紛れ込んでいるかもしれませんよ。あなた、自分の身分についてもう少し自覚を持つ必要があるようですね。ここにいてください。人を呼んできます。」
そう言って、静かな足取りで彼女はテントの外へ向かっていった。
大きな幕舎の中にグレンがぽつんと残されるまで、それほど時間はかからなかった。
「はぁ……」
彼はナディアが去った時と同じ姿勢で、しばらくの間ぼんやりと座っていなければならなかった。
敵の指揮官が重病にかかったという情報を得ておきながら、何もせずにいるのなら、それは愚か者の集団としか言いようがないだろう。
幸いにも北部連合軍はそんな愚か者の集まりではなかった。
バラジート公爵の健康状態に関する噂は瞬く間に広がり、その速さに比例して混乱も広がっていった。
勝利の兆しを感じた一部の貴族たちは、降伏するかのように北へ戻ってくるほどだ。
だが、それでもまだ不十分で――
「決定的な一手が足りません。」
「このままでは長期戦になるしかありません。本当にまともな大勝が一度あれば勝敗が決まるというのに……」
「大軍をにらみつつ時間を引き延ばす戦略を取ってはいますが――」
南部が長い月日をかけて蓄えていた戦力がどこかへ行くのではなく、彼らが持ちこたえられずに崩れてしまう方法しか残されていない。
会議場のあちこちからため息が漏れ始めた。
「引きずり出して、一気に叩き潰せればいいんですけど。」
「例えば川に追い落とすとか?」
「素直についてくるとも思えませんし、乾季で水量も不足しています。不可能と思われます。」
「それもそうだな。では森の中に引き込んで燃やすというのは?」
「乾いていてよく燃えるとは思いますが……純粋に誘引できるかが問題ではないでしょうか?森の中に陣を張るのは、禁じられた行為中の禁じられた行為ですよ。」
「まあ……いくらなんでもそこまで愚かではないでしょう。」
このまま中途半端な勝利で満足しなければならないのか?
会議室の雰囲気がまたしんと静まりかえった瞬間だった。
静かにしていた誰かが口を開いた。
「つまり……誘い出した敵を一気に叩き潰したいということですよね?」
まさにナディアだった。
普通であれば女主人が出席する席ではなかったが、彼女が共にいることに疑問を抱く者は誰もいなかった。
「今、私の父の代わりにバラジート軍を指揮しているのは誰ですか?」
「今のところ、二手に分かれているそうです。エイデン・エルンストが率いる兵力は工場地帯へ向かい、現在私たちの前にいるのはタクミ卿だそうです。」
「アラファド卿が戦死した後、彼が指揮権を引き継いだとのことです。」
「ふむ、やはり。」
ナディアが満足そうに微笑んだ。
その笑顔に、グレンの心臓はドキリとした。
「それなら、私がお手伝いできると思います。」
「どうやって?あらかじめ言っておくけど、危険なことをするなんて考えは夢にも見るな。」
「そんなに危険じゃありません。ただ、囮の役割をするだけですから。」
その言葉に、グレンは一度目を閉じてから開けた。
「……ナディア、まさかそれが危険じゃないなんて……そう考えているわけじゃないよね?」
「本当です。まずは私の話を聞いてください。」
実のところ、すぐにでも彼女の話を止めたかった。
自分が危険を引き受けるなんてことを言おうとしているのではないか?
しかしグレンにはそれができなかった。
ナディアは、自分の言いたいことを言い、自分のしたい行動を取れる人物だった。
彼女を止めて反感を買うくらいなら、無理に止めない方がましだった。
「タクミ、あの人のことなんですが、今ごろ私に腹を煮えくり返してると思います。私の顔を見るだけで怒りで目がひっくり返るくらいに。私が脱出する際に少しばかり……ごまかしを使ったんです。たぶん相当…」
「だから、彼らが目の前に現れたら、前も後ろも見ずに突っ込んでくるってこと?」
「はい。どんな手を使ってでも、もう一度捕まえたいでしょう?そんな相手が鼻先に現れたら、じっとしていられると思いますか?」
グレンはきっぱりと言い返した。
「ダメだ。危険すぎる。」
「危険ではないとは言い切れませんが、あなたが想像しているほどには危険ではないと思います。」
「それが今、言葉として成り立つとでも……!」
「馬に乗って逃げる私の背後に矢を放つことさえしませんでした。もしかして私が怪我でもしたら困ると思ったのかもしれません。」
「………」
最後の二文は、もしかして明らかな誤解を招くかもしれないと思い、グレンに対して言い訳のように語ったものだった。
だが、違ったのか、彼の表情はひどく険しかった。
「ちなみに言うと、その人に対しては何の感情もありません。」
「知ってるよ。あいつが一方的に君に執着しているだけだってこと。」
「知っていると言ってくれて安心しました。」
ナディアは次の文から声を大きくした。
会議場にいる全員に聞こえるように。
「もちろん、私の姿を見ても動揺しないかもしれません。罠にかからないかもしれません。では、その時に行って別の方法を探せばいいのではないでしょうか?」
「……」
「試してみる価値がないとは思いません。」
「ご自身が危険にさらされるかもしれませんよ?」
「それなら、私のそばにいてください。危険なとき、守ってくれるように。」
「………」
グレンが口を閉ざすと、会議室の中は氷のような沈黙に包まれた。
決定は家主であるグレンがすべきことだった。
家臣たちはただ口を閉じているだけだった。
しばらくの沈黙の後、彼がゆっくりと口を開いた。
「まさか私が情けなくて君が出て行こうとしているなら、もう少しだけ時間をくれ。君の助けなしでやり遂げてみせる。」
「いえ。そんな意味ではありません。」
ナディアが彼の手を握りしめて、言葉を続けた。
「私が決着をつけたいからです。」
「……」
「私が清算すべき縁だと思うんです。」
「……」
「私の思う通りにさせてください、グレン。」
どうして「ダメだ」と言えるだろうか?
ナディアには、自分の望む道を選ぶ権利があった。
たとえ夫であるグレンであっても、彼女を止めることはできない。
彼女の安全を心配して理由を並べたとしてもだ。
しばらくの沈黙の後、グレンは視線を落とした。
仕方なく許可の言葉を引き出すしかなかった。
「私が止めようとしても…… 君は止まる人じゃないからな。」
「よくご存じですね。」
その言葉にナディアがおどけたように小さく笑った。
「つまり、許可してくれるってことですね?」
「はあ……」
グレンの口から深いため息が漏れた。
「代わりに、私が君のそばにいる。一定の距離は必ず保たなければならない。」
「もちろんです。私がまたフォローになるのは嫌ですから。」
ナディアの口元にふっと微笑が浮かんだ。
これがグレンとあの男との違いだった。
どんなに不安であっても、常にナディアの意思を優先するグレンの態度が、最終的にナディアの心を開かせたのだった。
自分の判断を優先するタクミとは異なり、グレンは彼女の判断を尊重できる人だった。
彼の手にそっと触れたナディアが席を立ち、言った。
侍女たちがいる方向だった。
「皆さん。さっきお聞きになった通り、私が囮の役割を担うことに決まりました。では、皆で具体的な計画を立てていきましょう。」
「公爵様のご健康は?」
「日に日に悪化しているそうです。主治医によると、回復は難しいかもしれないとのことです。」
「そうか?」
主君が意識を失っているという知らせを聞いた。
それでもタクミの表情は無表情だった。
公爵が健康を回復できないか、あるいはすでに勝機を失っていると感じているからだ。
それでも不思議なほど……不思議なほど何の考えも浮かばなかった。
なぜだろう?この世界で生き残ることが、彼の長年の願いではなかったのか?
時間が巻き戻ったと知ったからだろうか、頭の中が空っぽになったようだった。
何も考えたくなかった。
「……卿?タクミ卿?」
「ん?」
タクミは役人が体に触れてようやく正気を取り戻すことができた。
「さっきからずっと返事がないので……具合が悪いのですか?」
「いや、ただ……少し疲れているだけだ。」
一応取り繕ったが、実際にはその通りだった。
全身が重くてだるい。
彼は本当に疲れていた。
何もかもが疲れて仕方なかった。
「では少しだけでも目を閉じられますか?顔色がよくありません。」
「……そうするのがいいだろう。」
一晩ぐっすり寝れば、この空っぽな気持ちも消えるかもしれない。
彼が副官の勧めに従って室内に足を踏み入れようとした瞬間だった。
「うわっ、ウィンテル侯爵家の足跡が見えます!」
城壁の下から上がってきた兵士の叫び声が彼の足を止めた。
突然ウィンテル侯爵家の足跡が現れただと?
タクミは反射的に眉をひそめて尋ねた。
「それはどういう意味だ?詳しく話してみろ。」
「川の向こう側にウィンターフェル侯爵とその騎士たちが現れました。直接見に行かれるべきかと存じます。」
「侯爵本人が直接現れたのか?」
奇襲を仕掛けるつもりなのか?
敵陣のすぐ前に現れた意図が何であれ、彼が現れたというだけで、じっとしてはいられなかった。
彼はすぐに兵士たちを率いて城を出た。
城の近くの川岸へと近づいていくと、案の定、ウィンターフェル侯爵の騎馬軍がずらりと並んでいる姿が見えた。
そしてその下にウィンテル侯爵と推定される人物が立っていた。
銀髪であったため、さらに目立った。
「あの銀髪は……ウィンテル侯爵では?」
「隣にいるのはジスカール・ヴァンシュタイン卿のようですね。そしてその反対側は……まさか女性ですか?」
「女性?女性がなぜこんな場所に……」
他の者たちの会話に、タクミはさらに目を凝らして目を開け直した。
よく見ると、彼らの言う通り、長い栗色の髪を持つ人物が見えた。
体格からして明らかに女性だった。
「ウィンターフェル騎士団に女性騎士なんていたか?」
もしそうだったなら、覚えていないはずがない。
彼女の正体を推測しながら見ていたタクミの目が、衝撃を受けたように大きく見開かれた。
「……!」
長い褐色の髪。
そしてウィンターフェル侯爵の右側に立っているにふさわしい地位の女性。
思い浮かぶ答えはただひとつだった。
「まさか、ナディア?」
その瞬間、空っぽだったように感じていた胸に火が灯ったような感覚が走った。
喉の奥がきゅっと締めつけられるように感じた。
「まさか……ウィンテル侯爵の夫人じゃないでしょうね?」
しばらくして他の者たちも彼女の正体に気づいたのか、ナディアの名前が取り沙汰された。
「おかしいですね。自分の妻をなぜこんな場所に連れて来たんでしょう?」
「タクミ卿、どうなさいますか?追撃隊を送りましょうか?」
「………」
川の向こうを見つめるタクミの目が細められた。
追撃して追いつくには少し距離があった。
しかしだからといって敵陣に放置するわけにはいかない。
策を撤回するのに、傍観できないほどの焦りだった。
どうする?
彼が手綱を握ったまま深く悩んでいる間に、川の向こう側の敵は馬の頭を回していた。
「おっ!戻っていきます!」
「本当だ。戻っていっています。タクミ卿、今からでも追いかけるべきじゃないかと……」
「もう遅い。今追いかけたところで追いつけないだろう。動くな。」
それにしても、遠くにいた敵がすぐに外に出るのは一瞬の出来事だった。
空っぽの川辺を見ながら、人々は一人二人と疑問を投げかけ始めた。
「本当に行ってしまったんですね。一体どういう魂胆で我々の前に現れたのか……」
「もしかすると単なる偵察だったのかもしれません。」
「だとすれば、なぜ夫人を連れてきたのです?理解できません。」
「う、うーん。散歩がてら砦に行って、ちょっと風に当たりたいという妻の言葉を断れなかったとか?」
「まさか。公私の区別はきちんとする人だと思っていたのに。」
「……だけど……」
それ以外にもいくつかの仮説が浮かび上がったが、それらしい答えはなかった。
疑問がさらに深まるだけだった。
いや、正解を推測した者はいた。ただ口には出さなかっただけだ。
タクミは川の向こうを見つめながら眉間にしわを寄せた。
『俺を逃がそうってことか?』
だとすれば、きちんとした方法を見つけたということだ。
自分の弱点を見抜かれたという恐れと同時に、ウィンターフェル侯爵への警戒心もまた湧き上がってきた。
もし自分だったら、ナディアに決して囮(おとり)役を任せなかったはずだ。
彼女が危険な場所にいることを許すはずがない。
ナディアがいるべき場所は、安全な後方で十分だ。
どうして愛する人に危険を監視させるなんてことができるのか?
無意識に歯ぎしりをしていた彼に、副官が意見を求めた。
「タクミ卿、どうなさいますか?」
「……姿を消してしまった以上、今はどうしようもない。ひとまず戻る。」
「はい。」