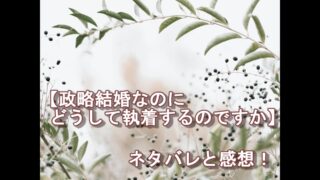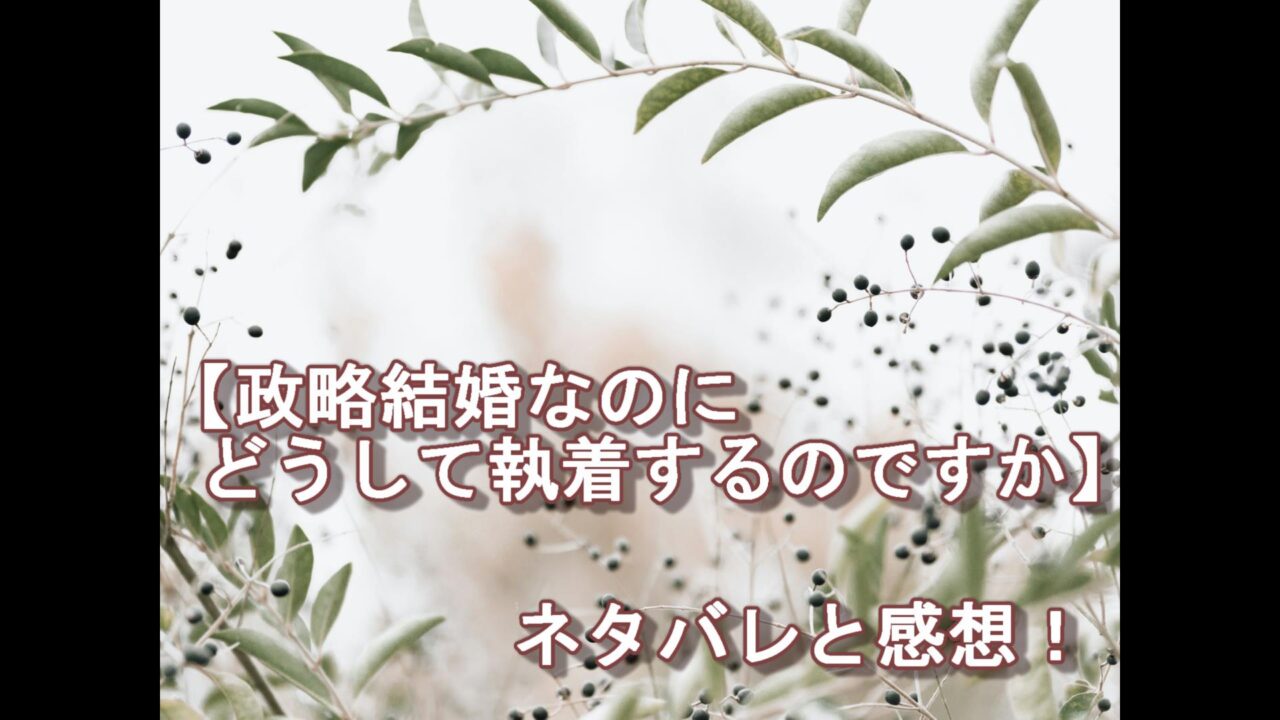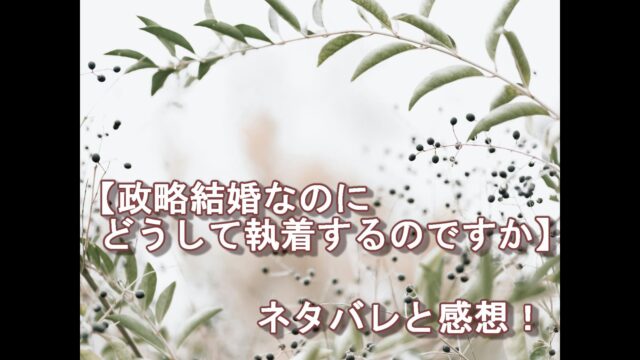こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

94話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 告白③
扉が閉まると同時に、グレンが口を開いた。
「すまない。」
「何がですか?」
「この問題を自分で解決すると豪語したせいで、こんな場を設けることになり……困難な状況に巻き込んでしまってすまない。」
「いえ、それに関しては。実際、先侯爵様の立場からすると当然のことでしたから。」
ナディアは軽く笑みを浮かべながら答えた。
実際のところ、彼女はアイザックがここまで忍耐強く振る舞ったこと自体、すでに大したものだと思っていた。
「彼の願い通りにして差し上げましょう。」
「なんだって?」
その言葉に、グレンの目が大きく見開かれた。
「別々の部屋を使うのが気に入らないのでしょう?それなら、時々寝室だけでも一緒に使ってみたらどうでしょう。時間は解決してくれるはずです。」
時間が経った後には……ナディアが侯爵の地位に残るのか、それとも別の貴族の若者が新たな後継者になるのか……。
侯爵夫人になるのか、それとも別の立場になるのか、いずれにせよ結論は出るだろう。
しかし、ナディアにはまだどの方向に進むべきなのか分からなかった。
「どう?」
「私としては構わないけど……本当に大丈夫?」
「この前も一緒に寝室を使ったことがあるでしょう?不便なら片方がソファで寝ればいいじゃないですか? 毎日というわけではなく、時々でいいんです……。」
言葉を続けていたナディアが言葉を詰まらせた。
瞬間的に、グレンから聞いた告白を思い出してしまったのだ。
軽く視線を落とした彼女を、グレンがまるで彼女を守るような眼差しで見つめているように感じられた。
「どうして言葉を止めるの?」
「あ……つまり、私が言いたいのは、毎日同じ寝室を使う必要があるわけじゃないし、それでもいいんじゃないかということです。」
首都へ向かう旅の途中、グレンと同じ寝室を使っても何事もなく快適に過ごせた。
他の家門の客間でも問題なく過ごせたのだから、ウィンターフェルでできない理由は何だろう?
「まあ……特に問題はないでしょう。」
グレンの告白が心に引っかかってはいたが、それが彼女に大きな影響を与えることはないだろうと思った。
すでに一度経験したことのある出来事だ。
そう、そう思っていたのに……。
「いざとなると……感じが違うな?」
手に握りしめた毛布に自然と力が入る。
目の前ではグレンがそわそわと布団を整えていた。
ベッドの左端に腰を下ろし、ナディアを見つめながら彼が尋ねた。
「具合が悪いのか?」
「あ、それが……」
ナディアが口ごもると、彼は立ち上がろうとしながら言った。
「やっぱり、見苦しいね。それなら私がソファに……」
「いいえ!最初に言ったことだけど、あなたにソファを内側に入れることはできない。」
彼女は言った通り、寝室の右端に座り込んだ。
寝具は広めで、旅行中に使った寝具よりも広く感じた。
その上で、彼女は寝心地の良い状態を維持していたのに、今まで以上に奇妙な感覚を抱いた……。
「それはやはり、心の内に抱えた不安のせいかな?」
一度、彼女はグレンを自分のパートナーと見ていたのだ。
彼女は吐息をついた。
一度死んだ経験はあっても、恋愛経験はないので、神経を使うことはなかった。
(私がしたことが今さら何になる?)
確実な自己責任の元に、彼女は判断した。
だが、少しでも不便さがあれば、少しは耐えなければならなかった。
目の前までのすべてを超えた彼女の姿に気づいた。
「おやすみ。」
「はい。」
グレンが協卓の上の蝋燭を消し、部屋には静寂が広がった。
‘やっぱり寒くなったな。’
何も見えなくなり、静かな考えを持つことができた。
彼女が目を閉じたまま自分を少し整えた。
‘私は今、広いベッドを使っている。自分の部屋のベッドを使っているときは……’
しかし、無駄な心配だった。
隣で布がこすれるような音が聞こえた瞬間、意識が鋭くなったからだ。
「……!」
閉じていた目が反射的にぱっと開いた。
窓の外から月明かりが差し込む中、寝室の様子がかすかに見える。
グレンの横顔も同様だ。
シルエットだけが見えるその横顔を一瞬見つめた後、ナディアは慌てて視線をそらした。
なぜか彼の鼻筋が非常に整っていると思ってしまったからだ。
『何を考えているの、早く寝よう。』
しかし、気持ちがざわざわした状態では眠ることなど到底できそうになかった。
時間が経つにつれ、むしろ頭が冴えていくばかりだった。
さらには、少し前に聞いたグレンの告白が、何度も耳元で繰り返されているようだった。
「そうさ、彼が君に愛を告白しているんだ。」
彼の声が思い出されればされるほど、わずかに残っていた眠気さえも完全に吹き飛んでしまう気分だった。
ナディアは少しでも眠りやすい姿勢を見つけるために、身をよじらせて体勢を変えようとしていた。
彼女がしきりに布団をもぞもぞさせているのを見て、グレンがゆっくりと口を開いた。
「眠れないのか?」
「あ、えっと……昼に少し昼寝をしてしまったから……」
もちろんそれは嘘だ。
昼寝などするはずがない。
すると、グレンが彼女の方に体を向けて言った。
「それならいっそのこと、眠れないついでに話でもしようか。」
「あなたも眠れないんですか?」
「ああ。」
「昼寝でもしました?」
「そうじゃない……好きな女性の隣に横たわっているから眠れないんだ。」
「……」
しばらくナディアは言葉を失った。
彼がこんなに率直に表現する人だったとは。
部屋の中が暗かったのは幸いだった。
そうでなければ、自分の顔が赤くなっているのがはっきりと見えてしまったはずだ。
彼女は少しすねたように答えた。
「てっきりいい加減な人だと思っていたけど、そうでもないんですね。」
「今は好き嫌いを言っている場合じゃないんだ。」
「……」
この人、本当に真剣なんだ。
ふとそう思った。
照れくさくなった彼女は、咳払いをして話題を変えた。
「別の話をしましょう。私と出会う前、どんなふうに生きていたのか……そう、子供時代のことを話してくれませんか?」
「……子供時代?」
彼の声に驚いた気配を隠せず、彼女は問いかけた。
少し言葉に詰まった彼が、やがて話を続けた。
「まあ、跡取り息子として徹底的に教育を受けて育ったから……君が興味を持つような話はあまりないと思うよ。」
「跡取り教育?」
「それなりに、普通のことだ。」
ナディアは、公爵家の跡継ぎとして育てられたエイデンの幼い頃を思い浮かべた。
厳格な教育と周囲の期待を一身に背負って育った子ども……思い当たるものがあった。
「もしかして、“ませてる”ってよく言われませんでしたか?」
「……正確だね。どうして分からるんだ?」
「知り合いの中に似ている人がいるんですよ。」
少年時代の彼がどんな姿だったのか、ぼんやりと思い浮かべるようだった。
今のような冷たい印象とは違い、ひたすら生意気だった子供。
子供っぽい話題に大人びた対応をしようとして、きっと周囲を驚かせていただろう。
「今よりずっと可愛かったでしょうね。」
「……今より?」
「ええ、今より。」
暗闇の中で、グレンの表情にわずかに微笑みが浮かんだ。
それはつまり、「今でも可愛い」と言いたいのだろうか?
褒め言葉なら褒め言葉ではあったが、グレンは笑うことができなかった。
『一体何が問題だったんだ?』
過去に男らしい魅力をアピールしようとした努力の記憶が脳裏をよぎる。
その必死な努力にもかかわらず、「可愛い」と言われるだけだとは。
彼は、どうにか作戦を変えるべきかもしれないと思い始めていた。
その時、ナディアの声が耳に届いてきた。
「では、私も自分の幼い頃の話をしてあげます。」
ナディアはグレンについてもっと詳しく知りたいと思っていた。
そして、それもまた同じだった。