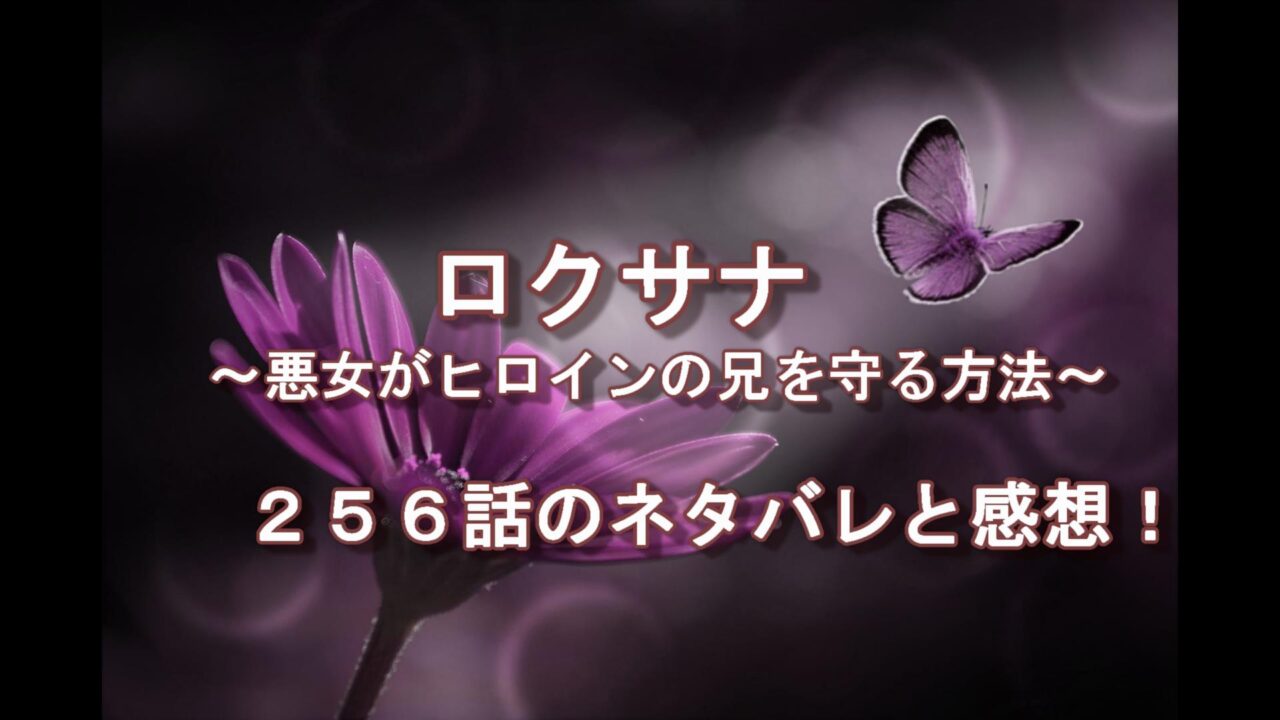こんにちは、ピッコです。
「ロクサナ〜悪女がヒロインの兄を守る方法〜」を紹介させていただきます。
今回は256話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

どういう訳か小説の中の悪の一族、アグリチェ一家の娘「ロクサナ」に生まれ変わっていた!
アグリチェは人殺しをものともしない残虐非道な一族で、ロクサナもまたその一族の一人。
そして物語は、ロクサナの父「ラント」がある男を拉致してきた場面から始まる。
その拉致されてきた男は、アグリチェ一族とは対極のぺデリアン一族のプリンス「カシス」だった。
アグリチェ一族の誰もがカシスを殺そうとする中、ロクサナだけは唯一家族を騙してでも必死に救おうとする。
最初はロクサナを警戒していたカシスも徐々に心を開き始め…。
ロクサナ・アグリチェ:本作の主人公。
シルビア・ペデリアン:小説のヒロイン。
カシス・ペデリアン:シルビアの兄。
ラント・アグリチェ:ロクサナの父親。
アシル・アグリチェ:ロクサナの4つ上の兄。故人。
ジェレミー・アグリチェ:ロクサナの腹違いの弟。
シャーロット・アグリチェ:ロクサナの妹。
デオン・アグリチェ:ロクサナの兄。ラントが最も期待を寄せている男。
シエラ・アグリチェ:ロクサナの母親
マリア・アグリチェ:ラントの3番目の妻。デオンの母親。
エミリー:ロクサナの専属メイド。
グリジェルダ・アグリチェ:ロクサナの腹違いの姉。
ポンタイン・アグリチェ:ラントの長男。
リュザーク・ガストロ:ガストロ家の後継者。
ノエル・ベルティウム:ベルティウム家の後継者

256話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- もう一つの夢と死の始まり②
その時、ロクサナはグリゼルダの隠れ家に滞在していた。
そうするうちに蝶から信号が来た瞬間、ロクサナの目つきがドキッとする。
彼女は静かに毒蝶と時刻を共有した。
明らかにデオンの部屋にいるのはカシスだった。
ロクサナはデオンのことを彼に話したことがない。
カシスはすぐベルティウムに行き、その直前にもそれぞれの家門のことに気を使うのに忙しくて対話をしたり焦げ付く暇がなかったから当然だ。
だが、今カシスは明らかにデオンがいるシエラの邸宅にいた。
それも密かに入って、デオンと向き合っているところだった。
毒蝶の目を通してカシスの手がデオンに伸びる光景が見えた。
「もしかして殺そうとしているのではないか?」という考えは最初からしていない。
口クサナが知っているカシスは、そのようなことをする人ではないためだ。
そしてやっばり・・・。
その後の彼の行動を見て、ロクサナは膝の上に置いた手をそっと握ってしまった。
彼女の息づかいはさらに小さくなる。
ついにカシスがデオンから手を離して振り向く前、一瞬目が合った。
カシスはロクサナが部屋に置いた毒蝶を一度凝視した後、その場を離れる。
口クサナは蝶とのつながりを断ち切った後もしばらくじっと座っていた。
彼女の視線はニックスのいる部屋のドアに移る。
最後の瞬間、彼女と時刻を共有した毒蝶に向かったカシスの視線が何を意味するのか、なんとなく分かるような気がした。
しばらくして、ついにロクサナが席から立ち上がった。
「ちょっと出かけてくるね」
「私も一緒に行くよ」
ジェレミーは目的地を聞かずに彼女の後をさりげなく続いた。
グリゼルダは、「そうしようがしまいが関係ない」というような堅苦しい態度で手を振る。
ロクサナとジェレミーがここにいる間に覚醒剤も落ち、結局グリゼルダは仕方なく睡魔の誘惑に負けてしまった。
仮眠だったが、それでも時々睡眠を取った彼女は、前よりはっきりと顔色が良くなっている。
ロクサナとジェレミーはグリゼルダを後にして、一緒にシエラの家に向かった。
「あ、何だ。マリアおばさんもここにいたの?」
「あら、今日はジェレミーも一緒に来たのね」
マリアは目的地に到着し、ドアを開けて中に入るとすぐに彼らを迎えた。
彼女がここにいるとは知らなかったジェレミーは怯えた表情をする。
彼は本当にシエラがいるところを見つけたマリアの執念に改めて驚いてしまった。
「サナ、お帰りなさい」
マリアの隣にいたシエラもロクサナを迎えてくれた。
中にいた人々の反応を見ると、少し前にここにカシスが訪れた事実は誰も知らないようだ。
ロクサナはまっすぐに歩いた。
「今日も入ってみようと思ってるの?」
彼女の足が向かうところを見たシエラは静かに口を開いた。
「午前中に医者が訪れて、患者の状態がだんだん悪くなっていると言ったわ」
そう言うシエラの声は淡々とした感じがするほど単調で、そこにはそれとなく肌寒い気配も滲んでいる。
しかし、彼女の表情はどこか妙に沈んでいた。
隣にいたマリアも、そんなシエラを見て心配そうな顔をした。
ただ、それは息子のデオンヘの感情なのか、やせ衰えたシエラヘの感情なのか不明だった。
「大丈夫です」
ロクサナはドアノブに手を当てて首をかしげた。
そして、自分を見つめる人々に向かって話した。
「今日は目覚めるはずだから」
他の人たちには意味の分からない確信。
しかし、そこにはなぜか奇異な信頼が伝わった。
口クサナは再び首を前に向けた後、手に握られた取っ手をつかんで回した。
すぐにカシスの元気がかすかに残った部屋のドアが開かれた。
デオンはまだ深淵をさまよっていた。
赤い蝶の群れに破片一片が残らないほど全身を全部裂かれて死んでしまい、再び生き返って同じことを数え切れないほと繰り返した。
その始まりと終わりにはいつもロクサナがいた。
デオンは隠さずに彼の前で涙を流している15人の少女を眺めて、不可抗力的に手を伸ばす。
これまでロクサナがその手先に触れたことは一度もなかった。
しかし驚いたことに・・・。
今度は彼の手が向かい合った少女の涙に触れる。
体温の低い冷たい指先に暖かい温もりが染み込んだ。
その瞬間、泣いていた少女が若い女性に変貌した。
同じように大人になったデオンは黙って彼女を見つめた。
いつの間にか彼は見慣れないようで、見慣れた部屋の中に横たわっていた。
窓際にかかったカーテンが揺れる。
デオンはゆっくりと瞼を下げ、持ち上げを繰り返した。
視界からかすかな光が漏れる。
どういうわけか指一本動かすことができなかったが、そもそも動きたくなかったので関係ない。
実際のような感覚だったが、それにしてもこれもやはり夢の延長だろう。
そうでなければ、目の前にロクサナがいるはずがなかったからだ。
「おはよう」
案の定、いつものように冷たい目で彼を見下ろしていたロクサナが唇を離して温度の低い声を吐いた。
「勝手に死のうとするなんて」
たとえそうだとしても、これが新しい種類の夢であることは明白だ。
過去ではなく未来の場面だなんて。
耳に流れ込んだ言葉から推測した時、今の時点は夕焼けが沈んでいたその平原でロクサナの毒蝶に飲み込まれた以後であることが明らかだった。
では、ここは天国なのか?
いや・・・そんなはずがなかった。
自分が天国のようなところに行けるはずがなかった。
むしろ地獄に落ちて永遠に終わらない幻覚の沼に陥っているのならまだしも。
「私がまだ許していないのに、あなたがどうして勝手に死のうとするの?」
それなら、これは本当に現実のような虚像だ。
耳元に絡む声も、視野に宿る顔も、すべて本物のように生き生きとしている。
それで、デオンは思わず低い笑い声を上げてしまった。
枕元に座っていたロクサナは、そんな彼を黙って見つめる。
日に砕ける金色の髪。
静かな赤い瞳。
鼻先に巻くほのかな香り。
開いた窓から入ってくる微温な風までも。
夢、あるいは幻覚であることを立証するかのように、ひどく温かく穏やかな風景だった。
しかし、デオンの考えとは違って、これは夢ではなかった。
ロクサナはベッドに横たわっているデオンを見下ろす。
今の彼は、子供の手振り一度でも簡単に殺せるかのように無力に見えた。
今にも死にそうだった状態から抜け出していたが、それでもまだ彼の体は完全に回復したわけではない。
そのせいか、デオンは今もじっと横になって目を閉じて開けることだけが精一杯のようだった。
デオンの口元に見えるようで見えないようにかすかに通り過ぎた見慣れない笑みが、先日のことを思い出させる。
あの時、明らかにデオンは彼女の蝶の群れに包まれて笑っていた。
「デオン・アグリチェ」
しばらくして、なんとなく遥かに感じられる声が再びデオンの耳元に響く。
そして、ついに鼓膜に食い込んだささやきが、デオンの心臓の深いところまで貫通して通り過ぎた。
「私はあなたが死ぬ時、一滴の涙も流さない」
記憶の中に残っていた過去の残滓が深い水面下から浮かんだのはその時だった。
「デオン、あなたが本当に望んでいることが何なのか私が分からないと思った?」
ロクサナがアグリチェでカシス・ペデリアンを出して過ごしたあの夜のことが記憶の彼方をよぎる。
「デオン。今まであなたの中に入っていた考えが何か私が当ててみようか?」
穏やかな声が日光に混じって空気中に溶け込んだ。
「あなたは本当は知っていることを羨ましがっていた」
しかし、一見穏やかに感じられるその低い声は、熊手のように鋭くデオンの中をかき分ける。
むしろ彼をあざ笑うための辛辣な口調だったなら良かっただろうか?
これは以前ロクサナの母親シエラが彼の前で勇敢に話していたよりもひどいうわごとだった。
「あなたが持っていないものを、彼は持っているから。それにもかかわらず本当に理解できないことに・・・」
「・・・」
デオンはその発言に反論できなかった。
そんな彼を見て、口クサナがため息をつくように笑う。
「的を射たような顔ね」
どういうわけか、誰かが心臓をぎゅっと握っているような感覚が一瞬彼をよぎった。
「あなたが私のそばにいたかった理由が何なのか分かる」
静かな声がデオンの上に落ちた。
以前もそうだったように、今回も彼女は彼さえも知らないことを知っていると言った。
「それは多分私があなたをそばに置いた理由と同じだろう」
しかし、デオンはその言葉に納得できず、ぎくりとした目つきをしてしまった。
「言ったじゃない。あなたと私は似ている部分があるかも知れないと」
口クサナは今彼に何を言っているのだろう?
彼女がデオンをそばに置いた理由は、きっと近くで彼に復讐するためだろう。
デオンはそれを知っていながら、ロクサナの手に直接自分の首輪を握らせた。
しかし、デオンがそのような選択をしたのは、ロクサナをそばで虐めたいからではない。
では、何の理由でかと聞かれたら・・・。
それもやはり明快に答えることはできなかったが。
それでも明らかにベールの向こうに存在する2人の本音が同じではないと思った。
だが、続いてロクサナの目に向き合う瞬間、ずっと凍っていたデオンの心臓に低い波紋が起き始める。
まるでアグリチェで過ごした最後の夜のような。
まるであの時のようにロクサナはデオンを前にしても棘だらけの言葉を吐き出さずに静かな顔で彼に向き合った。
しかし、彼女の目には自分に向けられた自嘲と冷笑が薄く滲んでいる。
これまで誰にもこのような話をしたことがなかった。
まず、ロクサナ自身も自分の根底にある心を認めたくなかったからだ。
デオン・アグリチェのことを考えると、軽蔑と憎悪心、そして嫌悪感が習慣のように一番先に押し寄せてくる。
しかし、その後は波が引いたところに残り、がさがさする砂粒のように、矛盾した感情が胸の中で当てもなくぐるぐる回った。
『あの人と君の関係はどこか奇妙だ』
いつかカシスが彼女に言ったことは間違っていなかった。
明らかにデオン・アグリチェはロクサナにとって思ったほど単純な存在ではない。
幼い頃からデオンがとても憎くて、できればこの手で彼を殺してしまいたいと思ったことも多かった。
最初は確かにそのように始めた。
しかし、実はそれが全てではない。
ロクサナは自分の弱さを初めて告白し、これ以上否定できなくなった。
(結局は一人になりたくなかったんだ。あなたも、私も)
実におかしくて情けない理由。
アグリチェに住んでいる間、彼女は一瞬も怖くなかったことがなかった。
でも、心を開いて頼れる人も、信じて頼れる人も誰もいなくて、彼女はいつも一人でなければならなかった。
自ら強くならなければ生き残れなかった。
それで一人でドアを閉めて泣いていた夜を忘れたように、夜が明けたらまた平気なふりをして人々の前で笑った。
休むところもないアグリチェの邸宅は、真夏にも肌が凍りつくようにこの上なく寒く感じられた。
デオン・アグリチェはいつからかそんな彼女の後ろに影のように立っていた男。
もうずいぶん前から彼とは家族も友逹もなれない関係だった。
しかし、ロクサナはそんな彼を見て、他の誰からも感じたことのない確信を一つ持つことができた。
この人は、きっと自分が死ぬ瞬間までいつもここにいるだろう。
生きてきて、それがうんざりする時も数えきれないほどあった。
それでも地獄のようなアグリチェで時々耐え難いほど息詰まる孤独感にあえぐ時には、そのうんざりする視線さえ慰めになる時があった。
分かっている、これはひどい矛盾だと。
その当時、ロクサナには永遠の味方と言える人が誰もいなかったが、永遠の敵と呼べる人は存在した。
とはいえ、アシルを殺したデオンを受け入れたわけではない。
心を開いて彼を自分の人のように思って頼ったわけでもなかった。
それでも・・・少なくとも彼がいる限りは死ぬ日までこの寒い所に一人になることはないだろうと、そんな考えをしていた。
(よりによって寂しさを解消する相手としてお互いを選んだというのが、あなたと私が愚かな人間だという証拠だろう)
そして、ロクサナはデオンも自分と似た感情を抱いていたことを知っていた。
このばかげた男はまだそれを知らないようだったが。
「デオン。私はあなたを憎んでいる」
彼に対する感情には依然として変わりがなかった。
しかし、育っていた。
そこにはいつからか他の何かが一緒に。
「私の兄を殺したあなたを、もしかしたら私は死ぬ瞬間まで許せないかも知れない」
デオンは彼女の思い通り、ロクサナの言葉を完全に理解できず混乱していた。
ただ、今ロクサナが言った言葉だけはデオンにとって今更のようなことはない内容だ。
そもそも彼はロクサナの許しを願ったこともない。
むしろ、永遠に消えない憎悪でも彼女の中に残ることができれば、デオンはむしろそれを喜ぶだろう。
しかし、ロクサナの話を聞いている間、ほんの少し。
なんだかほんの少し、心が痛くなった。
彼女の低い声はガラスの破片になって彼を刺すようだった。
「だからデオン、あなたはまだ死んではいけない」
今やデオンはこれが夢でも幻想でもないという事実が分かるような気がした。
これほど鮮やかな痛みが夢であるはずがない。
それに導き出された結論は明確だった。
結局、デオンはあの日、ロクサナの手によって死ななかったのだ。
そして彼女はまた彼に首輪をつけて目立たない所に放置する考えであることは明らかだった。
デオンが彼女の視野の外で一人で死ぬまで。
そう思うと、胸の中に埋まっていたものが、手に持った砂粒のように速いスピードで流れ出した。
最初からそこに留まっていた虚しさが押し寄せてきた。
しかし、次の瞬間、彼の鼓膜を刺したのは予想とは違う言葉だった。
「このまま代価も払わずに私の手に死ぬとは。それだけ厚かましい話がどこにあるの?」
デオンは無意識のうちに息を殺す。
そして続くロクサナの言葉に耳を傾けた。
「あなたはまだ私に何も与えていない」
向き合った瞳がまだ冷えていた。
「だからまだあなたは死ぬ資格がない」
彼女の声はその目つきと同じくらい冷たかった。
「私が・・・」
しかし。デオンにその言葉はそばにいてもいいという許諾として受けいれた。
「もういらないと言っていなかったのか?」
ロクサナの目つきがほんの少し変わる。
その中には、デオンとしては簡単には計り知れない感情が込められていた。
それをどこかで見たような気がするとぼんやりと思っていて・・・デオンはその目つきがシエラのものと似ているという事実に気づく。
「今までのところ、アグリチェにはいらない」
ロクサナも結局、彼らに最も馴染みのあるアグリチェのやり方で話した。
「しかし、これからのあなたなら、まだ分からない」
またもや声が遠くなる。
「だから、もう少し生きなさい」
「・・・」
「君が今より殺す価値がある人になったら、その時は私の手であなたを終わらせてあげる」
まぶたの間に結ばれたロクサナの姿が徐々に遠ざかった。
散開する光の中で、ついに視界に映ったすべてのものが真っ白に壊れた。
それらすべてが眩しかった。
遠い光の中に沈み、デオンは目を閉じる。
すぐに真っ白な闇が彼を抱きしめた。
しかし、今まで見たような夢は二度と訪れなかったので、デオンはとても長い間静かに眠ることができた。
ロクサナとデオンの奇妙な依存関係。
これからのデオンの行動次第では、その関係も変わるのでしょうか?




https://recommended.tsubasa-cham.com/matome/