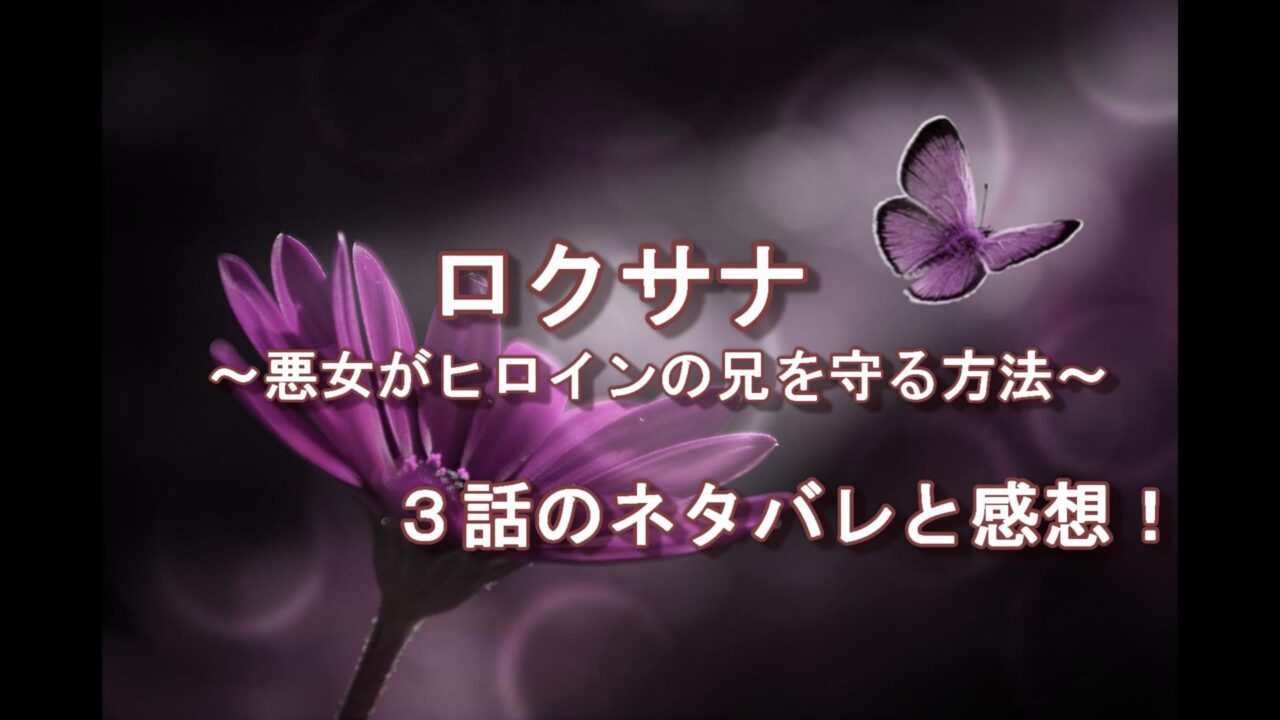こんにちは、ピッコです。
「ロクサナ〜悪女がヒロインの兄を守る方法〜」を紹介させていただきます。
今回は3話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

どういう訳か小説の中の悪の一族、アグリチェ一家の娘「ロクサナ」に生まれ変わっていた!
アグリチェは人殺しをものともしない残虐非道な一族で、ロクサナもまたその一族の一人。
そして物語は、ロクサナの父「ラント」がある男を拉致してきた場面から始まる。
その拉致されてきた男は、アグリチェ一族とは対極のぺデリアン一族のプリンス「カシス」だった。
アグリチェ一族の誰もがカシスを殺そうとする中、ロクサナだけは唯一家族を騙してでも必死に救おうとする。
最初はロクサナを警戒していたカシスも徐々に心を開き始め…。
ロクサナ・アグリチェ:本作の主人公。
シルビア・ペデリアン:小説のヒロイン。
カシス・ペデリアン:シルビアの兄。
ラント・アグリチェ:ロクサナの父親。
アシル・アグリチェ:ロクサナの4つ上の兄。故人。
ジェレミー・アグリチェ:ロクサナの腹違いの弟。
シャーロット・アグリチェ:ロクサナの妹。
デオン・アグリチェ:ロクサナの兄。ラントが最も期待を寄せている男。
シエラ・アグリチェ:ロクサナの母親
マリア・アグリチェ:ラントの3番目の妻。デオンの母親。
エミリー:ロクサナの専属メイド。
グリジェルダ・アグリチェ:ロクサナの腹違いの姉。
ポンタイン・アグリチェ:ラントの長男。
リュザーク・ガストロ:ガストロ家の後継者。
ノエル・ベルティウム:ベルティウム家の後継者

3話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 奈落の花
部屋に戻った私は気分が地下に閉じ込められて、あまり良くなかった。
あの少年が、カシス・ぺデリアンたという事実を本人のロから聞いて私が気分が良いはずがない。
直接確認したので、この危機をどう克服するか。
私はとうしてよりによってこんな答えのない悪役家門に生まれたのだろうか。
私がなぜあの少年のことをここまで気にかけているのか説明するには、この本の内容を先に話さざるを得ない。
アグリチェと私の未来が書かれていたのも、まさにその本だから。
過去の人生で交通事故で死ぬ前に、私はあるロマンス小説を読んだことがある。
卒業論文のために忙しい前、同じ学科の友違が最近人気のある本だと推薦してくれたのがきっかけだった。
もともと私はロマンス小説を読む趣味がない。
ところが、その時は特に暇で退屈だった時期だったので、友人が貸してくれた本を一度読んでみることにしたのだ。
タイトルは「奈落の花」
そう、タイトルから分かると思うが、これは疲弊ロマンス小説だった。
ページをめくるほど、私はこの本を投げたいという気持ちを感じなければならなかった。
なぜなら、これは女主人公のシルビアが他の男主人公たちと濃厚な拉致監禁ロマンスを撮る18禁ハーレム小説だったため。
この本の背景はかなり独特だった。
大まかに青、白、赤、黄、黒の5家がこの世界を支配するが、女主人公認のシルビアが属した家門は「青のぺデリアン」
物語はヒロインの少女時代から始まる。
シルビアは青みがかった神秘的な銀髪と日差しのようなきらびやかな金色の瞳を持った美しく愛らしい少女。
彼女は裕福で仲睦まじい家庭に生まれ、不自由なく愛され育った人だった。
彼女には兄が一人いたが、兄妹間の友愛もとても深い。
普通、兄妹同士は仲が良くない場合がほとんどだが、この小説の中の女主人公の兄妹は全くそうではなかった。
ちょっとオーパーに言えば、この2人は相手が望むなら、肝臓でも胆嚢でも全部抜いてあげられるほど、お互いをとても大切にし、愛する兄妹だった。
う一ん、正直私はこれを見て「やっばりフィクションだね」と言って鼻で笑ったが。
とにかくヒロインの悲劇は、まさにその大切な兄がある日突然失踪して始まる。
当時、ヒロインの年齢は15歳、兄の年齢は17歳。
そう、すでに察しているだろうが、まさにその拉致された女主人公の兄が今私の家の地下に閉じ込められているカシス・ペデリアンだ。
彼は支配階層家の一つであるぺデリアンの後継者として早くから「青の貴公子」と呼ばれ、家の公務に参加していた。
その日、カシスは境界付近で感知された不穏な動きを確認するために道を出た後、そのまま敵に捕まることに。
当然、ヒロインとその家族はカシスを探すために血眼になった。
心当たりはあった。
まさに「青のぺデリアン」と以前から争っていた「黒のアグリチェ」だった。
剥いても剥いても中が真っ黒だったので、よりによって名前も黒のアグリチェだという。
私の家門に本当によく似合う名前と言わざるを得なかった。
正義を守護するぺデリアンと卑劣なことをするアグリチェは、以前から仲が良いはずがなかった。
その上、その頃、ぺデリアンの首長とアグリチェの首長は大きく争ったことがある。
それでシルビアの家族たちはカシスを連れて行ったのがアグリチェだろうと思った。
それは正解だった。
しかし、心証があるだけで、物証が出てこない。
黒のアグリチェも青のぺデリアンと同等の位置であるため、心証だけでは簡単に動くことができなかった。
それでも手放すわけにはいかず、アグリチェに密かにスパイを隠して送り込んだりもしたが、死体になって帰ってくるだけ。
そうして3年の時が過ぎた。
もちろんシルビアはその時まで兄を探すことを諦めなかった。
18歳になったシルビアは兄の行方を直接追跡することに。
ところでこの小説が訳もなく18禁ハーレム小説ではないから・・・。
シルビアが情報を得るために向かったところは他の白、赤、黄の家門だったが、そこにいる男性主人公たちが非常に狂ったことだった。
私が見た時は、本当にみんな正気ではなかった。
ヒロインに惚れて拉致と監禁のロマンス。
私はこの本を全部見て、本当に変人たちのたまり場だと思った。
さらに、「黒のアグリチェ」でもシルビアに惚れる変人が出てくる。
シルビアはこの虎に拉致されることになる。
ある意味、そのおかげで今まであれほど足を踏み入れたいと思っていた敵の巣窟に、力を使わずに簡単に慢入したわけだ。
そして彼女はまさにこのアグリチェで兄のカシスが無残に死んだという事実を知ることになる。
その後シルビアは黒化して彼女に惚れた他の白、赤、貴の男衆と仲良く手をつないでアグリチェを破滅させる。
それから彼らは逆ハーレムを構成して幸せに暮らしました・・・、だったら小説の偽名が泣くよ。
結局、ヒロインのシルビアが他の男性主人公たちのおもちゃになって鳥かごの中に閉じ込められて暮らすというのがまさにこの「奈落の花」のあらすじ。
ちくしょう、シルビアもシルビアだが、この小説でアグリチェはまさにすっかり滅びてしまった。
ぺデリアンの怒りは素晴らしく、彼らはアグリッチェを種も残さず皆殺しにした。
他の家門の男性も自分たちが好きなシルビアを助け、アグリチェを殲滅するのに先頭に立つ。
もう一つ言えば、今私が転生したロクサナ・アグリチェもこの小説の裏役だった。
どんな役なのか気になるって?
ある意味かなり陳腐なキャラクターだと言えるが・・・。
父親の命令で女主人公のシルビアの男たちを誘惑しようとして失敗した後、アグリチェの大虐殺の日に一緒に無惨に死ぬキャラクターだった。
アグリチェの一員という理由だけで殺すなんて。
実際に私がアグリチェに属してからは、ちょっと悔しい連帯責任にならざるを得なかった。
しかし、実はこの家は機会がある時に根こそぎ取ってしまうのが正しい。
私が生きてみると、この家にいる人たちは皆、少なくとも一部分ずつは正常ではなかった。
この減びる家門は、まともな人も狂わせるオ能がある。
これに適応できなければ結末はたった一つだけ。
廃棄処分。
私の兄だったアシルのように不良品として扱われ死んでしまうのだ。
しばらくアシルが処刑された日のことを思い出した。
私だからといって、ただ家の隅から逃げようか、という考えをしなかったわけではない。
しかし、いくらアグリチェの有望株である私だとしても恐ろしい人間が並んでいる中で避けて隠れる自信はなかった。
その時、ドアをたたく音が耳元に響いた。
「ロクサナお嬢さん。エミリーです」
「お入りなさい」
すぐにドアが開き、無表情な顔の女性が私の部屋に入ってきた。
彼女は私の腹心で、毎日この時間になると私を訪ねてくる。
エミリーの手にはトレーが握られていた。
その中にはコップと二つ折りになった白い紙が入っている。
「報告しなさい」
「ネタリウム耐性化の5段階に入り、今日から服用量を0.2ペロン増やしました。致死量の4.7ペロンに達したレベルで、前の段階にはなかった腹部の痛みや一時的な麻庫、吐血などの副作用が考えられます」
私は薬包紙を手に取り,その中にある白い粉をコップに注ぐ。
他人の耳には説明が多少殺伐に聞こえるかも知れないが、この程度は仕事でもなかった。
アグリチェの人なら雛でも耐性化のために幼い時から少しずつ毒を服用する。
各自の体に合わせて適応できる量だけ綴密に測って摂取するため、この過程で死ぬことはなかった。
だから、今私が服用した量が一般的な致死量だとしても、実際に死亡することもない。
私は以前に基礎耐性化作業を終えたが、今は個人的な理由で毒を摂取していた。
「ジェレミーは今何をしているの?」
「お部屋にいらっしゃいます」
エミリーが再びお盆を持って出かける前に通り過ぎるときに尋ねると、すぐに返事が聞こえてきた。
ジェレミーはシャーロットと一緒にカシス・ぺデリアンを欲しがった異母弟だ。
昨日から時々状況を把握しているが、私の考えではそろそろ私を訪ねて時になったようだ。
「姉ちゃん!」
エミリーがドアを開けるやいなや雄叫びが聞こえた。
ジェレミーはエミリーを押しのけて部屋に入ってくる。
黒髪に青い目をしたかわいい少年の顔が覗界に映った。
彼は小説の中でヒロインをアグリチェに拉致し、家門を苦しめた悪役サブ男、ジェレミーだった。
「姉ちゃん、いつ部屋に来たの?私がさっきも訪ねて来たのに・・・」
ジェレミーは愚痴をこぽしながら歩いてきて、ふと気づいたかのように振り返った。
「何だよ、お前はどうしてまだぽんやり立っているんだ?早く消えないのか?」
私に向かう時と全く違う冷たい目つきと話し方。
しかし。エミリーはまだ玄関先に立っている。
部屋に勝手に入ってきたのは自分でありながらエミリーを邪魔者扱いしているようだった。
彼は彼女の存在に非常に神経質な様子だ。
しかし、エミリーは私の眷属。
彼女はジェレミーの話を聞いてすぐに部屋を出る代わりに私を見た。
許可なしに部屋に入ってきたジェレミーを追い出すか、それともそのままにするか、意見を求める目つきで。
「エミリー、出てちょうだい」
私が話してから彼女は静かに挨拶し、ドアを出た。
ジェレミーの悲しそうな目つきがエミリーの後ろ姿に触れる。
もちろん、私の人を思いのままに触ることはないが、エミリーの態度にやや気が荒くなったようだ。
「ジェレミー」
ドアが完全に閉まり、私はちょっとした迷惑を感じて彼を呼ぶ。
「こっちにおいで」
もちろん、そのような感情を表には出さなかった。
とにかく、私はこいつに優しい姉だったから。
ジェレミーは私の呼び声に勝てないふりをしてドアから覗線をそらし、私に近づく。
私は彼に手を差し出した。
「さっき来た時、部屋が空いてたけど。どこに行ってたの?」
ジェレミーはその手を握って躊躇なく私の足元に座り込んだ。
そうしながら私の足に顔をもたせる姿が、まるで主人に尻尾を振る犬のようだった。
ジェレミーがエミリーを早く追い出そうとしたのも理解できる。
他の人にこんな姿を見せることはできなかったから。
彼はさっき私を訪ねてきた時、会えずに無駄骨を折ったのが相当残念だったのか、少しむっとした顔をしていた。
私はジェレミーの質問に動じずに言った。
「孵化室に」
「毒蝶の孵化室?」
「ええ」
実は、地下牢にいるカシス・ぺデリアンを見に行ったのだが、そんなことは言わなかった。
ジェレミーは私が言ったことを素直に信じているかのように眉をひそめる。
「本当に孵化させるの?」
「最後の一つが残った卵だから、今度は成功させないと」
「私はただこの前のように死んでほしいんだけど」
「苦労して得たのに成果がないと残念じゃない」
しかしジェレミーはずっと気に入らないようだった。
私は彼が今私のことを心配してくれていることを知って、少し寛大になる。
小説の中でのジェレミーは、ヒロインに魅せられ、家門の秘密と恥部をさらさらと吹き飛ばした、少し間抜けな悪役キャラクターだ。
しかし、まだ幼いためか、このように見ればかなり可愛いところがあった。
性格が少し汚くはあるが、アグリチェでは普遍的な水準である上、私にだけはおとなしい。
「今回父が持ってきたおもちゃね」
私の膝を枕にして甘えていたジェレミーがふと思い出したかのようにカシス・ぺデリアンの話を切り出す。
「私たちに接近もさせないのを見ると、普通のやつではないようだが、いったい誰だろう?」
「さあ」
すでに知ってはいたが、やはり彼は地下にある新しいおもちゃにかなり興味があるようだった。
「ただ者ではないような気がするわね」
ジェレミーの体は一瞬、通りすがりの言葉でぎくりとした。
「何だよ、姉ちゃんも興味あるの?」
すぐに彼が私の足にうずくまっていた顔を上げる。
先ほどの私の反応から何かを機敏に捉えたようだった。
「ねえ、今まで一度もおもちゃに興昧を持ったことなかったじゃないか」
ジェレミーは私をじっと見た。
真っ青な瞳が私の顔を見つめている。
「うん、でも今回はちょっと面白そうで」
私は喜んで彼の反応に応えた。
ジェレミーは私の穏やかな笑顔を見て目を細めた。
「ふーん、そうなの?」
しばらく何かを考えているようだった彼が、すぐにまた私の足の上にあごを当てて私を見上げた。
「じゃあ、私は姉ちゃんに譲るよ」
ジェレミーが一度目をつけた獲物を譲るのは大変なことだった。
しかし、私は彼がこう言うことをすでに知っていた。
そっと私を見上げる瞳にはかすかな期待感がこもっていたから。
これは「私、優しいでしょ?旱く褒めてくれ!」という意味だ。
ジェレミーの頭を撫でた。
するとジェレミーが満腹の獣のように満腹感のある顔をして私の手に頭をこすった。
うなり声を出す姿はまるで猫のようだ。
こいつが猛獣であることを忘れてはならない。
しかし、こうして私にしがみついて愛情を渇望する姿を見ると、なんだかんだと言ってもまだ十五歳の子供であった。
私は昔からジェレミーが何を望んでいるのか知っていて、喜んで彼の望み通りにする。
私の手を受けているジェレミーは満足そうだった。
私もあなたが私の思い通りに動いて嬉しい。
私は彼を慰める優しい手とは裏腹に、少し乾燥した面持ちでそう思った。




https://recommended.tsubasa-cham.com/matome/