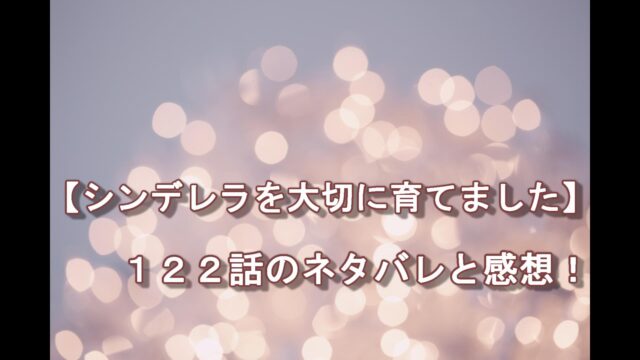こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

172話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 3姉妹の悩み②
「物語の中で妖精が美男子を誘惑して自分の国に連れて行くでしょう?」
リリーの言葉にダニエルは片方の眉を上げた。
「それがどうしたの?」という彼の態度に、アイリスとアシュリーは思わずお互いの手を握った。
「お母様を妖精の国に連れて行くつもりではないですよね?」
「はあ。」
そこでようやくダニエルは、子どもたちが緊張した表情をしながら自分を探しに来た理由を理解した。
何でもないふりをしていたが、少し緊張していた彼の顔に、ふと安堵したような表情が浮かんだ。
彼は妖精だからといってミルドレッドとの関係に反対することはないと思っていた。
子どもたちの反対を無視することもできるが、ミルドレッドはそうするわけにはいかなかったのだ。
彼女は子どもたちが二人の関係を反対するなら、それは困ると思った。
「違いますけど。」
ダニエルは緊張がほぐれた後、椅子に身を預けながら答えた。
しかし、表情と言葉のトーンが相変わらず冷静だったため、子どもたちは彼が緊張しているのか、緊張が解けたのかを見分けることができなかった。
「じゃあ……お母様を誘惑したのではないのですか?」
場の雰囲気が少し和らぐと、アシュリーが勇気を出して口を開いた。
「誘惑って?」
ダニエルは片眉を上げ、アシュリーをじっと見つめる。
その表情だけで、アシュリーの勇気は一気にしぼんでしまった。
「誘惑したのは確かだよ。」
そうだ、かなりのものだ。
ダニエルが生きてきた中でこれほど情熱的に誰かを誘惑したことがあっただろうか?
いや、考えてみると、ダニエルは誰かを本気で誘惑したことなどなかった。
誰かを誘惑したのは初めてだった。
彼はただそこに立っているだけで人々が近寄ってきた。それを押し進めたことも、押し返したこともなかった。
しかし、自分を男性として見ていない女性に男性として見せようと努力したのは初めてだった。
「妖精の力でですか?」
ダニエルの言葉を誤解した子どもたちは驚いて尋ねた。
何?
ダニエルは子どもたちの質問に眉をひそめたが、すぐに彼らが何を言いたいのかを理解した。
ああ、彼らは彼が妖精の力を使ってミルドレッドを誘惑したと考えているのか。
彼は笑うべきか、呆れるべきか迷いながら尋ねた。
「僕が誰かを誘惑するのに魔法まで必要な人に見える?」
瞬間、作業室内に静寂が訪れた。
リリーは「どうだ」と言わんばかりの表情をし、アイリスとアシュリーは視線をそらして目を合わせなかった。
ダニエルは言葉が見つからず、深いため息をつきながら手を振って言った。
「全部聞き終わったなら、出て行ってくれ。」
言葉が出たというより、ただの反射的な言い回しだった。
アイリスの顔が恥ずかしさで赤く染まり、母親のことを思い出して姿勢を正した。
「申し訳ありません。失礼を働こうとしたわけではありません。ただ、母が心配で……。」
アイリスの謝罪を聞きながら、再び眼鏡をかけたダニエルは微笑んだ。
彼は手に持っていた折り紙を置きながらこう言った。
「僕は君たちの母親が望まないことは何もしないよ。」
「結婚もですか?」
アシュリーがぽつりと尋ねる。
再び部屋の空気が凍りついた。アイリスも思わず声をあげてしまった。
「アシュリー!」
大丈夫だ。
ダニエルはアイリスに向かって手を挙げ、大丈夫だというジェスチャーを示した。
アシュリーの言葉は正しい。
彼はミルドレッドが望まない限り、何もするつもりはなかった。
ミルドレッドは既に2度結婚しており、子どもも3人いる
この時点で彼女が結婚で得られるものは夫の保護くらいだが、ダニエルはミルドレッドがそれを必要としていないと考えていることを知っていた。
アイリスが王妃になるなら、彼との結婚を考えるかもしれない。
アイリスのために。
しかし、ダニエルはミルドレッドが望んで初めて結婚を考えたいと思っており、状況や立場のために結婚することは望んでいなかった。
「君たちはどう思う?」
ダニエルは答える代わりに逆に質問した。
彼の質問がどんな意図を持つものか、アイリスたちには理解できなかった。
ダニエルはアシュリーを見つめながら再び尋ねた。
「僕が君たちのお母さんと結婚してもいいのか?」
「私たちには関係ありません。結婚するのはお母さんですから。」
リリーが答えた。
しかし、ダニエルはアシュリーが何か言い出しそうなのを察した。
アシュリーもリリーの言うことが正しいと考えているようだった。
お母さんがウィルフォード卿と結婚するかどうかは、お母さん自身が決めることだ。
しかし、それはお母さんがどこで何をしても血縁という二重の絆で縛られているアイリスやリリーには関係のない話だった。
ダニエルはアシュリーが何を最も不安に思っているかを理解していた。
そしてミルドレッドがそれを心配していることも知っている。
「アシュリー、僕が君のお母さんと結婚するとしたら、きっとこの家に来て一緒に暮らすことになるだろう。まあ、君のお母さんが僕の家に来ることになるかもしれないけれど、この家はかなり気に入ってるんだ。」
この丘の上にある邸宅は、街からかなり離れており、周囲は庭園と石垣で囲まれていて、誰も近づけないようになっているのが気に入っていた。
ダニエルはこの家が古びているところさえも気に入った。
たくさんの部屋、高い天井、広い階段、細い窓には、プレゼントや温室を補完する役割があった。
その細い窓は修理すれば問題ない。もしミルドレッドと結婚するなら。
ダニエルはミルドレッドとの結婚を想像し、思わずにっこりと笑う。
そして、自分の考えに困惑している子どもたちに問いかけた。
「その時、僕が君たちのお母さんの夫として君たちと一緒に住んでもいいかな?」
もう住んでいるじゃない?
アイリスとリリーの頭にまず浮かんだのはその考えだった。
しかし、アシュリーは違った。
彼女の表情は険しくなっていた。
母親がいつも彼女たちと一緒に暮らすだろうと父が言っていたことを思い出していた。
関係なく、彼女は自分が母親の娘だと言い聞かせていたが、それは母親の考えに過ぎなかった。
アシュリーはウィルフォード卿が彼女を気に入るかもしれないし、そうではないかもしれないと考えた。
それでも、それはどうにもならないことだと思った。
もしウィルフォード卿が母親と結婚した場合、二人が新婚生活を送り、干渉されないことを望むだろう。
アシュリーは、ウィルフォード卿が彼女を早々にどこかに嫁がせようとするかもしれないとも考えた。
それゆえにアシュリーは、「一緒に住んでもいいか?」というダニエルの質問に感動した。
「一緒に住まなければならないのですか?私はいつか一人で生活してみたいんです。」
アシュリーが感動している間、目に涙を浮かべたリリーが尋ねた。
ウィルフォード卿が母親と一緒に暮らしてくれるなら、それはいいことだ。
母親をウィルフォード卿に託し、自分の家を手に入れて一人で暮らせるかもしれないから。
ダニエルはアシュリーを見ていないふりをしながら、リリーに話しかけた。
「君たちのお母さんが許可すれば。」
お母さんが許可してくれるとは思えなかった。
リリーが一人で考え込んでいる間に、アイリスはアシュリーの手を握った。
ダニエルは確認していた折り紙を手に取り、再び話し始めた。
「もう答えは聞いたから、行ってもいいよ。」
子どもたちは重い足取りで外へ出て行った。
「どうして泣いているの?」
ポーチに出て、アシュリーが泣いていることに気づいたリリーが尋ねた。
分からなかった。
アシュリーは涙を流しながら苦笑いを浮かべていた。
いつかこの家を離れなければならないと考えていた。
生涯ここで暮らせるとは思ったことがなかった。
アイリスやリリーのように去ったとしても、また戻って来られるという確信はなかった。
彼女がいつもその家族の一員ではなく、ただの客であるように感じたからだ。
一度離れてしまえば、二度と戻れないのだ。