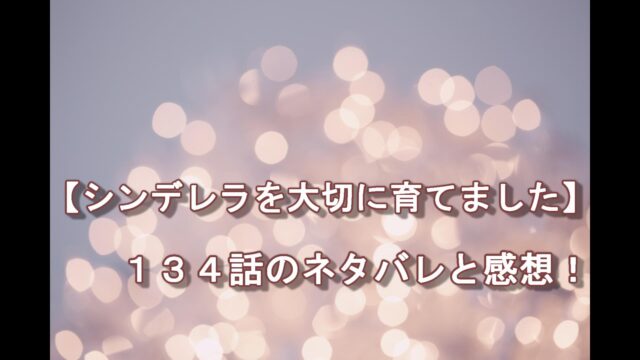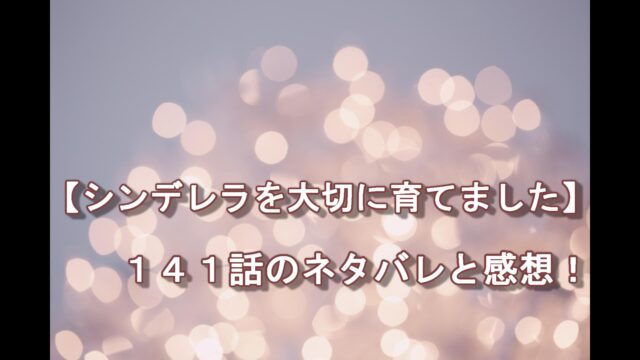こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

214話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 高貴な身分の謝罪②
「ムーア伯爵家から王太子妃候補を推薦したそうですよ。」
その二日後、城から戻ってきたダニエルが、ミルドレッドやナランと並んでかき氷を食べながら言った。
氷を削り、果物とアイスクリームを乗せたものだ。
単に氷を削ってシロップをかけたものは以前からあったが、ミルドレッドはそこに果物の盛り合わせと菓子、そしてアイスクリームが並べた。
「陛下からは何の言葉もなかったのに、許可が出たんですか?」
驚いたミルドレッドの言葉に、ダニエルは軽くうなずいた。
まだミルドレッドは、ムーア伯爵家に反対の手紙すら送っていなかった。
「ムーア伯爵が無理やり許可を取らせたみたいですね。」
「いいえ。ムーア嬢が直接、許可をお願いしたそうです。」
「そうなんですか?」
ミルドレッドの目が細められた。
自分から許可を求めただなんて?
そんなことをする人には見えなかった。
何か心境の変化でもあったのだろうか。
彼女はダニエルの肩に頭をもたせかけながら尋ねた。
「ムーア伯爵って、どんな人ですか?」
ダニエルは肩をすくめかけて、すぐに答えた。
「彼は自分の子どもにあまり関心を示さない人なんですよ。」
「全く反応もないんですか?」
「陛下には謝罪したそうですが。」
ダニエルには何も言わなかった。
それはミルドレッドやアイリスに対しても同じだったが、ミルドレッドはわずかに眉をひそめた。
少なくとも娘の方がまだましだ。
彼女の視線は、久しぶりにゲームをする子どもたちへ向かった。
城から戻ってきたダニエルがリアンを連れてきたおかげで、4人の子どもたちは久々にチームを組んで行う遊びを楽しめた。
「アシュリー、腕前が少し上がったわね。」
「リアンは少し体が締まったね。」
「最近、机に向かって座っている時間が増えたんですよ。」
「そうなんですね。」
ミルドレッドは全く残念そうではない表情でそう言い、持ってきたお茶を一口飲んだ。
ダニエルはそんなミルドレッドを見つめ、他人事のように言った。
「それで、二回目の試験のことですが。」
プリシラが辞退したので、残るはアイリスとロレナだけになった。
二人とも慈善活動には熱心だったが、回数で見ればロレナの方がやや多かった。
ダニエルはその微妙な結果を口にするのをためらっていたが、その時、アシュリーが打ったボールが建物の方へ飛んでいった。
次の瞬間、ダニエルはミルドレッドを抱き寄せ、彼女の体をかばっていた。
だがボールは二人からかなり離れた壁にぶつかって転がっていった。
驚いたミルドレッドは、くすっと笑って言った。
「ありがとう。」
続けて、ボールを打ったアシュリーが手を上げて──
「すみません!」
「私が行きます。」
リアンは建物の裏に飛んで行ってしまったボールを探しに走っていった。
アイリスがその後を追うのを見て、ミルドレッドの目が細まった。
ダニエルがカップを持ち上げながら尋ねた。
「アイリスを呼びましょうか?」
「いいえ、結構です。」
ミルドレッドがあっさりと答える態度に、ダニエルは薄く笑って聞いた。
「リアンを信頼しているんですか?」
「そういうわけではありません。」
そうじゃない?ダニエルが片眉を上げる。
ミルドレッドは彼に気づかないふりをして続けた。
「二人きりになりすぎないようにするのが、あまり目立たない方がいいと思いまして。」
「アイリスとリアンが二人きりになるのを防いでいたんですか?」
「そうです。この暑さの中、わざわざ外でゲームをしようと言い出した理由、何だと思います?」
「アシュリーがやりたいと言ったのかと思っていました。」
「まあ、それも間違いじゃないですね。」
いたずらっぽく答えるミルドレッドの言葉に、ダニエルも思わず笑みを浮かべた。
「見つけた!」
建物の裏に飛んでいったボールを追いかけていたリアンが、素早くそれを拾い上げて叫んだ。
そして、自分の後ろからついてくるアイリスの方へ向き直った。
「すぐ見つかったの?」
「花の前にあったよ。」
リアンが指さした場所を見たアイリスは、首をかしげた。
そこは、アシュリーが種をまいた場所だった。
芽が出始めた頃から、彼女がどれほど不思議がって喜んでいたか分からない。
「庭がきれいになったね。」
リアンの言葉に、アイリスの顔がぱっと明るくなった。
それは、初めて彼をこの家に連れてきた時を思い出したからだ。
あの時は雑草を抜くのが精一杯だった。
「うん。アシュリーと花を植えたの。」
リアンは、アイリスとアシュリーが花の種をまく姿を思い出して、にっこり笑った。
そしてすぐに顔を引き締めて言った。
「試験の話だけど。」
「ボランティア活動?」
「うん。発表があったんだけど……」
リアンが何を言おうとしているのか分かった。
アイリスは静かな表情を浮かべた。
彼女のボランティア活動の回数は足りなかった。
プリシラが一番多く、その次がロレナだった。
アイリスはミルドレッドと一緒に工房の準備をしていたため、あまり慈善活動には参加できなかった。
もう少し時間があって、工房の慈善団体が活発に動いていたら、それも得点に入ったかもしれない。
「大丈夫。」
「大丈夫だって?」
意外なアイリスの態度に、リアンは驚いて聞き返した。
当然、怒るだろうと思っていたのだ。
そんな彼の表情を見たアイリスも、すぐに口を開いた。
「悔しいけど、大丈夫。このくらいの差なら、慈善活動じゃなくて、むしろ財団の方にもっと貢献したってことだから。」
しかも今は、アイリスが前を歩いている。
彼女はにっこり笑って付け加えた。
「そして最後の試合は、私が勝つわ。」
自信たっぷりなアイリスの態度に、リアンは思わず安堵のため息をもらした。
手に持ったボールを一度見てから、彼女に近づき問いかけた。
「僕に手伝えることない?必要なことがあれば何でも言って。」
ない、とアイリスは言いかけて目を伏せた。
そして口を開きかけて、また閉じ、唇を噛んでためらった。
「アイリス?」
リアンは、どこかぼんやりしているアイリスの様子に何かを感じ、すぐそばまで近づいた。
どうにも躊躇しているようなアイリスの姿に、胸の奥が締めつけられるような感覚を覚えた。
「その……じゃあ……」
アイリスはためらいがちに口を開いた。
そして目をぎゅっと閉じて言った。
「キスして。」
「え?」
空気が止まったように感じた。
軽はずみなことを言ってしまったと後悔した瞬間、リアンは彼女の手を取り、尋ねた。
「してもいい?」
ずっとしたかった。
だが、アイリスが真剣に決意して努力している今、「キスしてもいい?」なんて聞くのはあまりにも場違いに思えて、なかなか口に出せなかったのだ。
「え?」
アイリスはリアンの質問に驚き、首をかしげたが、彼の表情が真剣だと気づき、再び顔が赤く染まった。
「う、うん。」
リアンはアイリスが気持ちを変えないうちにと、素早く彼女を引き寄せた。
そして彼女の顔の前で一瞬動きを止め、アイリスが目を閉じるのを見届けると、そっと彼女の唇に自分の唇を重ねた。
「ムーア伯爵令嬢がお見えです。」
執事の言葉に、本を読んでいたアイリスは目を丸くした。
周囲を見回し、自分とアシュリーしかいないことを確認してから尋ねた。
「私に会いに来たんですか? 母ではなく?」
「はい。アイリス・ヴァンス嬢にお会いしたいと申しております。」
執事の返答に、アイリスは何事か分からず瞬きをした。
プリシラ・ムーアが王太子妃候補から辞退したと聞いてはいた。
まもなく都を離れるという話も。
彼女がプリシラの友人なら、都を発つ前に会いに来たのだと考えることもできたが、アイリスはプリシラと仲が良いわけではない。
むしろ最後に会ったときには、彼女がプリシラを嘲るまでになっていたのだ。
まさか首都を離れる前に、自分を一度くらい叩いてから行こうというわけではないだろう。
アイリスはそう考えながらも後をついて、プリシラが腰掛けている書斎へ向かった。
「バンス様。」
プリシラはソファに座っていたが、アイリスが入ってくると立ち上がり、軽く会釈した。
本心では何の用で来たのか聞きたかったが、アイリスは最大限の礼儀を守って挨拶をした。
「今日はとても暑いですね。お元気でしたか?」
「ええ、この時期はいつも少し暑いですね。幸い、私が行く別宅は夏でもそれほど暑くないんですよ。」
首都を離れて行く場所がそこなのか?
アイリスは初耳だったが、黙って会釈し、プリシラに座るよう促した。
しかし、彼女は軽く首を振って言った。
「大丈夫です。すぐ出発しますから。出発前に、どうしても言っておきたいことがあって来ました。」
ついに本題か!
アイリスは思わず緊張して喉を鳴らした。
プリシラはひとつ息を吐くと、真っ直ぐに彼女を見つめて話し始めた。
「先日ヴァンス嬢と話してから、ずっと考えていました。少し気分を害されたのではないかと。」
それはアイリスも同じだ。
しかし彼女は何も言わず、プリシラはため息をついて続けた。
「高貴な身分には、それに見合う責任があります。それを知らない人はいません。」
――誰のこと?アイリスの視線が鋭くなる。
だが彼女が何か言う前に、プリシラが急いで続けた。
「問題は、その日ヴァンス嬢に会うまで、私はそのことを全く考えてもいなかったという点です。」
「そうですね。あなたの言う通りです。王太子妃という立場は、常にそういったことを考えなければならない立場です。私はそうは思っていませんでしたけれど。」
そんなことには興味はなかった。
プリシラが望んでいたのは、ただ自分が就ける中で最も高い地位だけだった。
彼女はおそらく、自分が王妃になっても王妃としての務めをそつなく果たせるだろうと考えていた。
十八年間を伯爵家の令嬢として暮らし、そのための教育を受けてきたのだから。
自信があるかと問われれば、そうではないが、できないとは思わなかった。
だが、家に戻ってからアイリスとの会話やミルドレッドとのやり取りを思い返すと、ふと疑問が湧き上がった。
――自分は本当に王妃になりたいのだろうか。
「結局のところ、私たちは貴族夫人として生きていくでしょう。運が良ければ、少しでも格上の家に嫁ぐことになるでしょうし。誰だって、より良い家に嫁ぎたいと思うものです。それは私も同じです。」
プリシラの言葉に、アイリスは渋い表情で喉を鳴らした。
それは彼女も同じ気持ちだった。
「だから私は王太子妃になりたかったんです。今でもそれが悪いことだとは思っていません。」
堂々としたプリシラの言葉に、アイリスは母の言葉を思い出した。
結局、人はより高い地位を目指すもの。
もしも貴族令嬢が得られる最高位が王妃の座なら、それを望むのは当然のことだ。
「私も、ムーア嬢が王太子妃の座を望むのは悪いことだとは思いません。」
アイリスはソファの肘掛けに手を置き、そう口にした。
ロレナとプリシラをライバルだと思ってはいたが、障害物だとまでは思わなかった。
いずれにせよ審査は宮廷で行われる。
彼女が資格を示すべき相手は、その二人ではなく宮廷そのものだった。
「でも、私があまりにも欲深だったと、そう思うでしょうね。」
プリシラはそう言って、苦笑した。
アイリスの目が見開かれた。
彼女は素早く身を乗り出し、声を上げた。
「まぁ!」
突然の大きな声に、廊下から書斎の中へと足音が近づいてきた。
プリシラはもちろん、アイリスも驚いた。
二人は口を閉じ、扉の方へ視線を向けた。
誰かが驚いて扉を開けて入ってきたわけではないか、確かめたのだ。
幸い、何事かと思って入ってくる者はいなかった。
アイリスは安堵の息をつき、プリシラに再び扇子を差し出しながら言った。
「そんなふうには思いませんよ。私が王妃になることを望むのなら、どんな羊だってそうなれるでしょう。」
プリシラの顔に、かすかな笑みが浮かんでは消えた。
――気に障る子だわ。
アイリスはそう思った。
気に入らない。
けれど――同時に気に入った。
「バンス嬢、あなたが王妃になることを願っています。」
そう言って、プリシラは暑さで脱いでいた手袋を再びはめ始めた。
そしてカップを手に取り、アイリスを見つめながら付け加えた。
「どれほど素晴らしい王妃になるか、楽しみですね。」
アイリスの顔にも微笑みが浮かんだ。
彼女が王太子妃になるとしても、王妃になるまではまだ時間がある。
アイリスはプリシラのために書斎の扉を開けながら尋ねた。
「外交官として行かれるんですか?」
「はい。父から詩集を編むか、首都官邸に入るか選べと言われたんです。」
「それで外交官を選んだのですか?」
「私は一度も従順な娘だったことがありませんから。」
そう言うプリシラの顔に、満足げな笑みが浮かんだ。
アイリスも、より柔らかく見えるその表情につられて微笑んだ。
そして、都を離れる彼女に一つ贈り物をしたいと思いついた。
「少しお待ちください。」
玄関先でプリシラを立ち止まらせたアイリスは、素早く中へ入り、試供品用に包んであった石けんを一つ手に取って戻ってきた。
「贈り物です。」
「石けんですか?」
「はい。あなたが防ぎに行った、あの工房で作った石けんです。」
プリシラの顔にわずかに赤みが差したが、彼女は何も言わずに石けんを受け取った。
それは、貴族へ送るための試作品として上品に包装され、美しい女性の横顔が描かれていた。
「あなたの妹さんですね。」
「はい、アシュリーです。リリーがそう言っていました。」
アイリスは、リリーがサンプル用の小袋をひとつひとつ描き終えるまで腕が取れそうなほど一生懸命だったことを思い出し、微笑んだ。
プリシラはビロードのカーテンをしばらく見上げていたが、召使い用の控室で待っていた自分の侍女の一人にそれを渡しながら挨拶した。
「ありがとうございます。大切に使わせてもらいます。」
「もし追加で買いたいときは、どこに連絡すればいいかご存じですよね?」
タイミングよく宣伝までこなしたアイリスの挨拶を背に、プリシラはムーア伯爵の馬車に乗って去っていった。
そして数日後、プリシラ・ムーア嬢がひっそりと首都を離れたという噂が、アイリスの耳にも届いた。