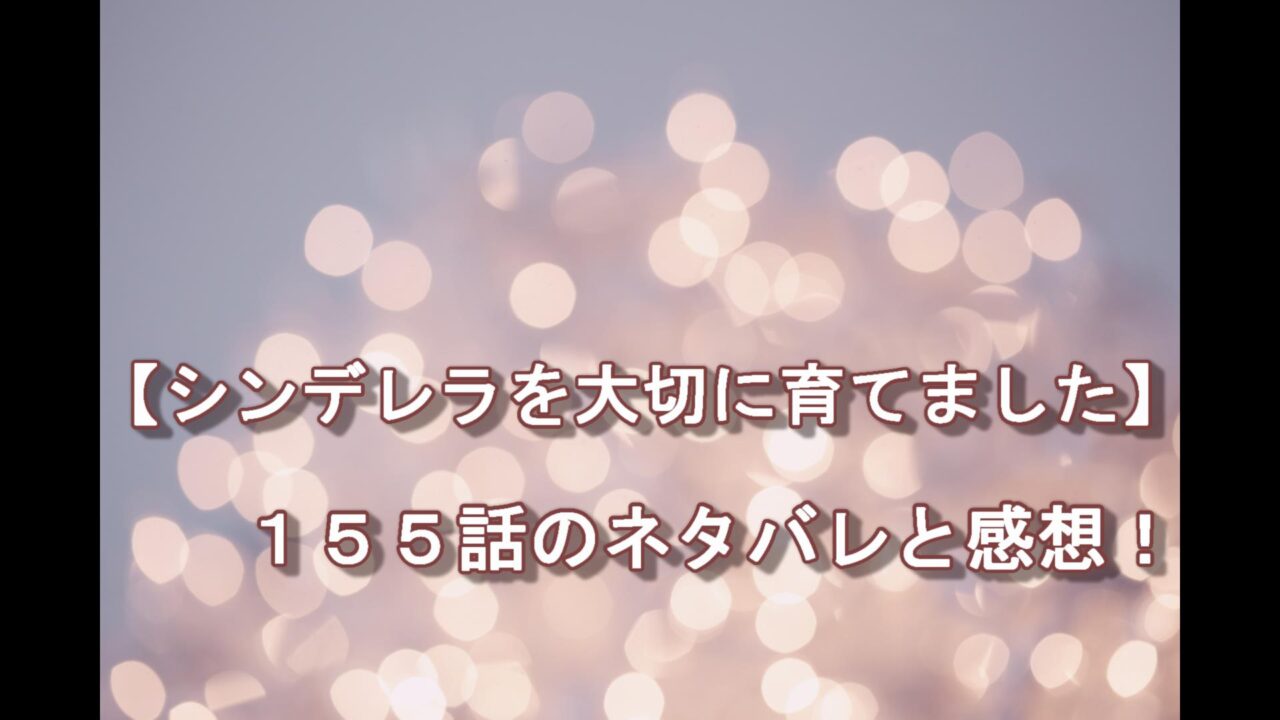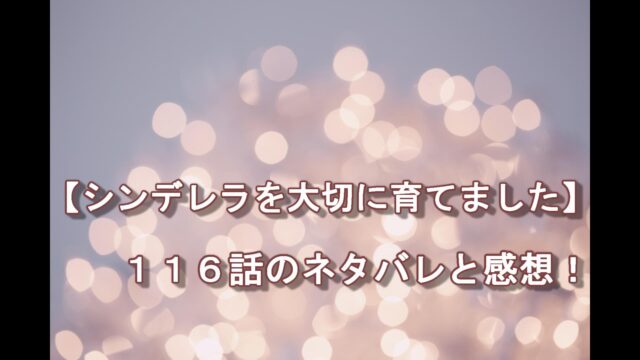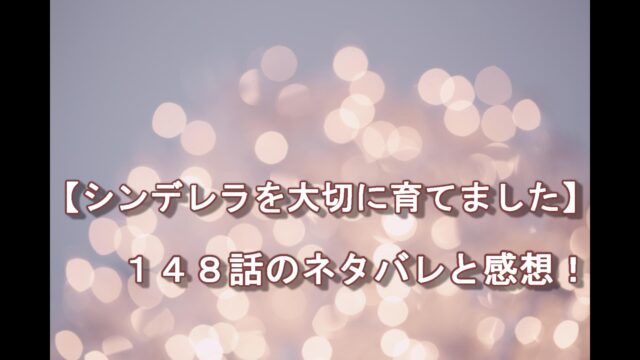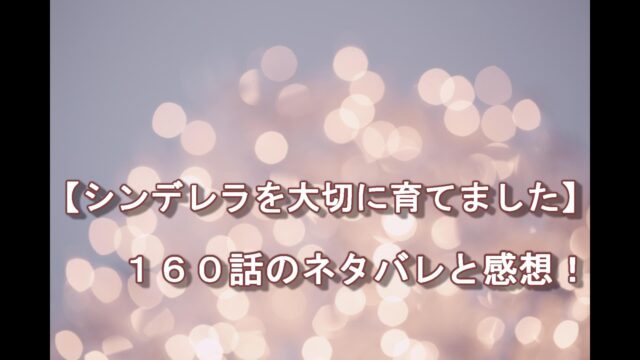こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
今回は155話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

155話 ネタバレ
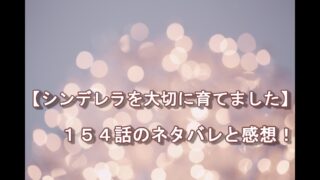
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 妖精のお茶会④
「虫がいないね」
ふとヴァレリーは、この天気に庭で行われるティーパーティーなら、必ずと言っていいほど現れる虫がいないことに気づく。
彼女の庭でもティータイムを持つ時はいつも甘いお茶とジャムの匂いを嗅いだ蜂や蝶が絡まったりした。
しかし、バーンズ家のティーパーティーは蜂どころか、蝶もいなかった。
「蚊帳です」
ミルドレッドはジャクソン伯爵夫人に微笑みながら言った。
ただ見やすいように網布を巻いたのではない。
蚊帳として使うために巻いたものだった。
彼女の言葉にヴァレリーは気づいたという表情で再びあずま屋を包み込んだカーテンを見た。
彼女のベッドにも蚊帳が付いていた。
しかし、それを東屋にも回すとは思わなかった。
「いい考えですね」
ヴァレリーの称賛にミルドレッドは天井を指しながら言った。
「元々はあの日よけだけを使おうと思ったんですが、アイリスが虫のせいで困っている方もきっといるだろうと提案したのです」
人々の視線がアイリスに向けられる。
確かに虫のせいで庭で食事をするのを諦める人がいる。
しかし、みんな不便だと思っていただけで、こんなふうに直すとは思わなかった。
人々の感嘆する表情に、アイリスは恥ずかしそうな顔をした。
「私も家に帰ったら、あずま屋に蚊帳を張らなければなりませんね」
サンドラはいい考えのように言った。
どうしてこんなにいい考えができなかったのだろうか。
その時、相対的に若い方に属するネルソン男爵夫人が割り込んできた。
「私はこの葉っば模様のキャノピーです。家に帰ったらすぐに注文を入れなければなりません。バーンズさん、どこで注文されたのか教えていただけますか?」
ネルソン男爵夫人の要請にアイリスの視線がミルドレッドに向かった。
それももう話を終えている。
彼女は再びネルソン男爵夫人を見つめながら言った。
「実はこれは参加してくださった方にプレゼントしようと思っていたんです。お宅にお送りしてもよろしいでしょうか?」
その瞬間、亭子の中に軽い歓声が沸き起こる。
ネルソン男爵夫人のように口を利かないだけで、他の人たちもそれとなく欲しがっていたのだ。
ミルドレッドはにっこり笑って茶碗を持ち上げる。
前もって冷浸しておいた冷たい車が心地よく感じられた。
「奥様」
その時、ジムが近づいてきてミルドレッドに体を傾けた。
なんだろう?
彼はまごついている彼女にささやいた。
「お客様がもう一人いらっしゃいました」
「もう一人ですか?」
招待した人はみんな来たけど?
ミルドレッドが東屋の客を見回した時だった。
ジムは素早く付け加えた。
「王妃様です」
ミルドレッドの視線はパビリオンの外を向く。
日が暮れているせいで外の姿が鮮明に見えなかった。
しかし、誰かがこちらに近づいているのが見えた。
なんてこった。
ミルドレッドは飛び起きてジムに言った。
「ティーカップの準備をしてください。デザートの残り物があるかも確認してください」
「了解致しました」
ジムがうなずいて引き下がると、人々はミルドレッドを見ていた。
彼女はアイリスを見て、安心してという意味で微笑んだ。
そして人々を見回しながら言った。
「驚きのお客様がいらしたそうです」
驚くべきお客さん?
人々は何が起こっているのかと思ってミルドレッドから入口に視線を移した。
その瞬間、背がすらりとした男が蚊帳として使うカーテンを歩いて入ってくる。
彼が誰なのか調べた人々の目が大きくなった。
クレイストーン卿。
王妃の護衛騎士だ。
彼がここにいるということは、王妃がバーンズ家のティーパーティーに訪れたということだ。
「殿下」
「殿下」
その瞬間、亭子の中の人々が席から立ち上がり、頭を下げる。
王妃は人々がまだ全員席を埋めているのを見て軽く驚いた表情をした。
今日、彼女はバーンズ家のティーパーティーだけでなく、クレイグ侯爵家のティーパーティーとムーア伯爵家のティーパーティーも参加した。
わざとバーンズ家のティーパーティーを一番後ろに延ばしたのはバーンズ家を無視するのではなく、逆にアイリスが気になったからだ。
ダニエル・ウィルフォード男爵が推薦した少女。
裕福でなく父もいない、目立つ美人でもないお嬢さん。
しかし、彼女が着たドレスが社交界の最初の1ヵ月を熱くし、王大妃殿下もよく見ていた。
それに王子が直接候補の一つに選んだなんて。
ヘザーはアイリスが息子を捨てたまさにあの娘だろうと直感した。
彼女の息子は一体アイリス・バーンズさんのどこがそんなに好きで、フラれても諦められなかったのだろうか気になっていたのだ。
それで彼女はわざとバーンズ家を一番最後に訪れることにしたのだ。
一番遅く行けばお客さんもほとんどいなくなるだろうし、アイリスと彼女の母親であるバーンズ夫人と静かに話せると思って。
「急に来て、びっくりさせたんじゃないかしら」
王妃はそう言ってあずまやの中に入ってきた。
外から見ても白い布に包まれてあちこちに明かりが見える亭子の姿は神秘的に見えた。
しかし、中に入ってみると、その神秘さはさらに強くなる。
椅子ごとに置かれた巨大な木の葉。
水盤の上に浮いた小さなろうそく。
規格がまちまちの椅子。
王妃の視線がカーテンを固定するために持ってきた植木鉢と額縁に向かった。
「ここに座ってください、殿下」
その時、ミルドレッドが自分の椅子を王妃に譲って退いた。
ヘザーは使用人が持ってきたもう一つの椅子に座るミルドレッドに感謝の意を表して目の挨拶をして席に座りながら話した。
「妖精のティータイムだね」
「なるほど、賢明な殿下はすぐにお気づきですね」
誰かがお世辞を言ったおかげで雰囲気が柔らかくなる。
王妃は周囲を見回しながら、楽しそうに話した。
「とてもおもしろいわ。新鮮で賢いね」
「蚊帳で全体を包んで虫も入ってこないんですよ」
モーガン伯爵夫人は自分の仕事のように誇らしげに言った。
なるほど。
王妃はムーア伯爵のティーパーティーを思い出す。
プリシラ・ムーア令嬢も庭でティーパーティーを開いた。
庭を美しく飾っていて目が楽しかったが、庭なので虫から自由ではなかった。
そのような点で、アイリス・バーンズ令嬢は賢く頭を使ったのだ。
庭の造園は何人かの伯爵家についていけないだろう。
だから亭子でティーパーティーを開くが蚊帳を叩いて周辺の姿を一皮隠して異国的な感じがするようにしたのだ。
「バーンズさんの考えかな?」
王妃の質問にアイリスは緊張のあまり反射的にうなずいた。
しかし、すぐに彼女は率直に答えた。
「アイデアを出したのは私の末妹でした、殿下。中に植木鉢と絵を置こうというのは二番目の妹の考えです」
「創意的な妹がいるのね」
ヘザーはそう言ってミルドレッドに尋ねた。
「君の娘がみんな3人だと言ったかしら?」
「はい、殿下。この子が一番上のアイリスです。下にリリー、アシュリーがいます」
「リリー」
どこかで聞いた名前だ。
女王がリリーの名前をどこで聞いたのかじっくり考えているうちに、ジムが新しいティーカップとケーキを持って帰ってきた。
「涼しくなったので温かいお茶を用意しました」
いい匂いに王妃は軽く目を閉じる。
今日一日中ティーパーティーに通いながら冷たいお茶を飲んで暖かいお茶が懐かしかったお茶だった。
ジムは続いて皿を下ろしながら言った。
「生クリームと果物をのせたカステラです」
これが残ってたの?
ミルドレッドの顔に驚いた表情が浮かんだが、素早く元に戻った。
運がよかった。
ゴシンがミルドレッドが作った方法を真似して比較してみようと自分のものを食べなかったのだ。
「それから」
ジムは2皿目を王妃の前に置きながら言った。
「ハムとチーズを入れたサンドイッチです」
嬉しい言葉に王妃の目が輝く。
一日中ケーキばかり食べていたので重たい料理になるようなものが食べたかったところだ。
そして、それは王妃だけではなかった。
4種類のおやつとお茶を飲んだが、楽しく話をしたおかげで招待された人々も小腹がすいた。
甘いものではなく、何か食べたかったのだ。
続いて、使用人たちが注いでくれる温かいお茶とハムを厚く切って入れたサンドイッチ一切れに、あずまやの中に再び活気が蘇る。
「おもしろいわ」
王妃は特別なサンドイッチをあっという間に食べてしまった後、カステラを味わいながら微笑んだ。
お城でも食べられるサンドイッチだったが、甘いものだけを一日中食べた彼女の口に特においしく感じられた。
喜ぶ王妃を見た人々の顔に意味深長な表情が浮かんだ。
彼女の表情を見ただけで今度の試験の優勝者が誰なのか分かるような気がした。
」とても面白かったです」
日が暮れて薄暗くなると、お客さんたちが離れ始めた。
その間、ゴシンが新しく作ってきたパウンドケーキとチーズ、ワインまでもてなされたお客さんたちは、楽しい気持ちで去っていく。
ミルドレッドは人造の木の葉のキャノピーを客の家に送ると約束し、客を見送った。
そして、その見送りの末、王妃がミルドレッドとアイリスを振り返りながら言った。
「実はバーンズさんと話がしたくて来たんだけど」
「光栄です、殿下」
今は緊張が少し緩んだアイリスがにっこり笑って挨拶する。
リリーとアシュリーは女王に挨拶するために彼女に近づいた。
「君の娘たちだね」
「はい、殿下。こちらがリリー、こちらがアシュリーです」
リリーはアイリスに似ている。
しかし、アシュリーは目に見えて美しい女性だった。
面白いね。
王妃はバーンズ家の3人の娘を交互に見て微笑んだ。
彼女の息子が一度蹴られても忘れられない娘だ。
家や外見なら、ロレーナ・クレイグの方がましだった。
欲と財力はプリシラ・ムーアの方が良かった。
王妃の頭の中にアシュリーはバーンズ夫人が2番目の夫の死んだ妻から得た娘だということが浮び上がった。
さっき、アイリスは功績を実妹のリリーだけでなくアシュリーにも渡した。
「姉妹が仲が良いのはいいことね」
王妃はそう言ってアイリスに向かって首をかしげた。
姉妹が仲が良いことと、自分の兄弟に功績を回すことは別問題だ。
それは目下の功を認めるという意味だ。
「近いうちに、バーンズさんをティータイムに招待しよう」
アイリスの目が大きくなる。
王妃の招待を受けるというのは光栄だ。
特に、今のように王子妃候補の試験中ならなおさらだ。
ヘザーは片目を閉じて冗談のように言った。
「その時に、さっき食べたあのソフトなケーキをもう一度味わいたいんだけど」
「アイリスにお間かせします、殿下」
素早いミルドレッドの言葉に王妃はにっこりと微笑んだ。
彼女はミルドレッド、アイリス、リリー,アシュリーに目礼をして振り返った。
「リリー・バーンズ」
思い出した。
馬車に乗って城へ行く途中にヘザーはリリーの名前をどこで聞いたかを思い出す。
ダグラス・ケイシー卿が好きで、どうしていいか分からないと言っていたお嬢さんの名前。
「ああ、これは面白いね」
ヘザーの口元に笑みが浮かんだ。
彼女の息子が夢中になっているアイリス・バーンズ。
ダグラス・ケイシー卿が夢中になっているリリー・バーンズ。
そしてダニエル・ウィルフォード男爵のミルドレッド・バーンズ。
王妃からティータイムに招待されたアイリス。
今回のティーパーティーの優勝は間違いなくバーンズ家でしょう。
功績を妹に譲ったアイリスが素晴らしいですね!