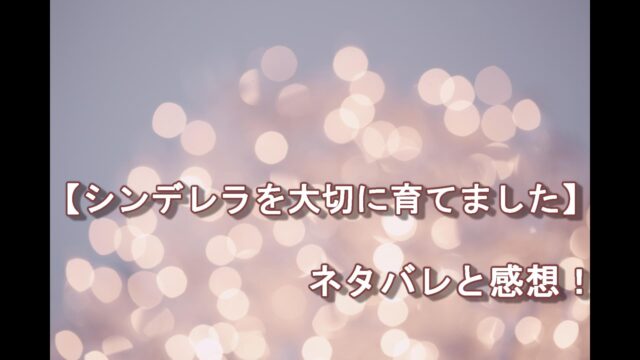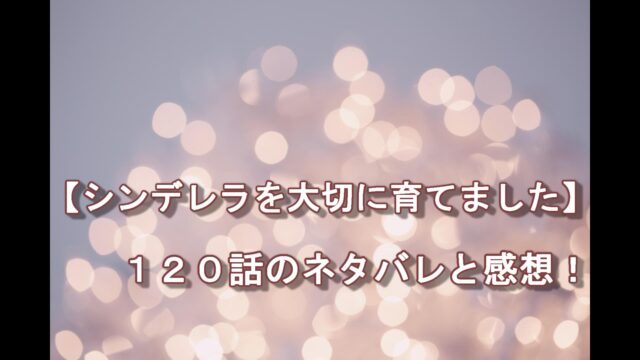こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

204話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 皇太子妃の資質②
王妃に会って帰ってきたアイリスは、気分がかなり良さそうだった。
何の話をしたのかは分からないが、悪い気はしなかったようだ。
私はパンをちぎりながら、そっとアイリスの様子をうかがった。
最近、いつも考え事にふけっていたアイリスの姿が、今日は少しはっきり見えた。
リリーとアシュリーの会話にも加わっていたし、私が「今日はどんな一日だった?」と尋ねると、ちゃんと返事もしてくれた。
何か考えることがあったのかと思って、ただ放っておいたけれど、それが答えだったのかもしれない。
あるいは、王妃との対話の中で答えを得たのかもしれない。
私は新しいアイリスが大きく成長したという思いに、思わずため息をついた。
もちろん私の記憶の中のアイリスはとても幼い赤ん坊の頃から始まっているけれど、もう一度その記憶を辿ってみると、彼女ときちんと向き合ったのは今年の初めからだった。
これは仕方のないことだと聞いていた。
家門は私をミルドレッドにしようとしていて、私が完全にミルドレッドと認識される前に、ダニエルが割り込んできた。
おかげで私は何も考えずに記憶を思い出すと、まずミルドレッドの記憶がよみがえるが、少し集中すればそれが自分の記憶ではないと区別できるようになった。
悪いことばかりではない。
私は少し前向きに考えていた。
どうせ私はミルドレッドとして生きていかなくてはならない。
変に言い間違えるよりは、むしろこの方がいいかもしれない。
ダニエルは、自分がもう少し遅れていたら、私の元の世界に関する記憶まで全部忘れていたかもしれないと言っていたし、それは一大事だから。
私がここでお金を稼ぐすべてのことは、私の元の世界で見たり経験したりしたことのおかげなのだから、それを忘れてしまってはいけない。
だから、このくらいがちょうどいいのかもしれない。
「お母様、そして旦那様。」
私が今年の初めに見たアイリスと今のアイリスは──頭の中でアイリスを比較していたところ、アイリスが口を開いた。
今年初めのアイリスは少し不満があり、表情もやや不機嫌だった。
少し自己中心的でもあった。
今でもアイリスは少し自己中心的なところがある。
でもそれは良い意味での自己中心性だった。
誰だって自分のために考え行動していれば、ある程度は自己中心的にならざるを得ないのだから。
むしろアシュリーが心配だ。
アの子はまだ自分が何をしたいのか、何が好きなのか見つけられていないようで、ほとんどの機会をアイリスやリリーに譲ろうとしていた。
「お話があります。食事が終わった後に、少しお時間をいただけませんか?」
私とダニエルの視線が交差した。
「いいわ。」
私はそう答えて、サラダを口に入れた。
そしてアイリスの様子をじっと観察し始めた。
アシュリーとリリーもちらちらとアイリスの顔色をうかがっているのが見えた。
私は最後にダニエルの方を見たが、彼はアイリスにまったく関心がない表情で肉を切っているのを確認した。
「何か違うことがしたいです。」
夕食が終わり、書斎に移動するとすぐ、アイリスはそう言った。
彼女は何を言っているのだろう。
私はコップを口に運びながら尋ねた。
「何が違うって? 何を?」
まさか王妃になるのを辞退したいという意味ではないだろう。
正直に言えば、リアンと比べるとアイリスはずいぶん控えめだが、王妃候補の試験を辞退するよりは、ただ落ちる方が簡単な気がする。
もしアイリスが王妃候補試験をやめたいのならやめさせて、むしろ試験を変に受けて落ちたふりをするように説得しようとしたが、アイリスが再び口を開いた。
「ボランティア活動のことです。今やっていることじゃなくて、別のことをしたいんです。」
私とダニエルの視線が交差した。
彼も私と似たような考えをしていたのか、その表情には理解の気配があった。
私は再びアイリスを見つめて尋ねた。
「何をしたいの?」
今やっていることといっても、貴族の令嬢たちを連れて孤児院に行っただけだ。
それ以外に何もしていないのに、別のことをしたいというのは少し時期尚早ではないかと思ったが、とにかくアイリスの言うことを聞いてみなければならない。
「今日、王妃様にも同じ質問をしました。」
王妃にそんなことを聞いたの?
私は反射的に問い返した。
ダニエルの方を見た。
こんなこと聞いてもいいのかな?
幸いにもダニエルは深刻な表情ではなかった。
彼は面白そうな表情でアイリスを見つめていた。
うーん、考えてみたら王妃はアイリスのロールモデルのようなものじゃない?
つまり、アイリスが王妃になるのなら、彼女の先生になってくれる人は王妃と王太后しかいない。
だから王妃に質問するのは、もしかしたらごく自然なことなのかもしれない。
「王妃さまは何とおっしゃったの?」
私の質問に、アイリスはしばらく口を閉ざしていたが、再び口を開いた。
そして私とダニエルを交互に見ながら言った。
「財団を作ってはどうかとおっしゃいました。」
財団?法人財団のようなもの?
私はふぅとソファに身を預け、胸の上で腕を組んだ。
横を見ると、ダニエルも同じようにソファにもたれながら足を組んでいた。
「いい考えダね。」
ダニエルの言葉に、アイリスの顔が少し和らいだ。
彼女は私の返事が気になる様子で私を見つめた。
私はよく分からなかった。
「財団」というのは何らかの目的を持ってお金を稼いだり使ったりする機関のことだよね?
でもアイリスが言っているのは人々を助けるってことじゃない?
稼ぐのではなく、使うことしかできないのでは?
「ダメですか?」
私が何も言わないでいると、アイリスは自信を失ったような表情で尋ねた。
私はパンを一口かじりながら聞き返した。
「財団を設立して、それで人々を助けたいってこと?」
「はい。」
「じゃあ、その人たちを助けるためのお金はどうやって集めるの?お金を使うのは財団だけど、どこからお金を稼ぐの?」
アイリスの顔に困っているような表情が浮かんだ。
彼女はダニエルを一度見つめてから、ゆっくりと口を開いた。
「戻ってくる途中で考えてみたんですが、旦那さまはギャラリーを病院で開いて、支援を受けていらっしゃいましたよね。」
「病院が受け取ったんだよ。」
ダニエルがすぐにアイリスの言葉を訂正した。
それは重要なことではないはずだ。
私は彼を一度見てから、再びアイリスに視線を移した。
彼女は膝の上に置いた自分の手の指をもてあそびながら話し始めた。
「最初は支援を受けてもいいのかと思って。でも、それで、うーん……」
それで何?
私とダニエルは、アイリスが続けて話せるように、何も言わずに待った。
彼女は私とダニエルの目線を気にしながら、再び口を開いた。
「旦那さまが私にお金を稼ぐ方法を教えてくださったんです。そうしてくれたら嬉しいです。もしそうでなければ……。」
「そうでなければ?」
私がパンをちぎるのと同時に、ダニエルが低い声で尋ねた。
「そうでなければ?」
「お母さまがビヌ工房を開こうとしていらっしゃるじゃないですか。そこで私ができることをして、財団が支援してくださったらどうかと思って。」
ああ、それでようやくアイリスが何を言おうとしていたのか分かった。
ははは。可愛らしい発想だ。
私はにっこり笑いながら尋ねた。
「ビヌ工房で何を手伝ってくれるの?」
「うーん、計算は得意です。手紙を書くこともできますし、知人たちにビヌを広めることもできます。それに……。」
それで?
私とダニエルはアイリスの可愛らしい申し出に、ただ口を閉じて次の言葉を待った。
まもなくアイリスの顔がぱっと明るくなった。
「私が王妃になれば、お母様のレース工房の助けになるのではないでしょうか?」
まったく…。
私は笑い出しそうになるのをこらえて唇をしっかりと閉じた。
いや、アイリスの言葉があまりにも突飛だったから笑ったのではない。
彼女の計画がいかにも子供っぽくて、可愛らしかったからだ。
隣でダニエルがゴホゴホと咳をしたのが聞こえた。
おっと、笑ってはいけない。
私はこっそり肘で彼のわき腹をつついた。
そしてアイリスに向かって言った。
「いい考えだと思うよ、アイリス。ただ問題は、私の工房はまだ始まってもいないということ。あなたの試験の点数の役に立つには、少し遅すぎるかもしれないわ。」
驚いたことに、アイリスの表情が真剣になった。
彼女は背筋をぴんと伸ばして言った。
「これは試験とは何の関係もありません。私がやりたいことなんです。」
その瞬間、ダニエルのくしゃみがぴたりと止まった。
彼は姿勢をすぐに整え、アイリスをじっと見つめた。
そしてため息をつきながら言った。
「リアンが半分の半分でも似ていればよかったのに。」
唐突な言葉に、私はもちろんアイリスも思わず笑ってしまった。
リアンには少し心配な部分もあるけれど、それでも好きな男の子だと言って、アイリスが弁護するように話した。
「いいえ。リアンも頑張ってるんです。」
「まあ、最近は少しマシになったけどね。」
そう言って、ダニエルは自分の膝をさすった。
とはいえ、まだ完全には納得していない様子に、私は苦笑いを浮かべた。
リアンは少し落ち着きのない、やんちゃなタイプではある。
「財団を設立すること、調べてみますね。」
そう言って、私はアイリスにそろそろ退出してもいいという合図を送った。
少し考える必要があった。
アイリスは大人びた考えを持っていたけれど、この国でそれをどう設立・運営するのか、そしてそれが彼女と私にどんな影響を与えるかを見極める時間が必要だった。
「前向きに考えてくださるのですか?」
最後の最後までアイリスは真剣に尋ねた。
当然だ。
「頑固じゃなければいいんですけど。」
アイリスが出て行くや否や、ダニエルがそう言った。
え?と私は間抜けな表情を浮かべたが、彼はにっこり笑って続けた。
「リアンのことです。アイリスの頑固さがリアンに似ていないといいなと思って。」
「うーん、夫婦は似るって言いますよね。二人が結婚したら似てくるんじゃないですか?」
ダニエルがふと立ち止まり、微笑んだ。
なぜ?「夫婦は似る」という言葉はこの国にはないのか?
ぎこちない私に、彼はパンを差し出しながら言った。
「そうなんですか。」
「バンス嬢。」
リリーがギャラリーから出てきたとき、彼女を迎えに来ていたのは、彼女を迎えに来る予定だったケイシー卿ではなく、別のケイシー卿だった。
フィリップ・ケイシーと会う予定だったリリーは一瞬戸惑ったようだったが、ダグラスを見て立ち止まった。
すると、ダグラスが素早く手を差し出して言った。
「奥様に急用ができたため、代わりに私が来ました。行かれるところまでお送りいたします。」
リリーはジャケットまで着こなしたダグラスの様子を見ていた。
どこかへ出かける道中なのか、非常にきちんとした装いだった。
もちろん、ダグラスは今まで家にいて、フィリップからの電報を受け取るや否やリリーに会える喜びで、きちんとした身なりで出てきたのだろう。
「まさか私のためにこんなに着飾ったわけじゃないよね」とリリーは思いながら言った。
「ちょっと画室まで行こうと思うんだけど、そこまでだけでも車に乗せてくれませんか?」
本来はフィリップと一緒に行く予定だった。
そして、お茶を飲みながら展示会の話をするつもりだった。
最近、リリーはいくつかの絵をギャラリーに預けたのだ。
もちろん、ここで言うギャラリーとは、裕福な人々や貴族が所蔵する芸術品を展示する場ではなく、それを販売する場所を指す。
リリー・バンスという名義ではなく、単に「リリー」という名前だけでギャラリーに販売を依頼した彼女の絵は――最近、1点が売れたという知らせを聞いた。
さらに2点に興味を示している人がいるという知らせに、リリーの気分は空を飛ぶようだった。
フィリップはそんなリリーに、自分のギャラリーでデビューし、展覧会に作品を展示することも考えていると話す予定だった。
「いいえ。奥様がどうしても玄関先までお送りするようにと仰せだったので、今日は私がエスコートさせていただきます。」
融通の利かないダグラスの言葉に、リリーは不満げな表情を浮かべ、パンをかじった。
少し不快だった。
温室であの日以来、ダグラスに直接会うのは初めてだった。
もちろんその間に、ダグラスがリリーに花や本などを送ってくることはあった。
リリーはそのことを思い出して、感謝の気持ちを込めて言った。
「先日送ってくださった本、ありがとうございました。とても楽しく読みました。」
「お気に召さなかったらどうしようかと心配していましたが、楽しんでいただけたなら何よりです。」
「アシュリーも面白かったって。」
ダグラスはアシュリーが面白く読んだという言葉に、喉を鳴らして咳ばらいをした。
彼はリリーさえ面白がってくれたなら、それで十分だと思っていた。
アイリスやアシュリーは、正直言えば彼の関心の外にあった。
もちろん、アイリスとアシュリーはリリーの姉妹だから、彼女たちにとってつまらないよりは面白い方がいいのだが。
「それと、お花もありがとうございました。」
「どういたしまして。」
その会話を最後に、馬車の中には静けさが流れた。
リリーはそっとダグラスの顔を見つめたが、彼がまっすぐな姿勢で自分の方を見て座っているのを見て、慌てて視線を逸らした。
本当に律儀な人だ。
リリーは、ダニエルやリアンはこれまでとは違うダグラスの姿にため息をついた。
彼女から見ると、ダグラスは幼い坊っちゃんのようなリアンや、何を考えているのかわからない大人の男、ダニエルの中間に位置する男のように感じられた。
大人ではあったが、ダニエルほど考えているようには見えず、リアンほど浅くもなく、どこか大人びていた。
「三人ともハンサムという共通点はあるわね。」
ため息混じりにぶつぶつと呟くリリーの言葉に、ダグラスが眉をひそめた。
「何とおっしゃいましたか?」
「いえ、なんでもありません。」
燃え立つような赤い髪と、やや明るく見える緑の瞳。
くっきりした鼻筋と彫りの深い顔立ち。
まるで彫刻のようなダグラスは、完璧にハンサムな男だった。
しかしリリーは、それ以上にダグラスの体つきがどれほど完璧なのかを知っていた。
彼と踊ったときに彼の首から肩にかけてのラインがどれほど整っているか、その下の広い胸板がどれほど硬いのかを手で触れてみた。
たまにはこんな風にハンサムな男性を描いてみたいと思う。
リリーは心の中でため息をついた。
自分の家族を描くのも楽しいけれど、こんなにハンサムで体つきのいい男性も描いてみたい。
もちろん、彼女が住んでいる近くの邸宅にもダグラスのように体つきがよくてハンサムな男性が一人住んでいる。
ダニエル・ウェルフォード。リリーが「私のモデルになっていただけませんか?」と声をかけることすらできないような人だ。
何度か聞いてみようかと迷ったこともある。
しかしリリーは、ダニエルが絶対に許可してくれないとわかっていたし、そう考えるだけで、彼が少し怖くもあった。
「ところで、アトリエには何をしに行くのですか?」
長い沈黙を破って、ダグラスが尋ねた。
リリーはぼんやりと窓の外を見ていたが、ぱっと顎を持ち上げた。
「…あ、新しい帽子を買おうと思って。少し前に別の画家から、新しい帽子職人の話を聞いたんです。」
最近、若い帽子職人が現れたという話を聞いた。
まだ若くて経験は少ないが、それほど高くなくて素晴らしい帽子を売っているという話に、リリーは今回は直接帽子を買いに行こうと考えていた。
これまで彼女は一人で帽子を買ったことがなかった。
ほとんどの道具はダニエルが選んでくれて、以前帽子店に行ったときもダニエルが同行してくれたので、彼の勧めどおりに買った。
いや、それを「買った」とは言えない。
リリーが別の帽子に夢中になっていたとき、会計しようとすると、すでにダニエルが支払いを済ませた後だったのだから。
そこで彼女は今回は直接購入する予定だった。
前回、画家たちと話をしてみて、自分が画材についてどれだけ無知だったのかを知った。
「それに、奥様があなたを画家の集まりに紹介したとおっしゃってましたね。」
ダグラスの言葉に、リリーはそっと微笑みながら言った。
「はい。楽しかったです。ケイシー伯爵夫人は本当に親切な方です。」
その言葉にダグラスは「奥様は気が利く方だ」と言いかけて口をつぐんだ。
リリーに他の男性を紹介したという話を初めて聞いたとき、彼は少しばかり嫉妬心混じりに、余計なことをしたんじゃないかと苛立った。
しかし今、リリーが目を輝かせながら楽しかったと言うのを見ては、とても奥様が「余計なことをした」とは言えなかった。
彼はリリーが楽しそうにしているのを見るのが好きだった。
自分には見せたことのない、嬉しそうな表情や面白がっている表情がリリーの顔に浮かぶと、彼女の瞳の色が少し明るくなって薄緑色に変わるのが好きだった。
リリーがそういう表情を他の男性のせいではなく、自分のせいで浮かべてくれたらどれほど良いか。
ダグラスはそう思いながら、心の中でため息をついた。