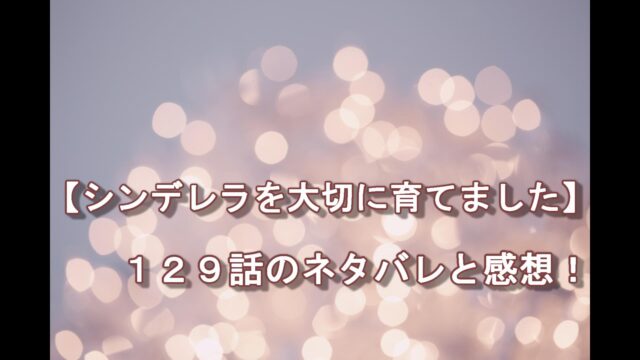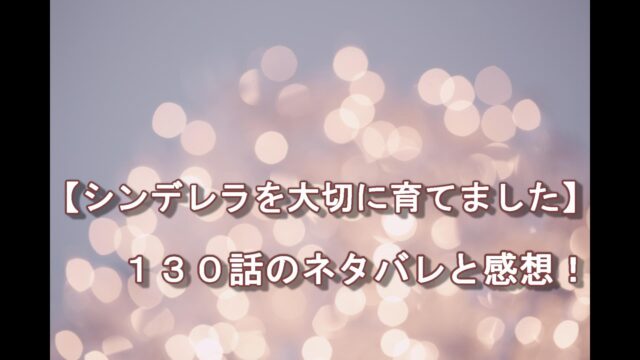こんにちは、ピッコです。
「シンデレラを大切に育てました」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

210話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- オープニングセレモニー
「ここまでにしましょうか?」
昼食の時間が近づくと、リリーは筆を置きながらそう言った。
「もう?」とダグラスはきょとんとリリーを見つめていたが、はっとして驚き、小声で尋ねた。
「もうですか?まだ続けられますけど。」
そう言いつつも、黙って座り続けていたダグラスの体はすっかり冷えていた。
彼は、リリーが席を立ち背伸びをする様子まで、じっと見守っていた。
昼近くになると、光が強すぎて――
カーテンが引かれていたおかげで、リリーがアトリエとして使っているこの階の音楽室は、柔らかな光で満ちていた。
自分の背丈ほどのイーゼルの前で体を伸ばすリリーの姿に、カーテン越しの緑がかった光が降り注いでいた。
ダグラスはなぜか、リリーの心情をほんの少し理解できた気がした。
もし自分に絵の才能があれば、今のリリーの姿を描いただろう。
「お昼ご飯の時間ですよ。お腹すいてませんか?」
そう言われて、ようやくダグラスは空腹を感じて席を立った。
リリーが自分を見上げながら絵を描く様子を眺めていたせいで、腹が減っていることさえ気づかなかったのだ。
剣術の稽古でもここまでではなかった。
ダグラスは苦笑しつつジャケットを脱ぎ、リリーのように大きく背伸びをした。
そのおかげで、体のこわばりが一瞬で解けた。
「わぁ」
そのとき、リリーが小さく感嘆の声をもらした。
「ん?」
ダグラスは動きを止め、彼女を見た。
しかしリリーがじっと自分を見つめていることに気づくと、彼も固まってしまった。
「な、何か?」
リリーは、ダグラスの引き締まった体に感心していた。
ジャケットを脱いだことで、薄いシャツ越しに筋肉の線がはっきりと浮かび上がっている。
こんな体を描いてみたい――できることなら上着も脱ぎ、シャツ一枚で無造作に立つ姿を。
少し乱れた髪のままで。
そこまで想像してしまい、リリーの頬は熱くなった。
(私、何を考えてるのよ…!)
そんなこと、ダグラスに絶対悟られてはいけない。
「い、いえ。お昼にしませんか?」
リリーは慌てて道具を片付け、話題を変えた。
彼女が今日の昼食を何にするか考えている間に、ダグラスはゆっくりとリリーに近づいた。
そして、さっきまでリリーが向かっていたイーゼルの上の絵に身をかがめた。
「これ、僕ですか?」
ダグラスはキャンバスに描かれた男性を見て感心しながら尋ねた。
まだ描き上がっていない部分のほうが多かったが、その男性は一目見ても輪郭がはっきりしていて、男らしい雰囲気を漂わせていた。
「どうして?違うと思いますか?」
リリーが大きく目を見開いて振り返る。
ダグラスは髪をかき上げながら答えた。
「ただ、不思議だなと思って。人から見た自分がどんな姿なのか、考えたことがなかったんですよ」
――こんな姿だったのか。少し威圧的に見える。
俺ってこんなに威圧感あるのか?と戸惑いを覚える。
ダグラスとは対照的に、リリーはゆったりとした様子だった。
腰に手を当て、肩をすくめながら言う。
「まだ顔を描いてないから、ちょっと違うんです。完成したらそっくりになりますよ?」
そうなればいい――ダグラスはそう思い、ノコギリを置いてにっこり笑った。
それは彼にとっても素晴らしい考えだった。
リリーに自分の肖像画を頼むことで、彼女と二人きりで過ごせる時間を作れるうえ、堂々と彼女の顔を見つめても不自然ではないという利点まであったのだ。
「お昼、召し上がっていってください。食べたら、私たちもすぐ出かけないといけないんですけど」
「どこへ行くんです?」
「工房です。今日、オープンセレモニーなんですよ」
「ああ、なるほど」
ダグラスの顔に理解の色が浮かび、うなずいた。
彼も聞いたことがあった――バンス夫人が新しいビヌの製造法を発見したということ。
それで工房を作り、国にビヌを供給するつもりだという噂も聞いた。
そして、既存のビヌ工房の人々が大きく反発しているということも。
「大丈夫ですか?」
「何がです?」
「その、ビヌのことです。ライバルができたみたいですね。」
ライバル?
リリーの顔に一瞬、戸惑いの表情が浮かび、すぐに消えた。
何のことか察し、彼女はかすかに笑みを浮かべて言った。
「そうじゃなくても、既存のビヌ工房側から妨害されそうになっていました。もともと工房の主人になるはずの人が別にいたんですが、その人が来られないようにされて、許可を取れずにいたんです。」
「そんなことがあったんですか?」
ダグラスの目が細められた。彼の顔つきが変わった。
ダグラスの表情に浮かんだ「よく分からない」という色に、リリーはクスリと笑った。
「大丈夫ですよ。今はアシュリーが暫定的に社長になってますし、工房のほうはあの男性が注意を受けただけだそうです」
「注意だけで済むのか?」
ダグラスの顔から、納得できない様子は消えなかった。
もちろん、その「注意」というのは関係者全員が解任され、工房からも追い出されたという意味だ。
つまり、その場所ではもう仕事はできない。
それでもリリーは、ウィルフォード氏がうまく処理してくれたと信じていたし、ダグラスも自分が工房側に異議を唱える方法はないかと考えていた。
「オープニングセレモニーなら、人も招待してるんでしょう?」
ダグラスが尋ねた。
彼が知っている「オープニングセレモニー」とは、寄付金で建てられた施設や財団が新設された際、寄付者や関係者を集めて軽い食事やお茶を振る舞うような催しだった。
だが、リリーの言う「オープン式」は、それとは違っていた。
彼女は「ああ」と短く言い、すぐに説明した。
「工房で働く従業員たちと挨拶をする場なんです。」
「そんなこともするんですか?」
「エシュリーが社長ですから。」
なるほど、とダグラスは理解した。
彼は微笑み、自分も一緒に行けるか聞こうとしたが、その前に午後に予定があることを思い出した。
ワッソン子爵夫人のティーパーティーに母をエスコートすることになっていたのだ。
彼は名残惜しそうに言った。
「次は私も招待してください。」
それは問題ない、とリリーは笑みをこぼした。
間もなくアイリスの慈善財団のオープニングセレモニーが行われる予定で、それは近隣の屋敷に人々を招いて行われるため、屋敷を掃除する使用人たちは大忙しだった。
「本当に弓を持ってきたの?」
その日の午後、工房へ向かう馬車の中で、アイリスはアシュリーの膝の上にある弓を見て、思わず声を上げた。
建物の裏で弓の練習をさせてほしいと頼んでいるのは聞いたことがあったが、まさか今日のような日に持ってくるとは思わなかったのだ。
「どうせ人に挨拶して、あとはお姉さんやお母様のお手伝いをするんでしょう?その合間にやることもないし、弓を引くつもりなの」
やることがないから弓を引くというわけだ。
アイリスは何か言いかけたが、口をつぐんだ。
貴族の令嬢が弓を引くなんてありえないと言いたかったが、アシュリーの父親はそもそも貴族ではない。
しかもバンス家には、すでにリリーという「貴族令嬢なら絶対にやらないようなことを平気でやる」人物が存在している。
「趣味があるって、いいことじゃない」
アシュリーの言葉を聞いていたミルドレッドがそう言うと、アシュリーの顔に笑みが浮かんだ。
アイリスが呆れた表情を見せると、ミルドレッドはクスクス笑いながら口を挟んだ。
「エシュリーが気に入らない人を、化粧室で刺すっていうなら止めますけど。」
「お母様!」
馬車の中には、アイリスの高い笑い声と、ミルドレッド、そしてリリーの笑い声が響き渡った。
いつの間にか馬車は首都の郊外に入っていた。
建物の前には「売り出し中」を示す看板があり、その前に人々が立っているのが見えた。
アイリスは人の数をざっと数えて言った。
「思ったより多いですね。」
人材を集めるのが難しかったわりに、工房に来た人は多かった。
アイリスの言葉に窓の外を覗いたミルドレッドの顔が歪む。
一目見ただけで、彼女が雇った人数の倍以上はいるとわかる。
紹介所で、もし一緒に働く人がいれば連れてきてもよいと言ったものの、まさかこれほどとは――。
人が多いと感じたのは、少し妙な気がした。
その違和感を覚えていたのはミルドレッドだけではなかった。
アイリスもリリーも、表情がどこか緊張でこわばっていた。
アシュリーも姉たちの顔を見てつられるように身を固くし、恐る恐る尋ねた。
「人が多いのは、いいことじゃないんですか?」
「そうなんだけど……」
そう言いながら、ミルドレッドは壁を軽く叩いて馬車を止めた。
嫌な予感がするときは、自分の直感を信じるのがいい。
彼女は馬車の扉を開ける前にアシュリーへと視線を向け、低く言った。
「アシュリー、弓を持って」
同じころ、ダグラスは母ケイシー侯爵夫人と共に、伯爵夫人主催のティーパーティーに出席していた。
「お噂はかねがね伺っております」
彼の隣に座った伯爵令嬢が、にこやかに挨拶をした。
ダグラスは、口にしかけた言葉や頭に浮かんだ考えを押し込め、微笑を浮かべた。
「できれば良い話だといいのですが。」
「まあ、とても良い話だったそうですよ。王子の師匠でいらっしゃるとか?」
「剣術の師匠です。」
ダグラスの簡潔な答えに、ワッソン夫人の表情が一瞬こわばったが、すぐに和らいだ。
その様子を見たケイシー侯爵夫人の顔には、不機嫌そうな色が浮かんだ。
――まったく、この間抜けな子。
彼女がわざわざダグラスを連れてきたのは、社交界にはリリー・バンス以外にも多くの女性がいることを知らせるためだった。
リリー・バンスのような頑固で気の強い女に時間を浪費するくらいなら、彼に好意を寄せる女性と会ったほうがいい――そう思っていたのだ。
ところが驚いたことに、息子は母の目論見を見抜いていたらしい。
――この子ったら。
この子はそんなに気が利くタイプじゃないはずなのに――。ジェネヴィーヴはテーブルの下で息子のすねを軽く蹴った。
「うっ」
ダグラスが小さくうめき、何事かと母を見た。
侯爵夫人はにっこり笑いながら言った。
「ダグラス、ワトソン嬢に王太子殿下に何を教えたのか話してあげたら?」
ジェネヴィーヴの言葉に、ワトソン嬢の表情がぱっと明るくなった。
ダグラスは困ったように母とワトソン嬢を交互に見ながら、以前リアンと交わした会話を思い出し、
リアンから褒められたことを話し始めた。
「そういえば、その話をご存じなんですか?」
ちょうどダグラスがワトソン嬢にリアンからの称賛を語っているとき、少し離れた席にいた夫人が口を開いた。
彼女はジェネヴィーヴに向かって扇を軽く動かしながら言った。
「バンス夫人がまた何か特別なことをしているみたいですね。」
「またですか?」
ケイシー侯爵夫人が興味を示すと、話を切り出した夫人が嬉しそうに続けた。
「工房を構えたそうですよ。」
「その話なら私も聞きましたわ。」
たまたまダグラスの近くにいた別の夫人も会話に加わった。
彼はワッソン夫人にリアンを褒めていたことも忘れ、夫人たちの話に耳を傾けた。
「ビヌ工房を立ち上げたそうですわ。新しいビヌの製造法を見つけたとか。」
「それは良いことですね。」
少し離れていた夫人まで加わってきた。
ジェネヴィーヴは中立的な立場を取ろうと、感情を交えずに言った。
「でも自分で工房を切り盛りしているんですって。これは礼儀を欠いた行動ですね。」
「そうですね。こんな流行が始まってはいますが、まさか事業に興味を示すとは思いませんでした。こういうのは流行になってはいけないと思うんです。」
「どうしてですか?」
ついに、母親と夫人たちの会話に我慢できなくなったダグラスが口を挟んだ。
その質問に、ジェネヴィーヴは目を大きく見開いた。
「どうしてって?どういう意味なの、ダグラス。」
「事業が流行になってはいけない理由が気になったんです。お父さまだって事業に携わっているじゃないですか。」
なんという馬鹿げた発言だろう。
ジェネヴィーヴは何事もないふりをして周囲を見回し、笑った。
「あら、この子ったらまだまだ未熟でしてね。そんな態度で事業をするなんて、流行になってはいけないと言ったんですよ。」
そう言った夫人の表情から、険しさが消えた。
ジェネヴィーヴは手を振りながら息子に言った。
「事業に関わるなんて、あり得ない話よ。」
ダグラスも以前なら母と同じように考えただろう。
貴族の夫人が事業に関わる?あり得ない。何をするつもりだというのか。
そもそも男性たちは最初からそんなことを許さないだろうし、普通の貴族夫人なら夫の財産をきちんと管理し、その収入で領地や家をしっかり維持するのが務めだ。
さらにダグラスは、これまで女性たちは邸宅を美しく整え、パーティーを開いて社交を楽しむほうを好むと思って生きてきた。
リリーに会う前に、もし誰かの夫人が事業に手を出したと聞いたなら、その夫はよほど無能なのだと考えたに違いない。
しかし今、彼はバンス夫人と会い、リリーのことを知ることになった。
「バンス夫人が直接運営しているわけでもなく、使用人が不足している今、その空いた部屋を埋めるのも悪くないと思います。」
ダグラスの言葉に、隣に座っていたワトソン夫人は目を細めた。
彼女の顔に浮かんだ「信じられない」という表情を見て、ジェネヴィーヴはできるだけ中立的に答えた。
「そういうのは男性に任せればいいじゃないの。」
「でも、バンス氏は少し前に葬儀をしたばかりですよ。」
一体どうしてこんなことを言うのか?
ジェネヴィーヴの視線もワトソン夫人を追って細くなった。
そして、目を細めたのは二人だけではなかった。
「ケイシー卿がバンス家によく出入りしていて、ずいぶん親しくなったようですね。」
「ええ、聞いた話では、あそこの次女に…そんな噂があるそうですが、本当みたいですね。」
ざわめく人々の声を耳にして、ジェネヴィーヴの心は急いだ。
彼女はダグラスに別の女性と会わせるためにここへ連れてきたのだ。
ここでダグラスがリリーに気があるという噂がさらに強まるのは困る。
彼女は素早くメアリー・ワッソン嬢に視線を向けて言った。
「ワッソン嬢、ワッソン子爵夫人から聞いたのですが、以前こちらの家に何度も招かれたそうですね。」
「ええ、叔母様からありがたいことにたびたびお呼びいただきました。」
「では、我が家の庭園をご案内していただけませんか?」
メアリー・ワッソンは、ケイシー侯爵夫人の意図を察した。
この場からダグラスを連れ出そうとしているのだ。
しかし、同時にダグラスと二人きりで話せる機会でもあった。
娘に会わせる機会も与えていた。
「そうです。」
ワトソン夫人が喜びを抑えてそう言うと、ダグラスもどうしようもなかった。
ダニエラならそんな考えはないと断っただろうが、ダグラスは、淑女をエスコートすることは紳士の義務だと教えられて育ち、今でも自分より弱い者は必ず守らなければならないと信じている男だった。
彼は母とワトソン夫人を交互に見ながら、心の中でため息をつき、立ち上がった。
「ありがとうございます、ワトソン夫人。」
ダグラスが腕を差し出して言うと、メアリーの顔に微笑みが浮かんだ。
彼女は庭のある方へと彼を案内した。
「ところで、侯爵夫人はバンス家と婚姻を結ぶおつもりはないようですね。」
ジェネヴィーヴは、少し嬉しそうに息子をメアリーと一緒にさせながら答えた。
ワッソン子爵夫人は、姪がダグラスと共に庭園へ出て行くのを見届けてから、彼女にそっと囁いた。
「バンス家の人たちは魅力的ですが、事件が絶えませんね。あの家のせいではありませんが、今回の工房の件は確かにバンス夫人の落ち度でしょう。」
「そうですね。工房だなんて、既存のギルドが黙っていないでしょうし。」
「そうでなくても、一度は衝突していたようです。」
「まあ。」
夫人の顔には呆れと興味深さが同時に浮かんだ。
他人の騒動というのは、何であれ面白いものである。
近くに座っていた人々の顔にも、その話を聞いて興味を引かれた様子が浮かんだ。
「どう思いますか、ムーア嬢?」
プリシラもその場にいた。
バンス家とムーア伯爵家が王妃の座を巡って候補者の試験をしていることを知る人々が、興味深そうに彼女へ視線を向けた。
もっとも、この程度で動揺するプリシラ・ムーアではない。
彼女はムーア伯爵家の令嬢として、常に人々の視線を浴びて育ってきた。
「私が何か言ってもいい話なのか分かりません。バンス夫人は私より年長ですから。」
以前のティーパーティーで一度恥をかいた経験もあり、彼女は自然に人々の関心から身を引いた。
どうせ黙っていてもバンス家の人々が話題に上るのだから、わざわざ出しゃばる必要はないと考えたのだ。