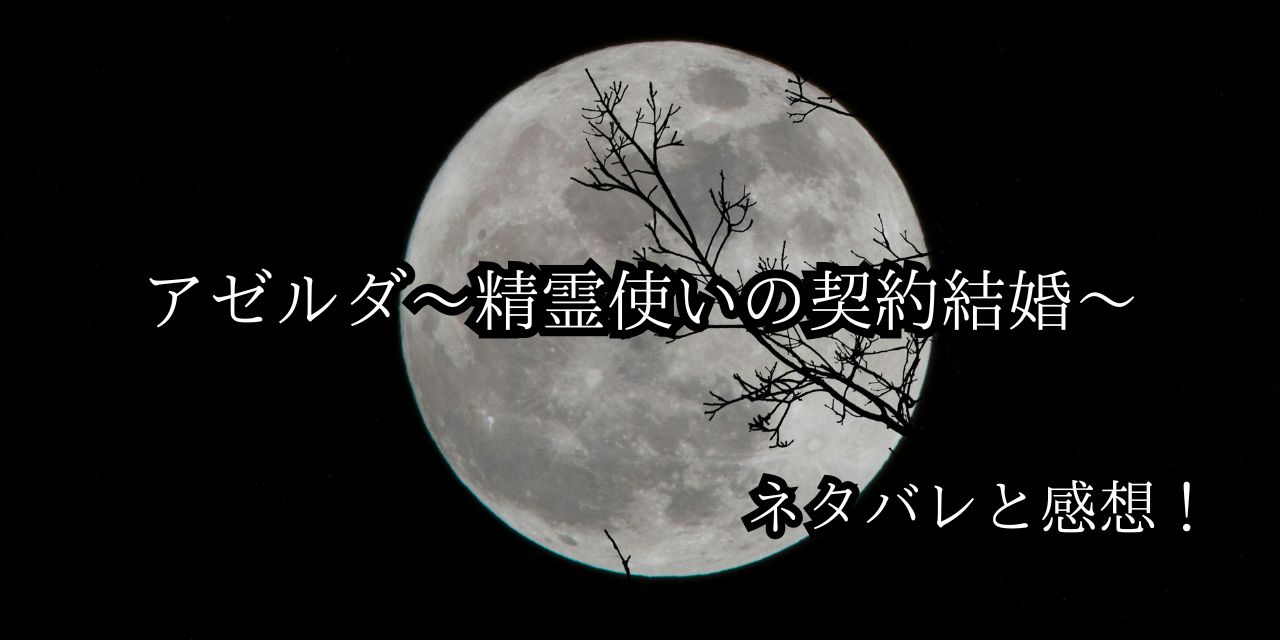こんにちは、ピッコです。
「アゼルダ~精霊使いの契約結婚~」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

34話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 友達②
簡素で質素な服を着て王城に到着したときには、ちょうど夕食の饗宴が始まる直前だった。
客室はきれいに整えられていた。
アゼルダは長く置かれていたソファに腰を下ろし、ため息をついた。
なぜか親しみを覚えたのか、ブユも彼女が勧めると遠慮せずに、寄り添うように隣に座って一緒に水を飲んだ。
彼女は、北部の人々がこのように不要な礼節を重んじて身分の違いを厳しく区別する文化がないことを、とても好ましく思った。
貴族と非貴族、そして貴族の中でもさらに身分を細かく区別することにより、治療用義肢が広く流通していても、ある場所ではそれすら手に入らず、足を切断せざるを得ない状況が起きている今の首都の状況を招いているのかもしれなかった。
もし、自分が救済院に通っていたことが他の貴族たちに知られたら、本当に叱責されるに違いないと思った。
それは本当に正しい選択だったのだろうか?
いや、間違いなく正しい選択だった。
母が知っていたら、間違いなく「よくやった」と言って彼女を抱きしめ、褒めてくれたはず。
誰の前でも堂々と胸を張って誇れること。
間違いなく、良いことだ。
それが今後どんな波紋を呼ぶとしても、前世では起きなかったことが起こるかもしれないが、それでも行動を抑えて慎重に構えるよりは、思い切って動く方が自分にとって正解なのだろう。
同じ状況に戻ったとしても、きっと同じことをするだろう。
黄金の通りが封鎖されていたせいで、自分が治療用の器具を大量に購入したことが外部に漏れるとは思っていなかったが、公爵と会う前にその話は一応しておくべきだと考えた。
ブユが水を二杯、冷たく飲み干してコップを置きながら話し始めた。
「ふぅ、なんとか慌ただしく戻ってきましたね。」
「うふふ、ですね。本当に急いで戻りました。公爵様は?」
「まだ会議が終わっていないそうです。どうやら話が長引いているようですが……。王太子さまがこんなふうに会議を長引かせて良い結果になった試しがありません。」
ブユを慎重に扱わなければ、首が飛ぶような目に遭うだろうと思ったアゼルダは、口を開こうとしたその瞬間──
トントン。
控えめなノックの音の後、侍従が入ってきた。
「ははは、こんにちは。」
彼女がややオーバーに挨拶をすると、侍従はブユの言葉を聞いていた様子はなく、淡々と挨拶を返した。
「ご機嫌よう、カルロス公爵夫人。ご不便はございませんか?」
「はい、とても快適で……ベッドも素敵です。」
「ちなみに、姫さまが公爵夫人に――おひとりで夕食を取られると思うと、心が落ち着かないとおっしゃって、夕食の宴にご一緒されませんかとお招きになりました。よろしければ……」
「公女様がですか?」
驚いて声を上げたのはアゼルダではなく、ブユだった。
ブユは自分でも気づかないうちに声を上げてしまったことが恥ずかしかったのか、それとも首都の格式ある会話に自分が入り込むのは無礼だと感じたのか、そっと口を閉じて座り直した。
しかし、彼がそれほど驚くのも無理はなかったため、アゼルダも侍従も彼を十分に理解した。
ブユは答えを迷いながら侍従を見つめた。
本当に驚くべきことだと言わざるを得なかった。
それもそのはず、公女は元々社交の場を避けることで有名だった。
自分の誕生日という名目がなければ、宴会場にいることもなかっただろう。
必要があれば踊りもこなすが、貴族たちと話すことに特別な関心を示したことはなかった。
気まずさを感じさせず自然に振る舞っていたが、皆の前に出る機会はそれほど多くなかった。
しかも姫様は、公爵様を見るたびに極端に緊張してしまうほど、昔から距離を置いていた方だ。
普段は親しい交流さえ極力避けるというあの控えめな方が、誰かを食事に誘ったと聞いて驚いたが、それが北部の公爵夫人だというのか?
あの侍従の気配りと自分の知る限りでは、公爵夫人と姫様は明らかに昨日の晩餐会で初めて出会った間柄のはずだった。
それが本当なら、まさに驚愕の出来事だった。
アゼルダは、侍従とブユがあまりに驚く様子に、かえって自分は落ち着いてくるような気分だった。
そして姫様のことに関しては、生涯驚かされっぱなしになるだろうという思いで救済院から戻ってきたばかりだった。
「姫様がお招きくださったのなら、ぜひ伺います。」
「前菜はほぼ準備が整っておりますので、お早めにご準備のうえ、お越しいただければ幸いです。」
「ええ、もちろんです。前菜が冷めないうちに参ります。」
彼女は王城内で着るために用意していたドレスの中から適切なものを選び、急いで身支度を整え、侍従の案内に従って食堂へと向かった。
食堂は彼女が滞在している部屋の二階下に位置していた。
さすがは王宮とあって、壁一面には装飾された草花模様や装飾構造、精巧に織られたタペストリーが飾られており、それらの間を通り抜けてようやく食堂にたどり着くことができた。
こんなに大きな扉が必要だろうかと思うほどに巨大な、彼女の背の二倍ほどもある扉が目の前に現れた。
白と赤、そして金色で華やかに装飾された扉を、侍従が開いてくれた。
三十人ほどは余裕で囲めそうな長テーブルに、公女はたった一人ぽつんと座って扉の方を見ていた。
どうして一人で?
広々とした部屋、巨大なテーブル、赤いテーブルクロスの上の広い空席。
それらすべてがアゼルダを見つめていた。
笑っているコチータ姫がさらに小さく見えた。
アゼルダは、この部屋に彼女が一人で座っていることに驚き、顔が強張るのを感じた。
それがまるで、招待されたことを名誉に思い、その感謝を表すためにドレスの裾をつまみ、丁寧に挨拶をした。
「お待たせしてしまい、申し訳ありません。」
姫は厳かな表情で頷きつつも、どこかいたずらっぽい気配がかすかに見えるのをアゼルダは見逃さなかった。
「まあ、あなたは急いで招かれた方ですから、光の速さで来るわけではありません。気にしないで、さあ座って何か食べましょう。」
「恐縮です。」
「ふふ。晩餐会でお会いして、またこうしてお会いできてうれしいです、公爵夫人。女性同士、少しお話でもしましょう。」
薄い金髪の下から覗く姫の幼い顔がにこやかに笑った。
晩餐会で会って、今が二度目の再会だった。
それに、途中で別の場所で話したことについて口外しないようにという言葉はなかった。
あの公女の兄に対しては非常に強い嫌悪感を持っていたが、その血を分けた肉親であるコチータ公女に対しては、簡単に憎むことができなかった。
どこか甘さのある構成をしていて、初めて会ったときからこびりついていた固定観念を少しずつ変えてくれた、柔らかな人物だったからだ。
アゼルダが公女の示す方へ近づいていくと、侍従が彼女が楽に座れるよう椅子を引いてくれた。
間もなく食器類が整えられ、スープと羊肉のポトフをはじめとした前菜が並べられた後、侍従たちは扉を閉めて退室した。
アゼルダは慎ましく料理人や侍従が出入りする北部の食事時間をふと思い出し、あまりに静かなこの空間の雰囲気に戸惑って、公女を見つめて言った。
「普段からこんなにプライベートな空間で食事をなさっているのですか?」
「私は人が来るのがあまり好きじゃないの。噂で聞かなかった? 私は“慎ましい姫”だから。」
慎ましい姫は、自分のことを「慎ましい姫」と誇張して言うわけでもなく、周りに人が集まっても急に馴れ馴れしくなることもなかった。
アゼルダはくすっと笑いながら、姫にならってスープをひとさじ口に含んだ。
宮廷の料理といえど、さほど期待はしていなかったが、バターがたっぷり使われているのか、トマトスープはとても甘くてまろやかに口の中を満たしてくれた。
「うわ、こんなに美味しいなんて思いませんでした。」
「ふふ、宮廷で自慢できるのは料理人だけよ。」
まあ、それも納得。
ブユに匹敵するほど味にうるさい姫なのだ。
アゼルダは、しっかりと閉ざされた扉のある食堂の時間が、何人かの安全に役立つだろうと思いながら、ひとり心の中で「人が来ない空間」について思いを巡らせていた。
公女は彼女が何も言わずにスープの入った器をきれいに空け、ポトフを器に移そうとしたのを見て、気まずくなったのか先に口を開いた。
「なんでこんなに人がいないのか、聞かないの?」
公女のその言葉がなぜか拗ねたように感じられて、アゼルダは思わず笑ってしまった。
「聞いた方がいいですか?」
宴だって呼んでおいて、こんなに人がいないじゃない?
それを聞けば何か失礼に当たるような気がして、アゼルダはため息をつき、ポトフを取ろうとしていたスプーンをそっと置いた。
「どうして宴なのにこんなに席が空いてるんでしょうか?スープはこんなにおいしいのに。」
「質素すぎて不満なの?」
アゼルダが青い光を宿した瞳をぱちぱちと瞬かせると、公女は真剣なふりをしていた顔をすぐに崩し、声を抑えて笑った。
「もともと予定していたのはこれじゃなかったんだけど、どうやらこちらに招いた三人の令嬢のうち、突然体調を崩された方がいたみたい。退屈な話よね?」
退屈?
アゼルダはどのあたりが退屈なのか考えながら、肉料理を口に運んだ。
「これは……本当に美味しいです。羊肉ですか?これ?」
「私が美味しいって言ったでしょ?」
「うわ……」
もともとこんなに美味しい料理だった?
目の前に整然と並べられた食事用のフォークとナイフ、スプーンなどを見ても、これからさらに十数種類の料理が出てくる気がしたが、彼女はスプーンを手から離すことができなかった。
どうやら濃厚な肉のスープのおかげで、こんな深い味が出ているようだった。
姫は、彼女が会話を少し避けていると思ったのか、他の令嬢たちの話を持ち出し、料理の話題へと自然に切り替えた。
「ふふ、あなたがそんなにおいしいって言うから、北部の味覚がぴったりだって感じちゃうじゃない?」
「はい、北部にもおいしい料理はたくさんありますよ。ただ……こうやってバターをたっぷり使うタイプではないですけど。」
「そう? でもね……」
公女は彼女が食事を十分に楽しむのを待ってから、スプーンを置いて彼女のほうに身を寄せた。
「ここって私たち以外いないけど、ずっと敬語で話すつもり?そんなふうに出るなら……」
まさかあの救済院の前での脅しが続いているのか。
アゼルダは「支援金を減らす」と公女がまた言い出す前に、両手を挙げた。
彼女は手に持っていたスプーンまで見せながら、明確な降伏の意を表した。
アゼルダは少し砕けた口調で言った。
「なんでこんなことするの、友達じゃん。」
公女はまた声を立てて笑った。
「ぷはははっ、それ知ってる?あなた、本当に面白いのよ。」
「え?」
「うん。友達がいなかったから、誰かに笑ってもらったこともないの。知ってる?」
言葉を返せずにいると、コチータ姫がふっと笑ったが、彼女の言葉に一瞬で表情が曇った。
「友達がいなかったの?」
そう言われてみると、一緒に笑ってふざけたり、獣を狩りに行くときに付き添っていた傭兵たちや、たまに滞在する北部公爵邸の傭兵宿舎でたむろしているシェイドを見たとき、まるで友達のように感じたこともあった。
しかし、「アゼルダにまったく友達がいないわけじゃない」と言い訳するよりも早く、コチータ姫がそっと彼女の手を握った。
「いるじゃない、アゼルダ……。私が……さっき戻ってくるときに考えてたんだけど。」
「うん?」
「実は……あなたのお母さん、覚えてるの。私が幼かったから、ほんの少ししか覚えてないけど。」
まるで心がじんわりと溶けていくような感覚は、一瞬にして吹き飛んだ。
食事の味など、もはや重要ではなかった。
「私の母のこと?」
「うん。あなたのお母さんとお父さん……名前は何だったかしら?とにかくマディスンガに王城を訪れるたびに会っていたの。特にあなたのお母さんのことは、今でもよく覚えているわ。整霊術を使う人って多くないから、幼い私の心にもとても神秘的に感じられたの。優しくて、美しくて、強い人だったってことを覚えている。」
アゼルダは、目に涙があふれそうになるのを必死でこらえた。
まるで母を覚えている人が誰もいないかのように、人々は母の話をしなかったのだ。
「お母さんの話、ほんとうに久しぶりに聞いた。覚えていてくれてありがとう。」
「ううん、私のほうこそありがとう。あなたのお母さんは、人を怖がる私にたくさんの優しさをくれたから。」
「なんで怖がってたの?」
「さあ、なんでだろう……」
コチータ姫は自分から話を切り出し、困ったような顔で両頬を手で覆った。
話すべきかどうか迷っているような目つきだったが、その琥珀色の瞳に強い意志の光が浮かんでいた。
「さっき招いた令嬢たちが体調を崩したって話、覚えてる?」
アゼルダはグラスを持ち直した。
「あなたに話したいの。私のことを大事にしてくれる人たちは皆、遠くへ左遷されるのが常だから、人が怖いの。こういう話……あなたにしても大丈夫?」
アゼルダは扉をちらりと見つめた。
そんな様子に気づいたコチータ姫は、気を使わないでというように手を差し伸べた。
「私があらぬ噂を立てられる前に料理を出すわけがないでしょ。心配しないで。」
「わかった。でも……すごく重い話だから……」
コチータ姫はかすかに笑った。
「そのつもりで呼んだんじゃないのにね。重かった?」
「いいよ。お母さんと関係ある話なら、何でも話して。」
「うん。実は救済院での出来事が衝撃的すぎて、あなたと少し話したかったの。あなたに友達がいないって聞いて……なんだか全部、自分のせいな気がして。話さなかったら、私がすごくケチみたいじゃない……って。」
コチータ公主が話す内容が何のことか、アゼルダには分かるようで分からなかった。
「何の話か、全然分からない。」
「私にとっては、政治的な勢力とか、そういうのは本当に何もないし、関わることもないの。でも、血の供物として選ばれるドラゴンの守護者を選んだのも、あなたのお祖父様でしょ?だから誰かを警戒する必要も、境界線を引く理由もないのよ。そうあるべきなの。」
「うん。」
「でも、それが私の心の思うとおりにはいかない。」
「公主様?ううん、コチータ。だから、あなたは今……」
「うん。私は……君のご両親がひどい目に遭ったのは私のせいだと思ってる。私が無鉄砲にあの方々について行ったせいで。」
爆弾発言もこれほどのものはなかった。
続けて姫は、自分の兄が公主(王女)の勢力を警戒し、公主の味方をする人物には即座に警戒、もしくはひどければ攻撃までしてきたのだと語った。
それがアゼルダの母や父にも及んだかもしれないと。
公主を慕った、あるいは公主の味方をしたせいで、災いを被ったのかもしれないと。
でも、いったい何のために?
王太子はすでに摂政の座を得て権力を振るっていたのに、正式な後継者にまで指名された。
その理由が分からない。
とんでもない話だと思った。
けれども、アゼルダはすぐに思いを改めた。
王太子が何を思ってそのようなことをしたのかは分からないが、母と兄を死に追いやろうとしたのは紛れもない事実だ。
ルバンテと王太子、そのどちらもがそう望んだのだ。
冷酷で残酷で、人の命を奪って遊ぶような連中が何を考えているのか、もっと知る必要があった。
もしコチータ公主の言葉が本当なら、彼女の話には一理あるはずだ。