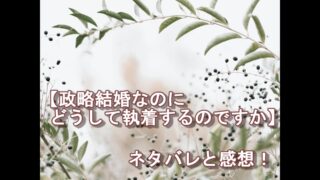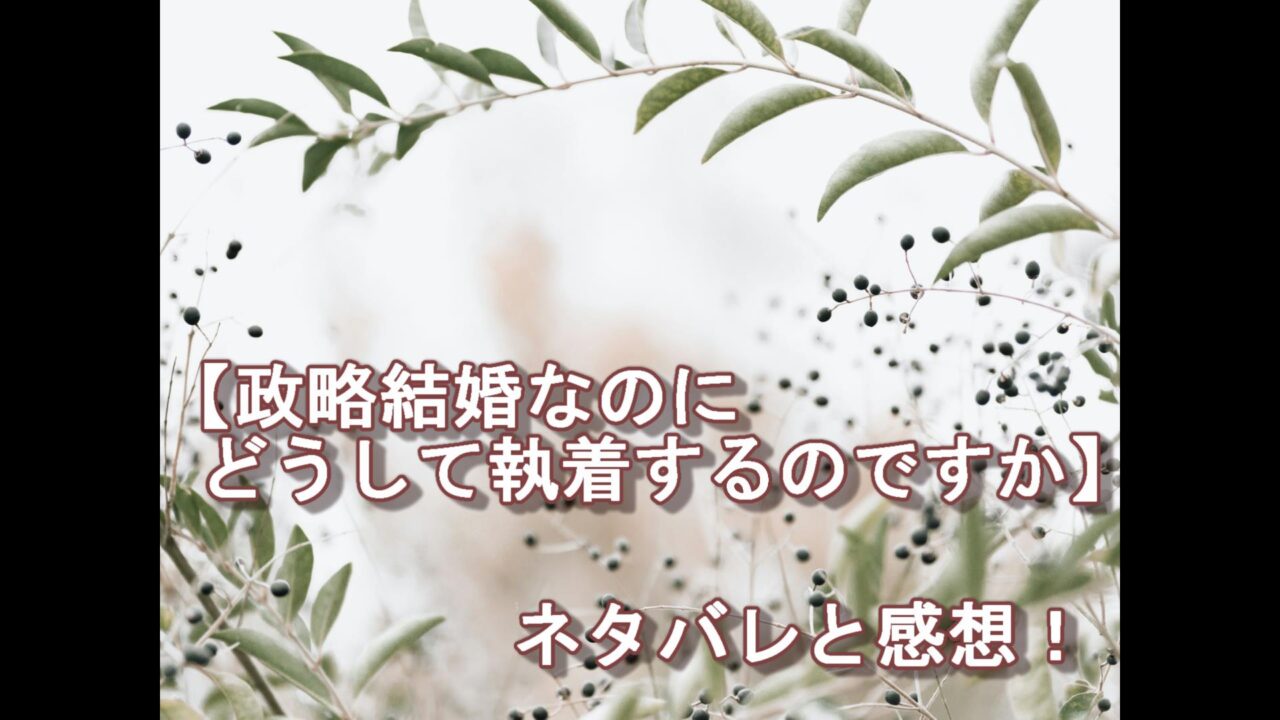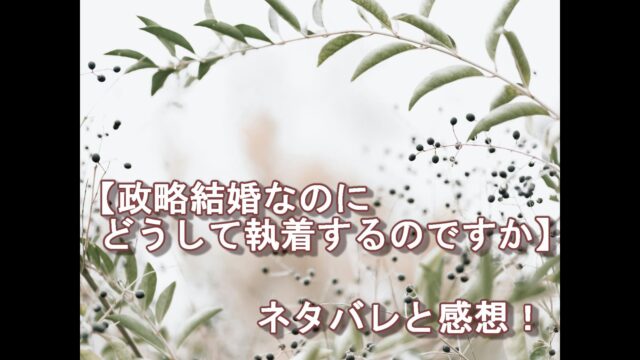こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

101話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 罠②
木の箱の中で、じっと目を開けた頭部が横たわっていた。
まさに今朝まで戦闘を繰り広げていたポルトゥナ伯爵のものだった。
グレンは落ち着いた様子で箱の中を眺めた後、ふたを閉めながら命じた。
「遺体はきちんと収めておき、希望があれば見せてやるように。」
「はい。」
衛兵が腰をかがめて壁の中に隠れ、箱を持って出て行った。
グレンは簡易ベッドに腰を下ろしながら考えた。
『これで三連勝か……。』
勝利の要因は、ウィンターフェルが戦争の準備をしていたからだということだ。
彼はまるで近い未来に起こるであろう戦争を予見して、力を蓄えてきた人物のように思い浮かべた。
その人物こそがナディアだ。
もし彼女が北部へ訪ねてこなかったならば、今日のような容易な勝利は果たして可能だっただろうか?
「絶対に無理だったはずだ。」
そう思うと、彼女が自分を選んでくれたことがどれほど幸運だったか分からない。
彼は今ごろ後方にいるであろうナディアの姿を思い浮かべていた。
「侯爵様、奥様から書信が届きました。」
思いがけずもたらされた知らせに、グレンは思わず体に染みついた幻聴かと思っていた。
それが幻聴ではないと気づいたのは、伝令が入口のカーテンを開けて中に入ってきたときだった。
「侯爵様、奥様からのお手紙です。」
「ナディアから?」
彼女が本当に手紙を送ってきたのか?
彼は思わず身を起こした。
「まさか後方で何かあったのか?」
「よく分かりません。他には何もおっしゃっていませんでした。」
会いたかったあの人から手紙が届いたということに、彼はただ素直に喜ぶことはできなかった。
この時期に軽率に夫人が会いたがって使者を送ってきたとは思えなかった。
グレンはやや緊張しながら封筒を開けた。
「……?」
中から見覚えのあるペンダントが一つこぼれ落ちた。
彼はそれが何なのか一目で分かった。
まさに自分がドワーフに託して作らせたペンダントだったのだ。
『これを、なぜ……』
封筒に入っていたのは首飾りだけではなかった。
短い手紙が同封されていた。
「長い間気づけなかったことを残念に思わないで。無事に戻る日、そっと答えるから。」
その意味を理解するのに少し時間がかかった。
いや、直感的に思い浮かんだ意味があったが、信じられなかった。
本人から直接聞かない限り、信じることはできないと思った。
グレンは震える声で尋ねた。
「これ……本当にナディアが直接書いたのか?」
「はい、私が直接侯爵夫人から受け取ったものです。何か問題でも?」
「いや、いい。もう行ってくれ。」
「はいっ。」
使者は何も言わずに足音を響かせて出て行った。
一人残されたテントの中で、彼は何度もその手紙を読み返した。
特に二文目を──。
これはまるで……手紙を受け取った者の気持ちに応じる、という意味ではないのか?
信じられず何度も見返してみたが、ナディアの筆跡に間違いなかった。
興奮とときめきが収まらず、彼はまさに部屋の中をぐるぐる歩き回らなければならなかった。
ベッドの上に座ったかと思えば、机の前に行き、出入り口まで歩いて行ったかと思えば、またベッドに戻る、ということを繰り返していた。
事情を知らない者が見たら、気が狂ったと誤解しかねないような光景だ。
いや、もしかすると本当に正気を失っていたのかもしれない。
儀式を放り出してでも彼女のもとへ駆けつけたいという思いが湧き上がるのを感じるのだから。
今すぐにでもナディアのもとへ戻って、この手紙の意味を聞きたい。
彼女と自分の気持ちが同じなのか確かめたかった。
しかし、刃のように残った理性と総司令官としての責任感が彼の足首をつかんでいた。
グレンがまだ静まらない胸を押さえながら呼吸を整えていた時だった。
「領主様。休憩中に申し訳ありませんが、少しお時間をいただけますか?」
テントの外から聞こえてきた声は副騎士団長ヨハンのものだった。
彼がつまらないことで休憩を邪魔するはずがないと知っているグレンは、すぐに入室を許可した。
一度目の前の敵を片付けてこそ、ナディアの元に戻れるのではないか?
「どうした?」
「他でもなく、ポルトゥナ伯爵の軍に潜入させていた間者が戻ってきたのです。」
ヨハンはそう言いながらグレンの前に歩み寄った。
「話してみろ。」
「亡くなったポルトゥナ伯爵の後任に座る者は、後爵様もよくご存知の人物のようです。実際、タクミ卿に決まったそうです。」
「驚くに値しない人事だ。実は以前から彼が前線に出てこないのは不思議だな。」
「異邦人という出自が足かせになっているのではないでしょうか?南部の貴族たちは我々よりもずっと保守的な面がありますので。」
「ふむ。」
グレンは顎を撫でながら思案にふけった。
『無口で、だから何を考えているのか全く分からない男……。』
ひとつ確かなことがあるとすれば、それは彼がナディアに対して何らかの思惑を抱いているということだ。
どうにも嫌な予感がする。
そして戦場では勘が時に大きな危機を避ける助けとなるものだ。
『とりあえずナディアに警告しておいたほうが良さそうだ。』
決心したグレンは執務室の中で紙とペンを取り出した。
その日の夜、彼の手紙を携えた伝令が北へ向かった。
・
・
・
「何だって?城壁のそばに南部軍が現れただと?」
「はい、バラジット家の紋章の軍靴が確認されました。」
哨戒兵から初めてそのような報告を受けたときジスカールが最初に感じた感情は「呆れ」だった。
驚きではなく、呆れだった。
『こんな時にここに来るなんて……?』
信じられなかった彼は城壁の上に上って、自分の目で直接確認しなければならなかった。
地平線の向こうから細かな砂埃が上がっていた。
敵軍が押し寄せてきている証拠だった。
彼は息を呑みながら凍りついた。
「本当だな。」
「憲兵の報告によると、バラジット公爵家の紋章が見えたとのことです。公爵家の軍ならば予備兵のはずですが、この時期にどうしてここへ向かったのでしょう?ここはまったく要衝でもないのに。」
「だからむしろ虚を突こうとしているのかもしれない。防備が手薄なところを狙って、弱い場所を攻めようという考えだったのかもしれない。」
実際、それなりに理にかなった判断だ。
兵力の大半はすでに抜けており、農耕を補うには食料もあまり十分とは言えなかった。
地平線を見つめながら考え込んでいたジスカールに、副官が尋ねた。
「どうなさいますか?」
「ひとまず見送る。」
「えっ、本気ですか?」
副官の目が見開かれた。
普段から好戦的なジスカールの性格を思えば、意外な返答だった。
「これだけの兵力がここまで来たというのは、他の場所ではその分の兵力が減ったということです。ならば我々はここで水路で補給を受けながら長く持ちこたえるのです。わざわざ彼らの思惑通りに城門を開けて戦う必要はありません。」
「なるほど、そういう意味でしたか。」
「ただし、近くの野営地から水と兵力を少し支援してもらうのが良いでしょう。近くの場所に連絡を送るように。」
こうしてその夜、闇に紛れて伝令たちが城を抜け出した。