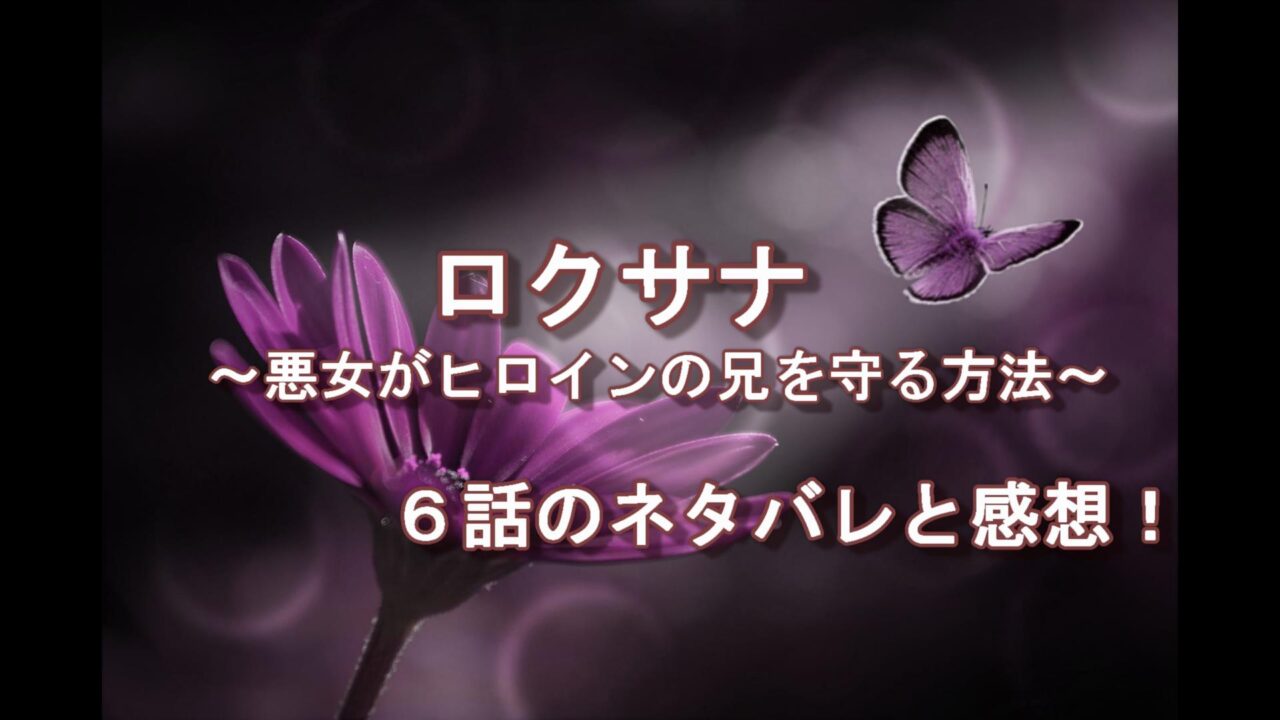こんにちは、ピッコです。
「ロクサナ〜悪女がヒロインの兄を守る方法〜」を紹介させていただきます。
今回は6話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

どういう訳か小説の中の悪の一族、アグリチェ一家の娘「ロクサナ」に生まれ変わっていた!
アグリチェは人殺しをものともしない残虐非道な一族で、ロクサナもまたその一族の一人。
そして物語は、ロクサナの父「ラント」がある男を拉致してきた場面から始まる。
その拉致されてきた男は、アグリチェ一族とは対極のぺデリアン一族のプリンス「カシス」だった。
アグリチェ一族の誰もがカシスを殺そうとする中、ロクサナだけは唯一家族を騙してでも必死に救おうとする。
最初はロクサナを警戒していたカシスも徐々に心を開き始め…。
ロクサナ・アグリチェ:本作の主人公。
シルビア・ペデリアン:小説のヒロイン。
カシス・ペデリアン:シルビアの兄。
ラント・アグリチェ:ロクサナの父親。
アシル・アグリチェ:ロクサナの4つ上の兄。故人。
ジェレミー・アグリチェ:ロクサナの腹違いの弟。
シャーロット・アグリチェ:ロクサナの妹。
デオン・アグリチェ:ロクサナの兄。ラントが最も期待を寄せている男。
シエラ・アグリチェ:ロクサナの母親
マリア・アグリチェ:ラントの3番目の妻。デオンの母親。
エミリー:ロクサナの専属メイド。
グリジェルダ・アグリチェ:ロクサナの腹違いの姉。
ポンタイン・アグリチェ:ラントの長男。
リュザーク・ガストロ:ガストロ家の後継者。
ノエル・ベルティウム:ベルティウム家の後継者

6話 ネタバレ

登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 血の匂い
それほど長い時閻はかからなかった。
「シャーロット、私はね。テーマを把握できない子が嫌いなの」
私は静かに泣き言を言いながら手の血を何気なく払いのけた。
白い廊下にかすかな赤い液体が私の手について飛ぶ。
「どうせ勝てないのに、どうして飛びかかって人に迷惑をかけるの?」
シャーロットを相手にするには、頭を飾っていたピンで十分。
宝石がちりばめられた5本のピンを全部使ったら、完全にほどけてかき分けられた長い髪が私の肩と背中の後ろを覆っていた。
シャーロットはさっきの猛々しい勢いを一服して血を流して私の前に倒れている。
私は彼女を踏んでいる足にそっと力を入れた。
「シャーロット.私が欲しいおもちゃを1つ手に入れるのに、あなたの許可を得る必要があるのかしら?」
「私が・・・、お姉ちゃんの年になればもっと強くなるよ」
可愛い顔で、殺伐と呟く言葉を聞いて、私は、ふうと低い声で笑った。
その音を聞いたシャーロットは一瞬身をすくめる。
こういうのを見ると、私を全く怖がらないわけではないが、ある意味では根性があると表現しなければならないのか。
「そうね、そういうこともあるだろう。今のところはよく分からないけど」
私は何気なく詠んだ後、シャーロットの体から足を離した。
「姉ちゃん、この子は私が処理するから先に行って」
壁にもたれて私たちの姿を観戦していたジェレミーが近づいてきた。
私はしばらく二人を交互に見て、すぐに彼の言う通りに先に席を離れる。
・
・
・
ロクサナが廊下を完全に出た後、ジェレミーは冷たい覗線でシャーロットを見下ろした。
彼女は体を落ち着かせ、よろめきながら席から立ち上がる。
その瞬間、ジェレミーの足がシャーロットに躊躇うことなく吹き飛ばされた
パァッ!
肩を蹴られたシャーロットが再び床に倒れる。
「本当に、姉ちゃんはとても優しいんだから。こんな生意気な女のをこれくらいまで見てくれて」
ジェレミーはシャーロットに近づき、かがんだ。
そして、彼女の乱れた髪をつかんで頭をもたげた。
シャーロットは反抗的な目でジェレミーを睨みつけている。
ジェレミーはそれを見て舌打ちをした。
必妻以上に傷つけず、急所だけを攻撃して相手を効率的に制圧したのがさすがにロクサナらしかった。
もちろん、かなり実力の差が大きくなければ、大きな負傷なしに戦いを終結させるのがむしろ難しいものだ。
シャーロットはこのような度にロクサナと自分の実力の差が目立ち、さらに自尊心が傷つくようだったが、ジェレミーが考えるにはロクサナが寛大すぎるようだった。
「ちっ。ただでさえ星のようなやつのせいでイライラするんだけど、あなたまで怒らせる?」
ジェレミーが青白い眼光を放ち、ぞっとするほど鋭くー喝すると、そのときシャーロットはぎょっとして目を見開いた。
「私が何をそんなに間違ったと・・・」
「お前なんかが姉ちゃんに喧嘩をしたのが、それじゃ間違いじゃないの?」
「お兄さんはいつもロクサナの味方ばっかりしてるよね?今回のおもちゃもそうだよ。私がどれだけ気に入ったか知っているくせに!」
シャーロットは憮しそうに叫んだが、ジェレミーは目も動かずに握っていたシャーロットの髪の毛を押すように放した。
些繍なことを扱うような誠意のない手つきで。
「腹いせをしようと思ったら地下にいるやつに行ってやれ。これは全部私のテーマも知らずに、姉ちゃんの前でうろうろして目についた、あいつの過ちだから」
そう言っているうちに、もう一度いらいらしてジェレミーは悪口を言った。
今回のおもちゃから手を引くと、この前ロクサナの前で言ったのでなければ、青の貴公子か何かというその子を今すぐ締め付けてしまうのだが。
「そう、考えてみたら本当に全部あの青の犬のせいだね」
ジェレミーは、今も地下に閉じ込められているカシス・ペデリアンに向かって殺意を感じながら歯軋りをした。
「青の犬?」
「あれ、カシス・ペデリアンだって」
まさにその瞬間、シャーロットの目からばっと炎が起きた。
彼女も今回のおもちゃの正体がぺデリアンだったという事実を今初めて知って、少なからぬ衝撃を受けたようだった。
その直後、シャーロットの目に浮かんだ感情を見て、ジェレミーは彼女を利用することに。
そう、自分が直接触れることができないなら、他の人に代わりに頼めばいいんじゃない?
「残念だ。あれは本当にあなたの好みだったと思うけど」
からかわれたジェレミーの言葉にシャーロットは唇をかんだ。
「だけど、仕方がない。おもちゃはたった一つだけだから」
彼は向かい合った顔から溝き立つ強烈な貪欲と怒り、そして嫉妬を読みながら生臭く笑った。
「君が持てないからといって壊すわけにもいかないし。そうじゃない?」
「血の匂いがするね」
ジェレミーとシャーロットを置いて引き返したロクサナは、地下牢に向かった。
彼女が中に入ってきた時から注意を払っていたカシスが突然口を開き、鋭く詠んだ。
その音を聞いてロクサーナはびくっとする。
彼が言ったように、今彼女の手と服には血がついていた。
先ほど廊下でシャーロットを相手にする時についた血が。
しかし、その匂いを嗅ぐなんて。
普通の嗅覚ではない?
ロクサナは微妙な気分を感じながらカシスを見上げた。
「大したことないわ。あなたは気にすることはない」
彼女の適当な答えにカシスは眉をひそめる。
しかし、彼には率直に話すことはできなかった。
妹と喧嘩してこんなに血を見たと言ったら自分をもっと警戒するだろう?
しかもその血が彼女本人のものでもなく、相手のものだとすればなおさら。
だからといって、他の理由を言い繕うのはまた面倒だった。
どうせカシスは今、目もまともに見えないから、そのまま見過ごしても構わないだろう。
こうなると分かってたら、部屋に寄って血も拭いて、服も着替えてきたのに。
そう思いながら、ロクサナは口を開いた。
「私はしばらく来られないと思う」
ロクサナの言葉にカシスは答えず、目の前にいる人を眺めた。
2人がこのようなやり方で地下監獄の中で会ったのも、今やその回数がかなり増えている。
昨日よりもっと明るくなった覗界にか弱い少女の形が映っていた。
いまだに全てがぽやけていて、やっと顔と体の輪郭が見える程度だが。
それで、この血の匂いの原因が正確に何なのかも分からなかった。
「そんなに長くはないけど、ほんの数日ぐらい」
もしかして、自分の名前を「ロクサナ」と名乗るこの少女がどこか怪我をしたのだろうか?
カシスは彼女のことを心配する立場でもないし、そんな関係でもない。
しかし、嗅覚を剌激するこの濃い血のにおいの持ち主が、目の前にいるこの幼い
少女だと思うと、なぜか少しは紳経が尖っている感じだった。
もしかしたら、たとえその意図はまだ疑わしいとしても、少女が他人の目を避けてこっそりとカシスを助けようとするという事実そのものだけはこれ以上否定しにくいからかもしれない。
カシスは目の前にいる人の様子をうかがうように覗線を置いた。
目が見えなくて状況を直接的に把握できないということは非常に不便なことだ。
「だから、また会えるまで元気でね。私がいない必要な時にあなたを助けてくれる人がいないから少し心配だけど」
いつものように物静かな声。
カシスはどうでもいいと言うように冷たい視線を他のところに向けた。
でも次に会ったときは今前にいる人の顔を見られたらいいなと、心の中でそう
思った。
・
・
・
2日後、私はシャーロットが地下牢を守っていた牢番を倒し、無理やりその中に入ったという話を聞くことになる。
それでも足りず、シャーロットはカシス・ぺデリアンを攻撃して傷つけたという。
「ふーん、やっぱり予想通りね」
シャーロットは大晩餐会の日におもちゃを所有している問題で私に飛びかかって、結局無残にも敗北した。
カシスを得ることもできず、私に武力でやられることさえあったので、シャーロットの性格上じっとしているはずがなかった。
それにジェレミーが隣でシャーロットに風を吹き込んだこともあるだろう。
あの日、晩餐会場から出てきたジェレミーの気分が低調に見えた時から、これから続く彼の行動をある程度察していた。
そのような中でジェレミーが私を先に送ってシャーロットと二人きりで残ろうとさえしたので、その後のことを予測できないはずがない。
初めてカシスを運れてきた時、私たちの父親であるラント・アグリチェはしばらく決定を保留し、私たちにしばらく誰も彼に触れないように命じた。
だからいくら怒りに目がくらんだシャーロットだとしても、父の命令に正面から惚れて廃棄処分されたくないなら、カシスを殺せるはずがないなかった。
だから、シャーロットはどうせ食べられないなら、剌してみようという気持ちでカシスに触れたのだ。
しかし、それにしてはカシスの負傷程度が思ったより軽微だった。
少なくとも手足の一つくらいは使えなくなるかも知れないと思ったが。
シャーロットが私の予想よりもっと気を使ったのか。
私は少し残念だと思って、視線を伏せた。
「それにシャーロット様が捕虜の拘束口を破壊し、逆攻撃されそうになったそうですね。そのことまで追加され、加重処罰を受けることになると思います」
「え?」
続くエミリーの言葉に私はティーカップを持った手をびくびくさせてしまった。
これはまだ予想できなかった状況だ。
他でもなく耐久性に優れていることで有名な大魔物用の拘束具をシャーロットが、しかもカシスを攻撃していて単純なミスで壊してしまった?
「面白いわね」
そんなはずがない。
カシス・ぺデリアンが何かトリックを使ったのは明らかだった。
シャーロットが多少軽率で多血質なのは事実だが、よりによってそのように偶然な
瞬間にミスをして拘束具を壊すとは、ありえない。
私の考えではそうではなく、カシスがわざと巧みにシャーロットを利用したと思う。
もちろん私が彼を過大評価しているのかもしれないが、こう見えても彼は青の貴公子というニックネームまで持っているぺデリアンの後継者。
ヒロインのお兄さんというタイトルを除いてでも。
私はテーブルの上にティーカップを静かに置く。
どうやらカシスにはもう少し時間が経ってから立ち寄ってみるのがよさそうだった。
「姉ちゃん、シャーロットの話聞いた?」
「地下牢のことなら聞いたわ」
ジェレミーはその晩、私の部屋にやってきた。
彼は閏違いなく私にしがみついて甘え、こっそりとシャーロットの話を切り出す。
シャーロットは20日間監禁された。
ラント・アグリチェは、シャーロットが自分の命に反して勝手に地下監獄に入ったうえ、カシスの拘束具を壊したことで大きく怒ったようだ。
私はこの結果に非常に満足している。
「おもちゃがちょっと壊れたみたいだけど、行かなくてもいいの?」
深海のような青い目が私をじっと見つめる。
ジェレミーは黒髪以外にランド・アグリチェにあまり似ていなくてよかったと思った。
もし彼の外見が父親を連想させたなら、こんなに近くで顔を合わせる時、自分でも知らないうちに拒否感を表出したかも知れないから。
「大した傷でもないというのに、どうして?」
私はジェレミーの頭をなでながらゆっくりと話し続けた。
「シャーロットが手を出したのが気に入らないけど、どうせ父から罰を受けるから、私が出る必要はないでしょう」
ジェレミーがカシスのことで私を探ろうとしているのを知って、私はわざと無感覚な反応を見せた。
「ふーん、そうなの?」
私がカシスの様子を見に行くつもりはないということを知って、ジェレミーはそうでないふりをしても確かに機嫌が良くなったようだ。
ジェレミーは以前よりもいっそうはっきりとした笑顔で再び口を開いた。
「姉ちゃん、これから私がシャーロットを地下に近づけないようにしようか?」
シャーロットをけしかけて地下牢に入るようにしたのはジェレミーに違いない。
ところが、彼はこれから私のために先頭に立ってシャーロットを阻止するという意思を表明していた。
すべての真実を知っている私の立場ではかなり面白いことだ。
「ほっといていいわ。あの子も命がもったいなければ自分で体を買うだろう。私も二度は許さないから」
もちろん、シャーロットはしばらく処罰の部屋に入っていて、カシスの近くに近づくこともできないだろうが。
「ジェレミー、あなたはシャーロットのように私のおもちゃには手を出さないわよね?」
私は優しくささやきながらジェレミーの髪を撫でた。
「あなたは私が唯一大事にしている私の優しい弟じゃない」
その瞬間、ジェレミーがびくっとする。
しかし、それは極めて刹那の瞬間だった。
すぐ彼は平然と私に向かって笑いながら答えた。
「当然だよ。姉ちゃんが嫌がることはしない」
・
・
・
「シャーロット、あの病身みたいなものが」
ジェレミーはロクサナの部屋から出て廊下を歩きながら苛立たしく頭を下げた。
少なくともあの子を半殺しにするべきだった。
「まあ、いずれ廃棄処分にされてしまうだろう」
氷のような瞳がひんやりと輝く。
ジェレミーはまだ地下に閉じ込められているカシス・ぺデリアンを殺してしまいたかった。
しかし、彼はこれ以上ロクサナのおもちゃに間接的にでも触れることができなかった。
ロクサナに「唯一大切にしている弟」とまで言われてしまったが、これ以上彼女の信頼に反することをするのはジェレミーにとってありえないことだ。
(くそっ、このキレるのに胸がいっぱいになるような気分は一体何だ?)
ジェレミーは妙な気持ちで後ろ髪をかきながら自分の部屋に向かう。