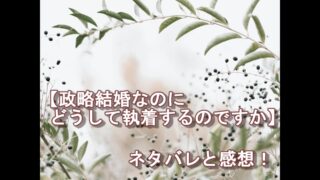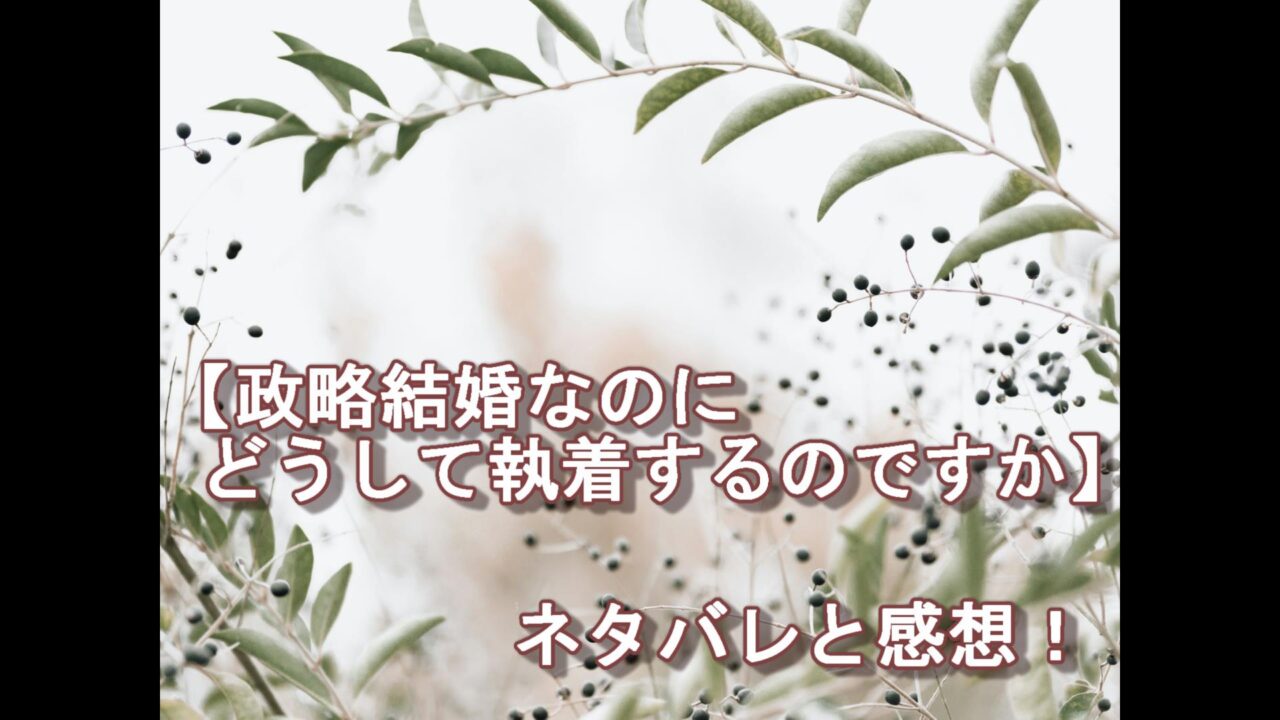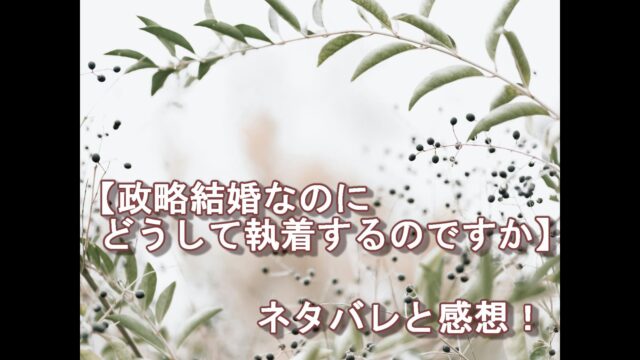こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
今回は68話をまとめました。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

68話 ネタバレ
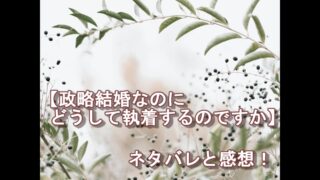
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- 不愉快な記憶②
ナディアは自分に伝えられた事実を全て聞いて、ただ茫然とするしかなかった。
「つまり、王子をそのまま帰したということですか?」
「聞いた話では、そうだと伺っています。」
「な、なんですって・・・!」
王族の家庭教師の役割を果たすのは、通常の学者ではない。
血統、学問、知識など・・・すべての面で最高の地位にいる貴族中の貴族である必要があるのだ。
リアムがいない間に評判を取り戻さなければならない彼らにとって、フレイとしては彼らと対立する理由はなかった。
さらに、彼は遅れて信頼を取り戻さなければならない立場ではないのだろうか?
迎え入れたばかりの家庭教師と初日から争うなんて、これから王子を導く学者が現れない可能性もある。
勇気を出して行動しようとしたナディアが一瞬止まった。
何かが妙だと感じたのだ。
性格が穏やかであることは、フレイの数少ない長所の一つではないか?
彼がこんなに無分別な行動をするのは珍しい。
彼女は事実確認のため再度尋ねた。
「つまり、軍が再び集結した王子を初日から追い回していたということですか?」
「はい、そのようです。」
「おかしいですね。そんな人ではないのに・・・。」
聞いた話だけでは限界があるため、直接尋ねに行くしかなかった。
馬車に足をかけたナディアはすぐに地面へ飛び降りる。
そして来た道を引き返すように走り始めた。
背後からファビアンの慌てた声が聞こえてきた。
「どこに行かれるのですか、奥様?」
「どこに行くって?問題が発生したんだから、それを解決しないと!」
父を避けて首都を離れる前に、フレイに関する問題を片付ける必要がある。
王子宮に向かう彼女が通り過ぎた侍従を捕まえて言った。
「王子殿下はどこにいらっしゃいますか?」
「えっ?失礼ですが、奥様、身分を明らかにしてくださいませんか・・・。」
「私はウィンターフェル侯爵家の夫人、ナディア・ウィンターフェルです!すぐにあなたの主人に伝えなさい。緊急事態なのだから!」
「えっ?あ、はい!」
若い侍従はどこかへ慌てて走り去った。
ナディアはすぐにフレイに案内されることができた。
他に訪問客がいなかったおかげだ。
ガサッ。
彼女は乾いた小枝を踏みながら、王子が座っているベンチへと近づく。
ベンチに座り、力なくぐったりとしているフレイの姿が見える。
力尽きた表情から、彼の心情を少しうかがうことができた。
ナディアが口を開いて言った。
「ここにいらっしゃったんですね。」
それでようやく、力なく横たわっていた王子がゆっくりと体を起こす。
彼は無理に笑顔を作りながら答えた。
「また会いましたね、侯爵夫人。」
「私もまたお会いできて嬉しいです。」
「母上に会いに宮殿に入ったと聞いていましたが、まさかここまで来られるとは思いませんでした。」
「王宮の侍女たちが王子殿下とススンの間で争いがあったと噂が広まっているそうです。」
「それがもう噂になっているのか?」
力のない表情をしていたフレイの顔に驚きが浮かんだ。
「は・・・。まあ、王宮とはそういう場所だ。」
そんな場所だと知っていれば問題を起こさないようにすべきだった。
嫌味が喉元まで出かかったが、ナディアは耐える。
(あの無神経な性格にまともにやり合おうとは思わないが・・・。何か感情的に溜まっているものがあったに違いない。)
まず、ファビアンがまだ把握できていない、全く伝えられていない状況を把握するのが最優先だ。
ナディアは毅然と立っている宮廷人たちに向かって言った。
「あなたたちは下がりなさい。」
すると、召使いや侍女たちが目でフレイに同意を求める。
彼らは主人が無言で頷くのを確認した後、ようやく足を引きずりながら立ち去った。
フレイが尋ねた。
「それで、宮廷人たちはどうして?」
「殿下が声に出して言いづらいことがおありだと思いまして。状況を知りたいのです。一体何があったのですか?」
「・・・」
ナディアはできるだけ優しく、相手を刺激しないように努めながら、再度問いかけた。
「第二王子がご滞在されている間、殿下は模範的な王位継承者の姿を見せる必要があります。そして、連れてこられた僧侶と争うことは、その模範的な姿からは大きくかけ離れています。それでも怒りを示されたということは、それ相応の理由があったはずです。」
「・・・」
「殿下が普段から衝突を好む方ではないことは、よく存じております。理由もなく苛立ちを示される方ではないこともよく存じています。ですから、どのような事情があったのか、お話しください。」
「はあ、侯爵夫人・・・」
ナディアの忍耐が功を奏した。
プレイが潤んだ目で彼女を見つめたのだ。
「私を本当に信じてくれるのか?咎めるつもりじゃないのか?」
「すべての衝突には原因があるものです。私はあなたにそれ相応の理由があったのだと信じています。」
「・・・!」
プレイは感動した面持ちで彼女を見つめた。
そして、まるで駄々をこねる子供のように不平不満を漏らし始める。
内容はおおむねこんな感じだった。
「私は本当にうまくやろうとしたんだ。一度私を教えてくれたスゥスを頼り、もう一度授業をお願いするくらいにはね。でも、まともに授業をするわけでもなく、むしろ本の内容を要約しろと言ったり、理解できないのが不思議だと言ったりして、無礼なことを平気で言ってくるんだよ。それができたなら最初から独学してたってば!」
貴族出身の学者たちはいつもそうだった。
事情を知らない者がいれば、彼らは愚か者だと思ったに違いない。
どれだけ一生懸命努力している姿を見せても、二ヶ月を越えずに辞職するのだ。
そして気がつけば、彼は最短記録を更新していた。
言葉の一つ一つがどうしてこんなにも人の自尊心を傷つけるのか・・・。
夫人も自分の立場になれば分かるだろう。
それでも再び私の元を訪れてくれて、なんとかうまくやり過ごそうと努力した。
今回は本当に自分の役割を果たして認めてもらいたかった。
それなのに・・・。
「またこんなことになってしまった・・・。」
はあ、と彼の口から深い溜息が漏れる。
そして彼はしおれた野菜のようにベンチの上に力なく横たわった。
ナディアはフレイが言った言葉を再び思い返しながら口を開いた。
「王子たちが全員、二ヶ月を超えずに辞職したというのですか・・・?」
「彼らには私の才能が低く見えたのだろう。教える価値がないと判断し、諦めたのかもしれない。そう・・・そう考えると、彼らの間違いだけではないな。私の成長が遅すぎたのが根本的な原因だったのだろうな・・・。」
「・・・。」
ナディアの表情が曇る。
密かに抱いていた希望が薄れていくのが目に見えるようだった。
(何かがおかしい。)
王族のススン(家庭教師)というのは非常に名誉ある職務だ。
どんな弟子であれ、そのような名誉ある地位をたった二ヶ月で辞めるなんて考えられない。
「一つだけよろしいでしょうか?」
「ん?」
「今まで王子を教えた家庭教師たちは、どのような方式で選ばれたのでしょうか?」
「ほとんどは母親の推薦で決まった。今日叱られて出て行った者は別として。」
いや、そいつもおそらく王妃と関わりがある人物だろう。
ナディアはそう確信した。
事態の進行がどうなっているのか、ようやく理解が及んだ。
(直接関与すれば非難を受けるだろうから、もっと知的な方法を使ったのだろう。)
自尊心を容赦なく叩き潰し、自己意識を芽生えさせる方法だ。
多くの学者たちが、自分では教えることができないと諦めて去っていった記憶は、脳に強烈に刻み込まれるだろう。
年齢が幼ければ幼いほど、他人から拒絶された経験は容易に忘れられるものではない。
同じことを繰り返して経験した幼い王子が無気力を学び取ってしまったことも、学者たちがこれ以上関わりたくないと諦めて去ったことも当然と言えば当然だ。
幼い頃のナディアが自分の才能を開花させられなかったのと同じように。
(この人を首都に放っておいてはならない。)
そう判断した彼女は再び口を開いた。
「私が見たところ、歴代の王子たちが皆短期間で辞職した理由は、他の誰かの干渉があったからではないでしょうか。」
「えっ? 誰がそんなことを・・・まさか母上か?」
「その可能性が高いでしょう。王子たちの教育を担うのは王妃の責務ですから。」
「え、ええ・・・そうなのか?」
フレイの表情が呆然とした。
考えてみると確かにその通りだ。
リアムが以前から自分を敵視していたことを彼はようやく悟ったようだった。
「これが今回の件で明確になったことだ。そうなると、彼の親族である王妃も同じように関与しているのだろうか?」
ナディアが再び口を開いた。
「私の考えでは、当面の間、首都を離れるのが良いかと思います。私の父の影響力から抜け出す必要がありますから。それに、殿下の義理の伯母であるオーデル伯爵の領地が適切かと存じます。」
まずは適切な保護者のもとで正しい教育を受けるべきだ。
オーデル伯爵であればフレイの外戚なので、干渉を防ぐことも期待できる。
「それは・・・。」
だが、良い方法だと考えた割には、本人の反応が冴えなかった。
フレイは渋い顔で答えた。
「義理の伯母が私を歓迎してくれるかどうかは分からない。」
「どうしてですか?甥が王位に就けば利益になるはずで、害にはならないでしょう。」
「そう考えたなら、本当に私を支えてくれていただろう。彼女が私に失望していたのなら、とっくに領地に戻って私に連絡することもなかったはずだ。首都の出来事に関わる気もないように思わないか?」
「・・・。」
「私がリアムに対して警戒しなければならないという義理の伯母の意図かもしれない。叔母をずっと無視していた結果だ。その程度の状況判断力しかないなら、弟に王位を譲るほうがいい。廃位の日を待つことが、この国を破滅に向かわせる道だろうな。」
「・・・。」
ナディアの表情が険しく変わった。
叔母が態度を改めず進んでいく様子が気に入らないのは理解できたが、言葉が少々厳しいものだった。
「それに、私のせいで騒ぎが起こったという根拠のない噂が広まった時も、私を探しに来ることはなかった。誕生日のお祝いで首都に来ていたのに、まったくの無視だ。」
「・・・。」
「私は怖い。無闇に外戚を探しに行ったところで、また何を言われるか分からない・・・。」
しおれた彼の顔には、いくつもの感情が入り混じっていた。
悲しみ、怒り、絶望、恐れ、期待、そして挫折。
このような状況の人間を動かすのは容易ではない。
どうすればフレイが外戚との関係修復を試みる気になれるだろうか?