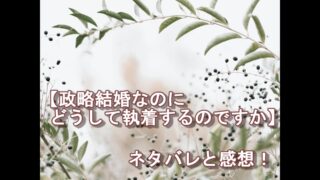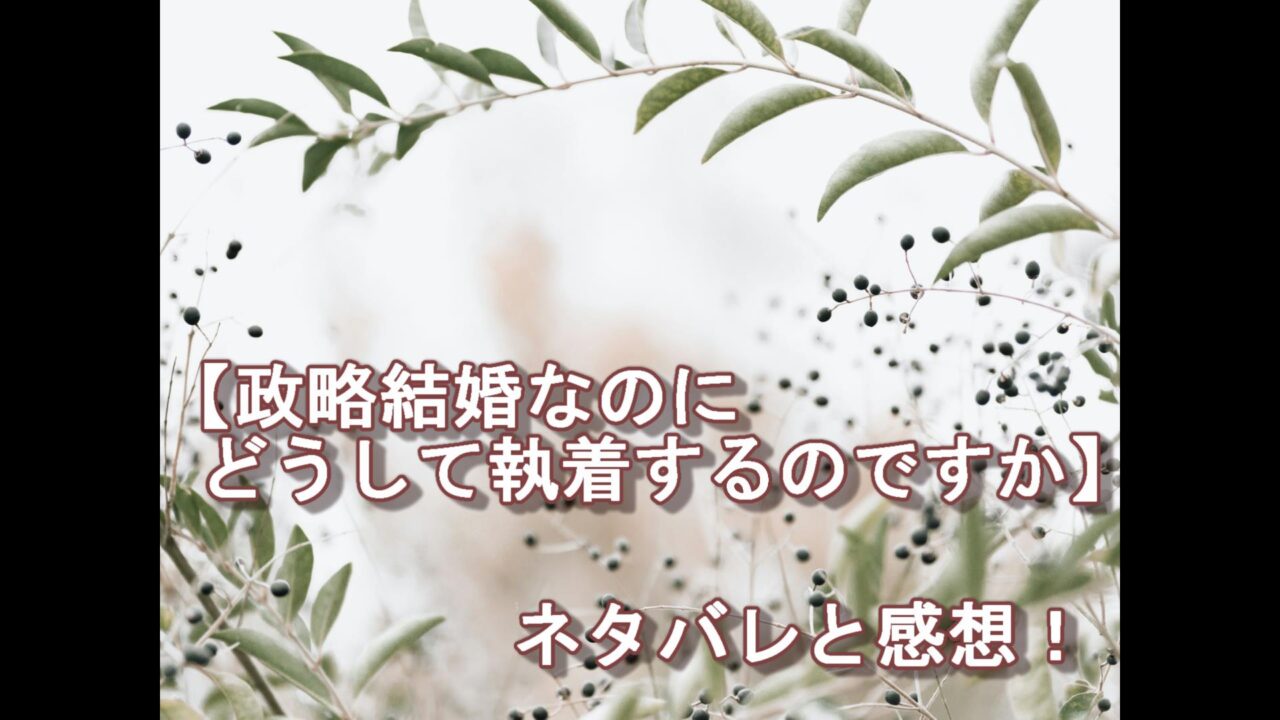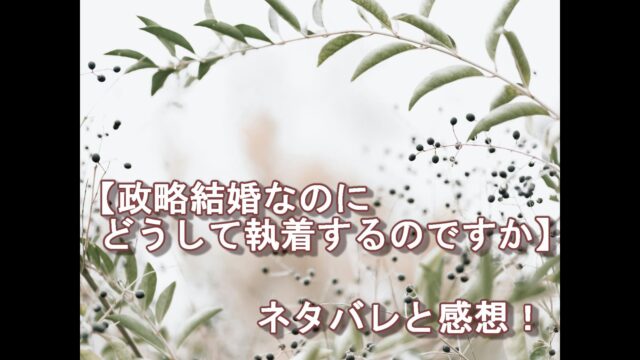こんにちは、ピッコです。
「政略結婚なのにどうして執着するのですか?」を紹介させていただきます。
ネタバレ満載の紹介となっております。
漫画のネタバレを読みたくない方は、ブラウザバックを推奨しております。
又、登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。

86話 ネタバレ
登場人物に違いが生じる場合がございますので、あらかじめお詫びさせていただきます。
- それぞれの戦場④
「……。」
グレンの表情が徐々に険しくなった。
心が急いているため、感情を隠しきれなかった。
「つまり、今ベラクサスの住民たちの命を諦めようというのか?」
「言葉を慎みなさい!まるで私たちを悪役に仕立てようとしているかのようだ。」
「侯爵様、私たちは救える命だけでもまず救おうと言っているのです。ああ、そうだ。まだこの城にも生存者が残っているかもしれません。近くにいる者たちから救出するのが効率的ではありませんか?」
「その通りだ。城に残っているかもしれない者たちを救うのが先だ。」
「……。」
グレンの瞼が小刻みに震え始めた。
内心が明らかに見えている。
『これ以上の被害を出したくないということだな。』
侵略軍が退却したからといって、平和が訪れるわけではない。
やむを得ない状況で一時的に手を組んだだけであり、彼らは元々諍いが絶えない関係ではなかったのか?
近い将来、互いに剣を向け合うことになるかもしれない状況では、戦力を失うリスクを恐れているのだろう。
「つまり、見捨てるべき命は見捨てるということか。」
「感情的にならず、理性的に判断しなければなりません。」
「一体……人の命を見捨てるなどと、そんなことをどうして簡単に……。」
「もしどうしても納得できないのであれば、侯爵様が率先して先頭に立ち出発してください。我々は少し整えた後、すぐに追従します。」
「そうです。追撃を主張されるならば、まず模範を示されるべきではありませんか?」
「……。」
歯を食いしばりながら、グレンは顔に拳を振り下ろさないよう必死に抑えた。
彼は生涯で使い切るであろう忍耐力をすべて振り絞らなければならなかった。
彼らの中でまともに従ってくる者は誰もいなかったが、グレンはかろうじて怒りを抑え込む。
『いや、後からしれっと追いかけてきて名分を立てる真似くらいはするつもりか。我々が命を懸けた後になってからだろうが。』
その痛みが怒りによるものなのか、屈辱によるものなのかは、もはや自分でも分からなかった。
苛立ちを押し殺した彼が後ろを振り返ると、他の忠臣たちが先に足を進め始めていた。
「さあ、さあ。それでは私たちはこれで整った話として進めるとしましょう。皆さん、早く手分けして生存者を探しましょう。」
「城に食料が残っているだろうか? とりあえず兵士たちを少し休ませるのが先のようだが。」
「そんなはずはない。持ち出せないものは全て燃やしたに違いない。」
グレンは黙って立ち尽くし、彼らが立ち去る様子を見守るしかなかった。
捕虜を救出しに行くべきだという意見に同調する者も一部いたが、その「一部」であることが問題だった。
残されたこれらの人員の戦力では、まるで岩を針で突くような無力さに過ぎなかった。
名前も知らない捕虜たちよりも、自軍の兵士たちのほうがはるかに重要なのは当然だった。
結局、全員が気まずいまま散会し、会議は形だけで終わってしまった。
グレンが絶望的な表情を浮かべていたその時、ジスカラが慎重に近寄り口を開いた。
「領主様、どうしようもありません。この辺りで引き下がりましょう。」
「……予想はしていたが、なんとも……大した連中だ。一箇所に集まった途端、こんな事態になるとはな。」
こうした不祥事が起こらないことを切に願っていたが、これ以上こうなってしまった以上、どうにもならなかった。
この混乱する状況を最大限利用する以外に方法はない。
「領主様、ここはひとまず幕舎に戻り休息を……。」
「ジスカラ卿、すぐに追撃の準備を整えよ。」
「……え?」
ジスカラの口がぽかんと開いた瞬間だった。
驚いたのは彼だけではなかった。
グレンの言葉を聞いた他の家臣たちも、目を大きく見開いて混乱した様子だった。
「追、追撃に行かれるとおっしゃるのですか? 単独で?」
「ああ。」
「それはなりません!怒りの気持ちは理解しますが、それではただ自ら破滅への道を歩むだけではありませんか……。」
「まず私の話を聞け。」
そう言って、彼は手を挙げ家臣たちを近くに集めた。
「追撃するふりをして、敵と軽い交戦をした後、ただ戻ってくるつもりだ。その後、我々が敗走兵のように戻ってきたという噂を広める。辛うじて命だけを持ち帰ったように装うのだ。」
「……!」
ジスカラの口がさっきよりさらに大きく開いた。
しかし、驚いたこととは別に、彼はその狙いが何であるかを理解することができた。
全員が私欲を前にして貴族の威厳を投げ捨てる中、唯一、人命を最優先する姿勢を示すこと。
それは、ウィンターフェルが他とは異なる高貴な家門であることを明示する行動。
もちろん、その意図をすぐに理解できない者もいたが。
「それで、今この事態がどう進んでいるんだ? 一体何の話でみんな黙り込んで……うっ!?」
一瞬の騒然とした空気がすぐに静まり返った。
ようやく冷静さを取り戻した家臣たちが口を開いた。
「良い……提案だと思います。これで後にウィンターフェルの大きな財産となるでしょう。しかし、その前に急ぎ伝令を送り、この知らせを広めるのがよいのではありませんか?」
「その通りです。魔族の方々が我々が単独で敵軍を追撃したことを知れば、きっと驚かれるに違いありません。」
「そんな心配はいらない。そんなことは起きないからだ。」
「起きないだなんて! 奥様が領主様をどれほど愛しておられるか。もし領主様が自ら危険に飛び込んだと知ったら、一晩中大声で泣き叫ぶでしょうに……。」
「そうじゃない。もう知っているんだ。」
「……え?」
「ナディアもすでに知っていると言っただろう。だから軍に知らせる必要はない。」
彼にこの決断を提案したのは、ナディア本人だったのだ。
『これまでの記録を見れば、魔族の軍勢は何かを奪いたいときには、あらゆるものを破壊し尽くして撤退します。持ち去れないものはすべて焼き払い、生きているものは捕虜として連れて行きます。』
『全員で追撃して捕虜を救おうと意見が一致するなんてことはあり得ないでしょう? それなら、そういった状況になったときに私たちがすべきことは、単独で追撃することです。いや、追撃するふりをするのです。』
『それは金銀財宝でも買えない、ウィンターフェルの財産となるのです。』
ウィンターフェルが単独で魔族軍勢を追撃したという知らせを伝え聞いたならば、ナディアはその場で激昂する代わりに、部屋に戻って微笑むに違いない。
彼女に関しては、何も心配する必要がなかった。
グレンが再び口を開いて言った。
「理解したなら、早速追撃の準備を進めろ。」